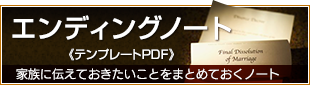「源泉徴収ありの特定口座」のメリット
① 証券会社が源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡所得や配当所得の年間の損益を計算して「年間取引報告書」「特定口座年間取引報告書」を作成してくれる。
② 源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡所得や配当所得の税金の計算をして源泉徴収(納付)してくれるので確定申告が不要。
③ 申告不要を選択した場合、その口座内で生じた上場株式等の譲渡所得、配当所得の金額及び利子所得の金額については合計所得金額に算入されないので、所得控除の適用要件や国民健康保険の保険料、医療費の窓口負担割合などに影響しない。
④ 特定口座内の国内の上場株式等だけが、特定管理株式等の価値喪失による「みなし譲渡損失の特例」を適用することができる(源泉徴収なしの特定口座も適用可能)。
「源泉徴収ありの特定口座」のデメリット
① 源泉徴収口座以外の口座や他の証券会社の損益と損益通算するには申告が必要。
② 源泉徴収口座の譲渡損失の繰越控除を利用するためには申告が必要。
また、源泉徴収口座の譲渡損失を申告する場合、その源泉徴収口座内の株式等の配当金所得の金額及び利子所得に金額をすべて申告しなければならない。
③ 上場株式の配当金の受取り方法を「株式数比例配分方式」(図表2-10-2参照)に設定していないと、特定口座内で上場株式の配当金を受け取ることができない※。
④ 上場株式等の配当金等は、原則として、1回に支払を受けるごと(銘柄別の支払時期ごと)に確定申告・申告不要の選択をすることができるが、特定口座に受け入れた上場株式等の配当金等については、特定口座ごとに確定申告するかしないかの選択をしなければならない(譲渡損失を申告する場合はすべて申告(上記②参照))。
⑤ 特定口座の株式等の譲渡日は「受渡日」が基準となるので「約定日」を選択することができない(年末における「益出し」「損出し」の調整期間が短くなる。)。
⑥ 特定口座の取得価額については、同一銘柄を同一日に売買した場合、「売」と「買」の実際の順序に関係なく、先にすべての「買」が行われ、その後にすべての「売」がされたものとして処理される(「クロス取引」で「益出し」「損出し」ができない。)。
⑦ 特定口座の「源泉徴収あり・なし」の変更は、毎年最初に上場株式等の譲渡をする時までにできるが、前年に「源泉徴収あり」を選択していた場合で、本年最初に上場株式等の譲渡をする時より前にその特定口座に上場株式等の配当金等を受け入れていたときは、変更することはできない。
不動産所得を生ずべき不動産等の貸付けが、「事業的規模」か「事業的規模に至らない規模(業務的規模)」かにより、不動産所得の金額の計算における「資産損失」「事業専従者給与」「青色申告特別控除」等の取扱いが異なります。
事業的規模の判定は、原則として、社会通念上事業と称する程度の規模で不動産貸付けを行っているかどうかにより判断しますが、次のいずれかに該当する場合は、特に反証がない限り事業として取り扱われています(基通26-9)。
事業的規模の判定基準(形式基準)
建物の場合、貸間、アパ-ト等の独立した室数が、おおむね10室以上、独立した家屋の貸家数が、おおむね5棟以上
土地の場合、土地、駐車場の契約件数が、おおむね50件以上(1室の貸付けに相当する土地の契約件数をおおむね5件として判定)
(注) 例えば貸室数が8室と貸地の契約件数が15件の場合、貸室8室+(貸地15件÷5=3)=11室となり、事業的規模と判定されます。
なお、実質基準として、賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等からみて、上記の形式基準に準じる事情があると認められる場合には、事業として取り扱うこととなります。これは、いわゆる5棟10室の基準を満たさないものの、賃貸収入が比較的多額で、かつ、不動産管理に係る役務の提供の事務量を相当要するような場合における事実認定による判定となります。しかし、この実質基準での判定の場合には、事業所得としての性質として掲げられる各性質(営利性・有償性、反復・継続性、自己の危険と計算における事業遂行性、精神的・肉体的労力の程度、人的・物的設備の有無など)を総合的に判断することとなりますので、非常に難しいものとなります(平成19年12月4日裁決)。
被相続人の財産にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(債務)もあります。そのため、相続人は相続の開始があったことを知ったときから3ケ月以内(熟慮期間といいます)に、単純承認、限定承認、相続放棄のうちいずれかを選択することができます。
(1) 単純承認
相続人が単純承認したときは、無限に被相続人の権利義務を承継します。したがって、被相続人の遺した財産がプラスの財産よりマイナスの財産のほうが多くて弁済しきれないときには、相続人は自分の財産で弁済しなければなりません。
単純承認は特に必要な手続きはなく、次のような場合には単純承認したものとみなされます。
(ア) 熟慮期間内に限定承認又は相続放棄をしなかった場合
(イ) いずれかを選択する前に相続財産の全部又は一部の処分した場合
(ウ) 限定承認又は相続放棄をした後で、相続財産の全部又は一部を隠匿、
消費等した場合
(2) 限定承認
限定承認とは、相続によって得たプラスの財産を限度として、被相続人の債務及び遺贈を弁済する相続の方法です。つまり、相続財産で被相続人の債務や遺贈を支払い(残った債務は返済しなくて可)、相続財産が残ればそれを相続できる、というものです。
限定承認をする場合は、相続人全員で、熟慮期間内に相続財産の財産目録を家庭裁判所に提出し、限定承認する旨を申述します。
(3) 相続放棄
相続放棄とは、相続財産(プラスの財産・マイナスの財産)を一切引き継がないという意思表示であり、相続放棄をする場合には相続人単独で家庭裁判所にその旨を申述します。
相続放棄をした場合、民法上は初めから相続人とならなかったとみなされますので、相続欠格や廃除とは異なり代襲相続はおきませんが、相続人や相続分に変更が生じます。
相続とは、死亡した人(「被相続人」といいます)が所有していた財産上の権利義務を一定の身分関係にある人(「相続人」といいます)に承継することです。相続は、通常、死亡によって開始します(特殊なケースとして、失踪宣告がされた場合も相続は開始します)。
(1) 自然的死亡
自然的死亡とは、老衰、病気、事故等により現実に死亡という事実が生じた場合をいい、その具体的な時期は、通常、医師が死亡診断書または死体検案書に記載した「死亡の年月日時分」となります。相続人等の利害関係人において死亡の事実を了知した日、死亡の届出日、死亡した旨が戸籍簿に記載された日のいずれでもありません。
(2) 失踪宣告
失踪宣告とは、不在者につき,その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪),又は戦争、船舶の沈没、震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)、家庭裁判所への申立てにより、生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。
(3) 認定死亡
認定死亡とは、水難、火災その他の事変によって、死亡したのは確実であるが、遺体が見つからない等の場合に、その取調べにあたった官公署が死亡の認定をして、戸籍上一応死亡として扱います(戸籍法第89条、第91条)。
為替差損益は、原則的には異なる通貨の交換(往復)により発生します。例えば、円貨を外貨に交換し、その外貨を円貨に交換した時(円転した時)に、所得税法第36条の「収入すべき金額」が実現したと考えられますので、その実現した金額を為替差損益として雑所得の所得計算を行います。
したがって、購入した外国通貨をそのまま保有し続ける限りにおいては、為替差損益については未実現の評価損益に過ぎないものと考えられますので、所得として認識する必要はありません。また、外貨建預金として預け入れていた元本部分の金銭について、①同一の金融機関に、②同一の通貨で、③継続して預け入れる場合の預貯金の預け入れも、外貨建取引に該当しない(円換算しない)こととされていますので、その元本分部に係る為替差損益が所得として認識されることはありません(令167の6②)。(なお、実務的には、他の金融機関に預け入れる場合であっても、同一の外国通貨で行われる限り、令167の6②の預け入れに類するものとして、同様に扱われています。)
ただ、為替差損益は異なる通貨の交換(往復)の場合に発生するだけではなく、異なる通貨の交換(往復)以外にも、為替差損益が実現したと認識しなければならない場合があります(新たな経済的価値が外部から流入したことにより、それまでは評価差額にすぎなかった為替差損益に相当するものが、所得税法第36条の「収入すべき金額」として実現したこととなる場合)。
 詳しくはこちら
詳しくはこちら
退職所得の選択課税とは、非居住者が受けるべき退職所得でその支払の基因となった退職に基づいて、その年中に支払いを受けるべきものの総額を、居住者として支払を受けたものとみなして計算した場合の税額が、その退職所得についてその支払の際に源泉徴収された税額よりも少額である場合には、確定申告を行うことによって、その差額の還付を受けることができる制度です(法171、172、173)。この場合、基礎控除等所得控除は一切適用されません。また、受給者が選択課税を受ける場合であっても、退職手当等の支払者はその支払の際に、国内源泉所得部分に対して20%(平成25年から平成49年までは、20.42%)の税率で源泉徴収を行う必要があります。なお、退職所得の選択課税は、常にその選択を受けた方が有利とは限りません。例えば、居住者としての勤務期間が比較的短期間である場合には、20.42%の源泉徴収税額の方が少額となることもあります。
【退職所得の選択課税の手続き要件】
退職所得の選択課税を受けようとするときは、その源泉徴収された税額の全部又は一部の還付を受けるためにその年の翌年1月1日(同日前に選択課税の対象となる退職所得の総額が確定した場合には、その確定した日)から5年以内に、以下の事項を記載した申告書を所轄税務署長に提出しなければなりません(法173、令297、規70)。
① 退職所得の総額及びその総額について退職所得控除額を控除し、その控除後の1/2相当額について計算した所得税等の額
② 退職所得について源泉徴収された又は源泉徴収されるべき所得税等の額
③ ①の税額から②の税額を控除した額
 詳しくはこちら
詳しくはこちら
【居住者】
□ 住宅を取得した時は、非居住者ではないか。
☞ 住宅の売買契約時及び先行取得の土地の取得時は非居住者であっても構いませんが、住宅の取得時(引渡しを受けた時)は居住者でなければなりません。
□ 公務員が海外転勤中に住宅を取得した場合、控除が受けられないとしていない。
☞ 国家公務員、地方公務員(日本国籍を有しない者及び日本国籍を有していても
現に国外に居住し、かつ、その地に永住すると認められる者を除く)は、海外に滞在する期間も日本国内に住所を有するものとみなして所得税法の規定を適用することとされています。
【留守家族の範囲】
□ 単身赴任の場合に、留守家族である「配偶者」は控除対象配偶者に限定されていると考えていないか。
☞ 配偶者の場合は、あなたと生計を一にしているかどうかにかかわらず、単身赴任が解消した後は配偶者と共に居住すると認められるのであれば、あなた自身が入居し引き続き居住の用に供しているものとして取扱われます。
□ 妻子のほか両親と同居してきたが、転勤命令を受け、転勤先に妻子を伴い転居した場 合、引き続き居住しているのが両親だけのため控除が受けられないとしていないか。
☞ 両親であっても、転居前において同居し、かつ、生計を一にしている場合には、転勤が解消した後は両親と共に居住すると認められるのであれば、あなた自身が入居し引き続き居住の用に供しているものとして取扱われます。 なお、転勤に伴う転居前には同居していなかった両親に留守を預かってもらう場合は、たとえ両親と生計を一にしていたとしても、本人が引き続き居住の用に供しているものとする取扱いを受けることはできません。
【やむを得ない事情】
□ 離婚後、元妻とともに生計を一にする子が引き続き居住する場合に、控除が受けられるとしていないか。
☞ 仮に離婚が「やむを得ない事情(措通41-1,41-2)」に当たるとしても、その事情が解消した後は、あなたがその子とともに居住するとは認められませんので、控除は受けられません。
□ 親の介護のために妻子を残して一時的に転居した場合に、控除が受けられないとしていないか。
☞ 「やむを得ない事情(措通41-1,41-2)」には、転勤のような外的な要因に伴う事情だけでなく、転地療養のような個人的な事情も含まれますので、親の介護も「やむを得ない事情」に該当します。
□ 転地療養のため家族全員で一時実家に移り住んだ場合に、「再居住の場合の再適用の特例」を受けられるとしていないか。
☞ 転地療養は、勤務先からの転任命令のような外的要因ではなく、個人的事情であり、これに伴い家族とともに転居する場合は「再居住の場合の再適用の特例」の要件である「やむを得ない事情(措法41⑱)」には該当しないこととなります。
□ 夫が転任命令を受け転居するが、妻は夫に同行するため会社を休職する場合、再び居住の用に供したとしても、夫は「再居住の場合の再適用の特例」を受けられるが、妻は受けられないとしていないか。
☞ 妻の転居は妻の勤務先からの転任命令等やむを得ない直接的な事情があるわけではありませんが、夫の転任命令という外的な要因に基因していますので、「再居住の場合の再適用の特例」の要件である「やむを得ない事情(措法41⑱)」に該当することとなります。
【賃貸】
□ 転勤が解消し帰ってきた年に賃貸していた場合に、年末時点では居住しているとして 控除を受けていないか。
☞ 帰ってきた年に賃貸していた場合は、翌年から控除が受けられることとなります。
□ 当初3年の予定であった転任期間中に3年契約で住宅を賃貸していたが、1年で転勤が解消された場合に、2年間他の物件を賃貸することとなったため、控除は受けられないとしていないか。
☞ 再び居住の用に供する日について、そのやむを得ない事情の解消後、直ちに再居住するとか、1年以内に再居住するとかいった制約があるわけではないため、その住宅に係る賃貸借が終了し、再び居住の用に供した時は、その翌年から残っている期間について控除を受けることができます。
 詳しくはこちら
詳しくはこちら