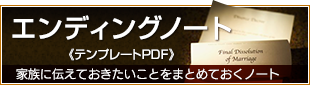現在、税務署を被告として延滞税の賦課に関する無効確認訴訟及び国家賠償法を求める訴訟を東京地裁に提起しています。税務署(国)を相手に税務訴訟した場合の納税者の勝訴率は国税庁の統計資料によれば、、7.6%となっています。
なお、税理士が保佐人として関与した場合の納税者の勝訴割合は、25.57%と、平成22年度国税庁統計資料の3.3倍を超えています。
限定承認した場合
相続人が限定承認をした場合には、被相続人の有する資産(譲渡所得の基因となる資産に限ります)については、その相続時における時価により譲渡があったものとみなされます(所法59)。
したがって、被相続人の有する資産に含み益がある場合には、準確定申告の際に、被相続人にかかる所得税として課税されることになります。ただし、相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ所得税を納付する責任を負います。
また、遺言により法人に対して遺贈があった場合においても、その相続時における時価により譲渡があったものとみなされます。
配当所得の損益通算と扶養控除等
平成21年分の所得税確定申告から、「上場株式等に係る配当所得」と「株式等の譲渡損失及び過去3年以内に生じた繰越損失」が通算することができるようになりました。
株式の売買により損をされた方は、上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択することで、上場株式等の配当金から源泉徴収された所得税が還付されます。
この通算制度を適用した場合の配偶者控除や扶養控除の判定については、上場株式等の配当所得と株式等の譲渡損失の損益通算後の所得をもって控除対象の判定をします。
(設 例)
扶養控除判定対象者の所得が、上場株式等の配当所得 95万円 、株式等の譲渡損失 △80万円の場合、通算後の所得金額が15万円となり、所得金額が38万円を超えないため、配偶者控除や扶養控除が受けられることになります。
①通算後の所得 95万円-80万円=15万円
②控除の判定となる合計所得金額 15万円 ≦ 38万円
一方、配偶者や扶養親族が、その年の上場株式等の配当所得と過去から繰り越してきた株式等の損失との通算をした場合、配偶者控除や扶養控除の判定については、株式等の繰越損失の損益通算前の配当所得で判定することになります。
(設 例)
扶養控除判定対象者の所得が、上場株式等の配当所得 95万円 、株式等の譲渡損失 △80万円の場合、通算後の所得金額が15万円となりますが、株式等の繰越損失の損益通算前の所得金額が38万円(95万円)を超えるため、配偶者控除や扶養控除が受けられません。
①通算後の所得 95万円-80万円=15万円
相続の開始時期
相続は、通常、人の死亡によって開始します(「自然的死亡」といいます)。
また、特殊なケースとして、生死不明の者に対して家庭裁判所が失踪宣告をした場合(「擬制死亡」といいます)や災害等により遺体が見つからない者に対して官公署が死亡を認定した場合(「認定死亡」といいます)にも相続は開始します。
「相続の開始時期」については、相続税の申告書の提出期限や納付期限等を判断する場合に問題となります。
(1) 自然的死亡
自然的死亡とは、老衰、病気、事故等により現実に死亡という事実が生じた場合をいい、その具体的な時期は、通常、医師が死亡診断書又は死体検案書に記載した「死亡の年月日時分」となります(民法882)。相続人等の利害関係人において死亡の事実を了知した日、死亡の届出日、死亡した旨が戸籍簿に記載された日のいずれでもありません。
(2) 擬制死亡
擬制死亡とは、不在者の生死が7年間明らかでないとき(「普通失踪」といいます),又は戦争、船舶の沈没、震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(「危難失踪」といいます)、家庭裁判所への申立てにより、生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です(民法30、31)。
(3) 認定死亡
認定死亡とは、水難、火災その他の事変によって、死亡したのは確実であるが、遺体が見つからない等の場合に、その取調べにあたった官公署が死亡地の市町村長に死亡の報告をして、戸籍上一応死亡として扱う制度です(戸籍法89、91)。
更正の請求の改正について
平成23年度税制改正に関する法律「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)が平成23年12月2日に公布され、「更正の請求」が次のとおり改正内容されました。
1. 更正の請求期間の延長
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。
なお、平成23年12月1日以前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年となりますが、増額更正(所得税であれば3年、法人税であれば5年)ができる期間内に「更正の申出書」の提出があれば、調査によりその内容の検討をして、納めすぎの税金があると認められた場合には、減額の更正が行われます。但し、申出のとおり更正されない場合であっても、不服申立てすることはできません。
2. 更正の請求範囲の拡大
当初申告の際、申告書に適用金額を記載した場合に限り適用が可能とされていた措置のうち、下記のような措置については、更正の請求(又は修正申告書)の提出により事後的に適用を受けることができるようになりました。
【所得税関係】
• 給与所得者の特定支出の控除の特例(所法57の2)
• 保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の所得計算の特例(所法64)
• 純損失の繰越控除(所法70)
• 雑損失の繰越控除(所法71)
• 変動所得及び臨時所得の平均課税(所法90)
• 外国税額控除(所法95)
• 資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入(所令182の2)
【法人税関係】
• 受取配当等の益金不算入(法法23、81の4)
• 外国子会社から受ける配当等の益金不算入(法法23の2)
• 国等に対する寄附金、指定寄附金及び特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入(法法37、81の6)
• 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入(法法59)
• 協同組合等の事業分量配当等の損金算入(法法60の2)
• 所得税額控除(法法68、81の14)
• 外国税額控除(法法69、81の15)
• 公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例(法令73の2)
• 引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例(法令113)
• 特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の制限の5倍要件の判定の特例(法令113の2)
• 特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入の対象外となる資産の特例(法令123の8)
• 特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例(法令123の9)
【相続税関係】
• 配偶者に対する相続税額の軽減(相法19の2)
• 贈与税の配偶者控除(相法21の6)
• 相続税における特定贈与財産の控除(相令4)
また、控除等の金額が当初申告の際の申告書に記載された金額に限定される「控除額の制限」がある下記のような措置について、更正の請求(又は修正申告書)の提出により、適正に計算された正当額まで当初申告時の控除等の金額を増額することができることとされました。
【所得税関係】
• 外国税額控除(所法95)
• 試験研究を行った場合の所得税額の特別控除(措法10)
• 試験研究を行った場合の所得税額の特別控除の特例(措法10の2)
• エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の所得税額の特別控除(措法10の2の2)
• 中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除(措法10の3)
• 沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の所得税額の特別控除(措法10の4)
• 雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除(措法10の5)
• 所得税の額から控除される特別控除額の特例(措法10の6)
• 青色申告特別控除(65万円)(措法25の2)
• 電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除(措法41の19の5)
【法人税関係】
• 受取配当等の益金不算入(法法23、81の4)
• 外国子会社から受ける配当等の益金不算入(法法23の2)
• 国等に対する寄附金、指定寄附金及び特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入(法法37、81の6)
• 所得税額控除(法法68、81の14)
• 外国税額控除(法法69、81の15)
• 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(措法42の4、68の9)
• 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例(措法42の4の2、68の9の2)
• エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の5、68の10)
• 中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の6、68の11)
• 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の9、68の13)
• 沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の10、68の14)
• 国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の11、68の15)
• 雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除(措法42の12、68の15の2)
• 法人税の額から控除される特別控除額の特例(措法42の13、68の15の3)
東日本大震災により被害を受けられた方の所得税の特例 2
2.事業所得者等の取扱い
東日本大震災により事業所得者等の有する棚卸資産、事業用資産等に損失(以下、「事業用資産の震災損失」といいます)が生じた場合、納税者は、当該損失額を平成22年分の事業所得の金額等の必要経費に算入するか、平成23年分の必要経費に算入するかを選択することができます。
※事業用資産の震災損失額には、大震災に関連して支出したやむを得ない支出を含みますが、これらの損失について保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる金額がある場合には、その金額を差し引きます。
(1)事業用資産の震災損失額を平成22年分の事業所得の金額等の計算上必要経費に算入する場合
平成21年分から青色申告をしている方は、平成22年分の所得において純損失が生じたときは、平成21年分の所得に繰り戻して所得税の還付請求をすることができます。なお、既に、平成22年分の所得税の確定申告書を提出している方は、平成24年4月26日まで「更正の請求」をすることができます。また、被災純損失金額(純損失の繰戻しの適用を受けていない部分に限ります)については、5年間繰越控除できます。
(2)事業用資産の震災損失額を平成23年分の事業所得の金額等の計算上必要経費に算入する場合
純損失の金額が生じた場合には、純損失の金額のうち次に掲げるものについては、5年間繰り越すことができます。
① 保有する事業用資産等(土地を除きます)に占める事業用資産の震災損失額※の割合が10%以上である方
イ 青色申告の場合
平成23年分の純損失の金額(震災損失額だけでなく、平成23年に生じた他の純損失の金額も含みます)
ロ白色申告の場合
平成23年分の被災事業用資産の損失の金額と変動所得に係る損失の金額による純損失の金額
② 上記①以外の方
事業用資産の震災損失による純損失の金額
東日本大震災により被害を受けられた方の所得税の特例 1
1.雑損控除
東日本大震災により住宅や家財などについて損失が生じた場合、納税者は、平成22年分の雑損控除とするか、平成23年分の雑損控除とするか、いずれかを選択することができます。また、その年分の所得金額から控除しきれない大震災による雑損失の金額がある場合には、5年間繰越控除できます。
なお、平成22年分の雑損控除とした場合には、平成23年において当該損失は生じなかったものとみなされます。また、既に平成22年分の確定申告書を提出している方は、平成24年4月26日までこの特例の適用を受けるための更正の請求をすることができます。
上記の雑損控除に代えて、災害減免法の適用を受けることもできます。この場合も、納税者は、平成22年分で適用を受けるか、平成23年分で適用を受けるか、いずれかを選択することができます。ただし、災害減免法は、当該年分だけの適用になります。
※住宅や家財の損失額は、その損失の生じた時の直前におけるその資産の価額を基として計算することになっていますが、損害を受けた資産について個々に損失額を計算することが困難な場合には、国税庁ホームページ「東日本大震災により損害を受けた場合の所得税の取扱い(情報) 第3 雑損控除における損失額の合理的な計算方法」をご参照ください。
振り込め詐欺は「雑損控除」の対象とならない!
災害、盗難又は横領によって自己又は生計を一にする配偶者やその他の親族で総所得金額等が38万円以下の者の所有する資産に損害を受けた場合や、災害等に関連してやむを得ない支出をした場合に「雑損控除」が受けられます(所得税法第72条)。
この「雑損控除」の対象となる損害は、損害発生原因が被害者の意思に基づかない災害、盗難又は横領によるもの に限られます。そのため、詐欺によりだまされた場合や脅迫により脅し取られた場合の損害は、雑損控除の対象となりません。そのよう理由から、「振り込め詐欺」により損害を受けた場合には「雑損控除」は認められません。
なお、「耐震偽装による損害」は、マンション購入者が販売業者から騙されたような感じがしますが、国税庁が「雑損控除」の対象として認めています。
所得税の確定申告とは?
私たちの生活の中で最も関係深い税金は、「所得税」です。そこで、最初に所得税についてご説明します。所得税は、個人の所得に対して課税する税金で、1月1日から12月31日までの1年間に得た所得を計算して、住所地を管轄する税務署に申告(これを「確定申告」といいます。)しなければなりません。このように自分で所得金額を計算して税金を納める制度を「申告納税制度」といいます。通常、サラリーマンは毎月の給料から所得税等が源泉徴収され、年末に勤務先で所得税の精算(これを「年末調整」といいます。)をしていますので、確定申告をする必要がありません。但し、次のような場合には、サラリーマンでも確定申告が必要となります。
【サラリーマンでも確定申告が必要なケース】
① 給与の年収が2000万円を超える場合
② 給与や退職所得以外の所得金額の合計金額が20万円を超える場合
③ 給与を2ヶ所以上からもらっている場合
④ 給与から源泉徴収がされていない場合
確定申告が必要な方は、所得のあった翌年の2月16日から3月15日までの期間(「確定申告期間」といいます。)に、税務署へ確定申告書を提出しなければなりません。なお、「医療費控除」や「ローン控除」などを申請して所得税の還付を受ける方は、2月16日まで待たなくても、翌年の1月1日から確定申告をすることができます。
所得税は、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計が20万円以下であれば確定申告の必要がありません(上記「サラリーマンでも確定申告が必要なケース」の②)が、住民税にはこのような取扱がないため、所得金額が20万円以下であっても市町村の住民税課(納税課)などに住民税の申告が必要となりますので注意が必要です。
なお、所得がない方であっても国民健康保険加入者の保険料の減額判定や各種福祉関係の所得証明(非課税証明)等の交付などに必要なため、住民税の申告書の提出が必要な場合があります。
税理士が担うべき成年後見制度について
税理士法第1条で、「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」と規定されています。その使命を達成するには高潔な倫理観と高度な専門性が求められていると同時にその職能により社会へ貢献することをも期待されています。一方、成年後見制度は、本人の残存能力の活用及び自己決定権の尊重、そして障害者との共生を目指すノーマライゼーションといった、新たな理念との調和を基本としつつ、社会全体が高齢者の保護に取り組むことを求めています。この成年後見制度は、少子高齢化社会が加速度的に進行する我が国において、これからの国民生活を支える重要な社会基盤と位置付けられる制度です。成年後見人等の業務は、代理権・同意権・取消権の三つの権利行使に立脚していますが、その業務に応じて行使権限は異なっており、また、任意後見人については契約した範囲の代理権行使を前提としています。これらの権利行使内容は広範囲にわたると同時に、社会・経済の多様性の中で、その運用に当たっては高度な専門的知識と的確な判断、そして高い倫理性が求められます。そのため成年後見人等及び任意後見人を従来のように本人の血縁者に頼ることが、成年後見制度が有効に機能しない原因となっている場合もあり、そのことが各分野において質の高い専門家に期待が寄せられている理由となっています。税理士は公共的役割を担っており、業務の遂行には高度な専門性と客観的な判断が必要とされるとともに、高潔な倫理観が求められています。税理士法により、これらの資質の保持を制度的に義務づけられている税理士が、成年後見制度に参加することは、成年後見制度の目的に資するとともに、より高い制度運用が図られる一助になるものと考えられます。特に、税理士は財産管理業務や後見業務の監督といった場面においては、その専門性を遺憾なく発揮できるものと考えられます。