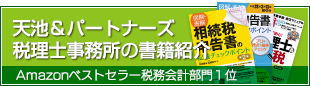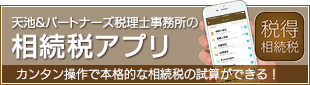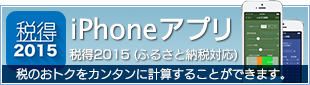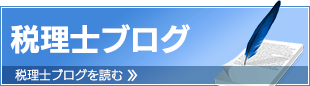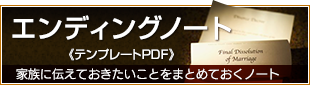税金お役立ち情報

相続税の課税対象財産と非課税財産
相続税の申告において、すべての財産に相続税が課されるわけではなく、課税の対象とならない財産も存在します。
この違いを理解しておくことで、課税リスクを減らし、相続手続きをスムーズに進めることができます。
本記事では、相続税の課税対象財産と非課税財産について紹介します。
相続税の課税対象財産とは?
相続税の課税対象になる財産とは、被相続人が亡くなった時点で所有していた、経済的価値のある財産を指します。
まずは、主な課税対象財産の種類を見ていきます。
プラスの財産
代表的なプラスの財産は、以下のような財産です
現金・預貯金
もっとも一般的なのが、現金や銀行口座の預貯金です。
相続開始時点の残高がそのまま相続財産として評価されます。
定期預金や外貨預金、ネット銀行の口座なども含まれます。
不動産
自宅や土地、賃貸用物件などの不動産も課税対象です。
評価額は路線価や固定資産税評価額を基に算出されます。
不動産は評価方法が複雑になりやすいため、専門家に確認して進めることが推奨されます。
有価証券
株式、公社債、投資信託なども課税対象に含まれます。
上場株式は相続開始日の終値などで評価され、非上場株式は類似業種比準方式などで評価されます。
貸付金・未収金
被相続人が貸していたお金(貸付金)や、未回収の売掛金なども財産とみなされ、相続税の対象となります。
その他の財産
自動車、貴金属、美術品なども課税対象に含まれます。
これらの評価も、原則として相続開始時点での時価や市場価格が基準になります。
マイナスの財産(債務)
「債務」も、相続財産として扱われ、プラスの財産から差し引くことができます。
主な債務としては、以下が挙げられます。
借入金
住宅ローンや事業資金など、被相続人が生前に負っていた借金は債務控除の対象です。
未払い費用
死亡時点で未払いの医療費や税金、クレジットカード代なども債務控除の対象です。
支払内容が確認できる請求書や明細を保管しておくことが大切です。
葬式費用
通夜・告別式・火葬など葬儀に直接かかる費用は控除可能です。
ただし、墓石代や香典返しなどは控除の対象外なので注意が必要です。
みなし相続財産
被相続人の死亡によって取得するもののうち、形式上は相続財産でないものも、「みなし相続財産」として課税対象になるものがあります。
代表的なものとして、生命保険金や、死亡退職金が挙げられます。
生命保険金
被相続人が被保険者かつ保険料を負担していた場合、死亡保険金は「みなし相続財産」として課税対象になります。
ただし、「500万円×法定相続人の数」までの非課税枠があります。
たとえば、法定相続人が3人いる場合、1,500万円までは非課税となり、それを超える部分が課税対象になります。
死亡退職金
会社から支給される死亡退職金も、課税対象になります。
こちらも「500万円×法定相続人の数」まで非課税となります。
相続時精算課税の適用を受けた贈与財産
生前贈与のうち、相続時精算課税制度の適用を受けた財産は、贈与時ではなく相続時にまとめて評価され、相続財産に加算されます。
贈与から何年経っていても相続税の課税対象となる点に注意が必要です。
亡くなる前の7年以内に贈与された財産(暦年課税分)
暦年贈与制度を利用して生前贈与された財産のうち、被相続人の死亡前7年以内の贈与分は、相続財産に加算されます。
基礎控除額110万円以下の贈与財産も加算することになります。
相続税の課税対象とならない財産
以下のような財産は、法律上、相続税の課税対象外となっています。
祭祀財産
お墓、仏壇、位牌などの「祭祀財産」は、文化的・精神的な価値を持つものとされ、相続税の対象外です。
一方で、装飾品などのように資産性が高く、祭祀目的が認められない場合は課税対象になる可能性もあります。
公益目的の寄付財産
相続財産のうち、国や地方公共団体、公益法人などに寄付した財産は非課税になります。
ただし、一定の条件を満たす必要があるため事前に確認が必要です。
まとめ
相続税の課税対象財産と非課税財産を正しく理解することは、スムーズな相続手続きと適切な節税の第一歩です。
現金や不動産などの明確な資産だけでなく、生命保険金や死亡退職金、美術品など多様な財産が対象になる可能性があります。
一方で、非課税となる財産も複数あり、これらを上手に活用することで相続税の負担を軽減することが可能です。
相続に関する状況は人それぞれ異なるため、専門家である税理士と相談しながら進めることをおすすめします。
文責:
-

- 税理士 天池 健治
- 天池 健治 税理士のプロフィール
- 税理士 / 証券アナリスト / 宅建士 / 公認コンサルタント