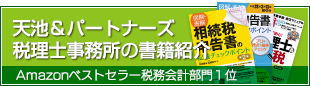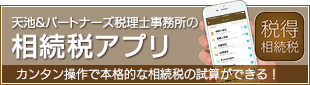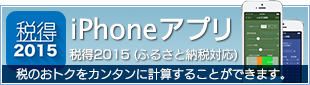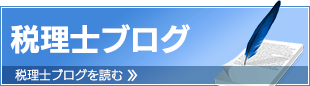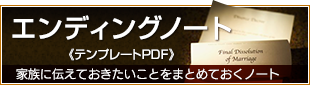税金お役立ち情報

相続税の基礎控除額とは?計算方法も併せて解説
相続が発生すると、遺産の分割だけでなく相続税の負担も大きな問題です。
相続税には基礎控除があり、相続税の負担を軽減してくれます。
本記事では、相続税の基礎控除額の考え方について解説いたします。
相続税とは?
相続税は、被相続人が亡くなったときに遺族などが財産を引き継ぐ際に課される税金です。
現金や預貯金、不動産、有価証券、自動車、貴金属など幅広い財産が課税対象となります。
遺産を受け取った相続人が、それぞれの取得分に応じて税金を負担する仕組みであり、一定額を超える遺産にのみ課税される点が特徴です。
この税負担を軽減するため、基礎控除や特例が用意されています。
相続税の基礎控除額とは?
相続税には基礎控除額が設けられており、この額以内の遺産には課税されません。
基礎控除額は次の計算式で求めることができます。
たとえば、相続人が配偶者と子2人の計3人の場合、以下の計算で基礎控除額を算出できます。
また、法定相続人の人数によって控除額が増えるため、人数を適切に把握しておくことが大切です。
相続税の基本的な計算方法
相続税の計算は、法定相続人の人数や相続財産の内容などに応じて異なります。
まず被相続人のすべての財産を合計し、そこから債務や葬式費用を差し引いて正味の遺産額を算出します。
次に、正味遺産額から基礎控除額を引いて課税遺産総額を求め、それを法定相続分に従って各相続人に仮分割します。
仮分割した額ごとに定められた税率を適用して仮の相続税額を計算し、それを合計して全体の税額を求めます。
続いて、各相続人の遺産相続の配分に従って、全体の相続税を分配します。
最後に、配偶者控除や未成年者控除など、適用できる各種控除を利用し、各相続人が実際に納める相続税額を決定します。
まとめ
相続税は、遺産を引き継ぐ際に発生する重要な税金であり、基礎控除額を超える財産に対して課税されます。
課税対象額の計算や控除の適用には細かなルールがあるため、正確な計算が必要です。
税理士に相談することで、円滑な相続手続きを進める上でさまざまなサポートを受けることができます。
相続に関してお困りの際は、お気軽に税理士にご相談ください。
文責:
-

- 税理士 天池 健治
- 天池 健治 税理士のプロフィール
- 税理士 / 証券アナリスト / 宅建士 / 公認コンサルタント