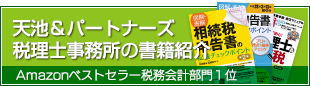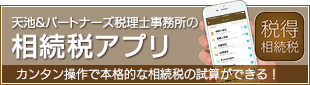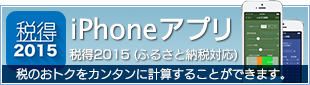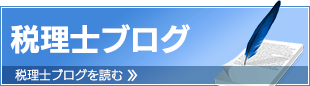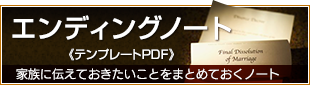税金お役立ち情報
財産および債務の五十音索引
- 第1キーワード:
- 絞り込み(AND検索)
- 第2キーワード :
検索結果
| 項目 | 評価方法等 |
|---|---|
| IPO株式 |
IPO(Intial Public Offering)株式とは、証券市場に新規公開する株式で、①公募等が行われる場合は公開価格、②公募等が行われない場合は課税時期以前の取引価格等を勘案して評価します(評基通174⑵)。 |
| 青空駐車場の敷地 |
土地の所有者が、自らその土地を貸駐車場として利用している場合には、その土地の自用地としての価額により評価します。ただし、車庫などの施設を駐車場の利用者の費用で造ることを認めるような契約の場合には、賃借権の価額を控除した金額によって評価します。 |
| 青地(青道)のある土地 |
青地(旧水路)のある土地の価額は、青地を含む土地を一画地として評価し、青地部分については、国市町村からの払下費用相当額を控除して評価します。 平成30年11月30日付東京地裁判決、平成28年12月7日裁決 青地のある土地 = 青地を含む土地の評価額 - 払下費用相当額 |
| 赤道のある土地 |
赤道は国(道路としての機能がある場合は市区町村)が所有するものであり、赤道がある土地を評価する場合は、原則として赤道を除いてその両側の所有地を別々に評価することになります。ただし、敷地として占有しているなど一定の場合は、赤道を含む土地を一画地として評価し、赤道部分については、国市町村からの払下費用相当額を控除して評価します。 赤道のある土地 = 赤道を含む土地の評価額 - 払下費用相当額 |
| 空き家となっている貸家の敷地 |
その家屋がもっぱら賃貸用として新築されたものであっても、課税時期において現実に貸し付けられていない貸家の敷地については、自用地価額で評価します(評基通26)。 なお、課税時期において一時的に空き家であった場合であっても、空き家となっている家屋は自用家屋として評価します(評基通89)。 |
| 空室のあるアパートの敷地 |
課税時期において現実に貸し付けられていないアパート等の敷地は、原則として自用地価額で評価しますが、継続的に賃貸されていたアパートに一時的に空室であったと認められる部分がある場合には、その部分を含めて全体を課税時期において賃貸されていたものとして差し支えありません。なお、家屋の評価についても同様に取り扱われます。 |
| アジア開発銀行債 |
アジア開発銀行債(主に外貨建てで発行される外国債券)の価額は、①金融商品取引所等に上場している場合、②上場していない場合に区分し、次の算式により評価します(評基通197~197-5)。なお、邦貨換算は、対顧客直物電信買相場(TTB)により計算します(評基通4-3)。
|
| 預け金 |
預け金の価額は、元本の価額(その返済されるべき金額)と利息の価額(課税時期現在の既経過利息として支払を受けるべき金)との合計額によって評価します(評基通204)。 |
| アスベスト使用建物 |
アスベスト使用建物の価額はアスベストの除去が必要である事情について、具体的に建物の価額に影響することを立証することができない限り減額評価はできません。 |
| あずまや |
あずまや(庭園などに眺望、休憩などの目的で設置される簡素な建屋)の価額は、その庭園設備の調達価額(課税時期においてその財産をその財産の現況により取得する場合の価額)の70%に相当する価額によって評価します(評基通92)。 |
| アパート |
その家屋(アパート)の固定資産税評価額に借家権割合(30%)と賃貸割合を乗じた価額を、その家屋の固定資産税評価額から控除して評価します(評基通89、93、94)。 固定資産税評価額 - 固定資産税評価額 × 30% × 賃貸割合 |
| アフリカ開発銀行債 |
アフリカ開発銀行債(主に外貨建てで発行される外国債券)の価額は、①金融商品取引所等に上場している場合、②上場していない場合に区分し、次の算式により評価します(評基通197~197-5)。なお、邦貨換算は、対顧客直物電信買相場(TTB)により計算します(評基通4-3)。
|
| 暗号資産 |
暗号資産の価額は、原則として、納税義務者が取引を行っている暗号資産交換業者が公表する課税時期における取引価格によって評価します。なお、活発な市場が存在しない暗号資産の場合には、その暗号資産の内容や性質、取引実態等を勘案し、個別に評価します(評基通4-3、5)。 |
| アンティーク品 |
アンティーク品の評価は、①書画骨とう品の販売業者が有するものの価額は、たな卸商品等の評価、②上記以外の書画骨とう品の価額は、売買実例価額(ネットなどの相続開始日の取引価格等)、精通者意見価格等を参酌してします(評基通133、135)。 |
| ETN |
ETN(上場投資証券や指標連動証券とも呼ばれ、特定の指標価格に連動する金融商品)の価額は、「上場株式の評価」(評基通169)に準じて評価します。また受益証券発行信託証券に係る権利の価額は、「配当期待権の評価」に準じて評価します(評基通193、213-2)。 |
| ETF |
ETF(株価指数などに連動する上場投資信託)の価額は、「上場株式の評価」(評基通169)に準じて評価します。また証券投資信託証券又は受益証券発行信託証券に係る権利の価額は、「配当期待権の評価」に準じて評価します(評基通193、199⑵注)。 |
| EB債 |
他社株転換可能債(EB債)とは、デリバティブにより株価や為替などの変動リスクを背負うことにより、大きな利回りのリターンを得られるもので、その仕組み債の内容(ノックイン又はノックアウト価格やその時の償還資産、残存期間など)により評価方法は異なります。 |
| 育英年金 |
会社から支給される育英年金は、「契約に基づくもの以外の定期金」(相法3①六)として相続又は遺贈により取得したものとみなされますから、相続税が課税されます。また、この場合の年金は、「有期定期金」(相法24①一)により評価します。 |
| 遺骨運搬費用 |
相続人(無制限納税義務者)又は包括受遺者が支出した被相続人が遭難した場合などに支出される死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用は、葬式費用として債務控除できます(相基通13-4)。 |
| 遺言執行費用 |
遺言執行費用は、民法第1021条で「遺言の執行に関する費用は相続財産の負担とする」旨規定していますが、相続開始後に発生する費用であり、被相続人に係る費用ではなく相続人が負担すべき費用ですので債務控除の対象とはなりません。 |
| 意匠権 |
意匠権は、特許権の評価(評基通140~145)の定めを準用して、その権利に基づき将来受ける補償金の額の基準年利率による複利現価の額の合計額によって評価します。なお、権利者が自ら実用新案を実施している場合は、その者の営業権の価額に含めて評価します(評基通146)。 |
| 遺族一時金 |
国民年金等の公的年金の加入者に支給される遺族一時金は非課税ですが、公的年金以外から支給される遺族一時金(確定給付企業年金等の年金加入中に相続が発生し、遺族一時金として支給を受けた場合など)については、相続税の課税対象となります。 |
| 遺族共済年金(経過的職域加算額) |
「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」施行(平成27年10月1日)以後、経過措置として平成27年9月30日以前の加入期間に応じて、公務員及び教職員の組合員の遺族に支給され続ける「遺族共済年金(経過的職域加算額)」は、相続税法3条1項2号(退職手当金)に該当します。 |
| 遺族国庫債券 |
遺族国庫債券(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金及び特別給付金等に代えて交付される国庫債券)は、戦没者遺族の配偶者に対する特別遺族弔慰金として国債で支給されるもので、支給原因が弔慰金となるので、相続税は課税されません(戦没者の遺族に対する特別弔慰金支給法12)。 |
| 遺族に対する一時金(公務員及び教職員) |
平成27年10月1日以後、公務員及び教職員の共済組合から組合員の遺族に支給される「遺族に対する一時金」は、相続税法3条1項2号(退職手当金)に該当します。 |
| 遺族年金 |
厚生年金や国民年金などの受給者が死亡したときに遺族に支給される遺族年金は、契約に基づかない定期金に関する権利(相基通3-46)ですが、各法令に非課税規定が設けられているため、非課税となります。なお、死亡したときに支給されていなかった年金を遺族が支給を受けた場合(未支給年金)は、その遺族の一時所得となります。 |
| 遺体解剖費用 |
遺体解剖費用は、相続税法基本通達13-5(葬式費用でないもの)に列挙されている「医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用」に該当するので、葬式費用として債務控除できません(相基通13-5)。⇔死体若しくは遺骨の運搬に要した費用(相基通13-4) |
| 一時使用に係る借地権 |
建設現場、博覧会場、一時的興行場等の一時使用のための借地権については、借地借家法の手厚い保護規定の適用がなく、期間の満了とともに消滅することとされており、借地権として評価することは適当でないので、雑種地の賃借権の評価方法に準じて評価します(評基通87)。 |
| 位置指定道路に面している宅地 |
路線価の設定されていない道路(位置指定道路)のみに接している宅地は、税務署長に対して特定路線価の設定の申出をすることができます。この設定の申出により、税務署長が特定路線価を設定した場合には、この特定路線価を路線価とみなして評価します(評基通14-3)。 |
| 一団の工場用地 |
土地の価額は、原則として地目の別に評価し、2以上の地目からなる一団の土地が一体として利用されている場合には、その一団の土地はそのうちの主たる地目からなるものとして、その一団の土地ごとに評価します(評基通7)(大規模工場用地の評価については、「大規模工場用地の評価」(評基通22)から「大規模工場用地の路線価及び倍率」(評基通22-3)を参照)。 |
| 一般家庭の庭園設備 |
庭園設備(庭木、庭石、あずまや、庭池等)の価額は、原則としてその庭園設備の調達価額(課税時期においてその財産をその財産の現況により取得する場合の価額)の70%に相当する価額によって評価しますが(評基通92)、一般家庭の庭園設備は特に評価しなくて構わないものと考えられます。 |
| 一般定期借地権 |
一般定期借地権の価額は、原則として、課税時期において借地人に帰属する経済的利益及びその存続期間を基として評定した価額によって評価しますが、課税上弊害がない限り、財産評価基本通達の定めにかかわらず、次の算式によって評価することができます(評基通27-2)。
自用地価額 × |
| 一般定期借地権の目的となっている宅地 |
一般定期借地権の目的となっている宅地は、原則として、その宅地の自用地としての価額から、定期借地権等の価額を控除した金額により評価しますが、課税上弊害がない限り、財産評価基本通達の定めにかかわらず、次の算式によって評価することができます。
自用地価額 - 自用地価額 × ( 1 - 底地割合 ) × |
| 一般動産 |
一般動産(棚卸資産を除きます。)の評価は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。ただし、売買実例価額等が明らかでない場合は、同種及び同規格の新品の小売価額から、取得時期から課税時期までの償却費の額を控除した金額によって評価します。なお、家屋と構造上一体となっている設備については、その家屋の価額に含めて評価します(評基通92、128~130)。 |
| 犬 |
犬の価額は、①販売業者が販売の目的をもって有するものは、「たな卸商品等の評価」(評基通133)によって評価し、②それ以外のものは、売買実例価額(ネットなどの取引情報など)、精通者意見価格等を参酌して評価します(評基通134)。 |
| 位牌 |
位牌は、相続税法第12条(相続税の非課税財産)第2号の「祭具並びにこれらに準ずるもの」に該当し、相続税の課税価格には算入しません(相法12、相基通12-2)。ただし、金の位牌など、日常崇拝の目的に供されず趣味、観賞用又は投資のために保有されるものについては、非課税財産とはなりませんので(相基通12-2)、貴金属や骨とう品として評価します。 |
| 位牌の購入費用 |
相続人(無制限納税義務者)又は包括受遺者が支出した葬式若しくは葬送の際に使用される白木位牌の購入費用は葬式費用として債務控除できますが、仏壇にお祀りする本位牌の購入費用は葬式費用として債務控除できません(相基通13-4)。 |
| 忌み地 |
忌み地(事件・事故などで呪いや祟りがあるとされる場所)の価額は、同一路線価の土地に比べ利用価値が低下していると認められる部分の面積に対応する部分の価額に10%を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価することができます。 宅地の価額 - 利用価値が低下している部分の面積に対応する宅地の価額 × 10% |
| 入会地 |
入会地とは、村や部落などの村落共同体で総有した土地で、各構成員はその団体財産について持分(持分分割請求権)を持たないため、構成員は入会地を相続財産に含める必要がありません。 |
| 医療法人への出資 |
出資持分は、その医療法人の規模に応じて、類似業種比準価額方式か純資産価額方式、又は両方式を併用した方法で評価します。なお、剰余金の配当が禁止されており配当還元方式は適用できません(評基通194-2)。 |
| 引湯権 |
引湯権の価額は、鉱泉地の価額又は温泉権の価額に、その引湯権に係る分湯量の割合を乗じて求めた価額から、引湯の条件に応じ、その価額の30%の範囲内において相当と認める金額を控除した価額によって評価します。ただし、別荘、リゾートマンション等に係る引湯権で取引価額が明らかなものについては、その金額によって評価することができます(評基通80)。 |
| 引湯権の設定されている温泉権 |
引湯権(鉱泉地又は温泉権を有する者から分湯をうける者のその引湯する権利)の設定されている温泉権の価額は、温泉権の価額から引湯権の価額を控除した価額によって評価します(評基通79)。 引湯権の設定されている温泉権 = 温泉権の価額 - 引湯権の価額 |
| 引湯権の設定されている鉱泉地 |
引湯権(鉱泉地又は温泉権を有する者から分湯をうける者のその引湯する権利)の設定されている鉱泉地の価額は、鉱泉地の価額から引湯権の価額を控除した価額によって評価します(評基通79)。 引湯権の設定されている鉱泉地 = 鉱泉地の価額 - 引湯権の価額 |
| ウィークリーマンションの敷地 |
ウィークリーマンション(一般的には、賃貸の住居を1週間単位で借りるサービスで、借地借家法の定期建物賃貸借契約に基づいて運営されています。)は、居室の賃貸借ですが借家権がないことから、その敷地はホテルや宿屋の敷地と同様に、自用地価額で評価します。なお、その建物についても自用家屋として評価します。 |
| 受取手形 |
受取手形の価額は、①支払期限の到来している受取手形又は課税時期から6か月を経過する日までの間に支払期限の到来するものは、その券面額によって評価し、②それ以外の受取手形については、金融機関において割引を行った場合の金額によって評価します(評基通206)。 |
| 受取日歩 |
被相続人が株式の信用取引(売建て)をしていた場合に発生する日歩の受取(日歩)は、融資を受けた買い方が払う金利のことで、被相続人の財産(未収金)となり、支払日歩(逆日歩)は債務となります。 |
| 牛 |
牛の価額は、①販売業者が販売の目的をもって有するものは、「たな卸商品等の評価」(評基通133)によって評価し、②それ以外のものは、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します(評基通134)。 |
| 馬 |
馬の価額は、①販売業者が販売の目的をもって有するものは、「たな卸商品等の評価」(評基通133)によって評価し、②それ以外のものは、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します(評基通134)。 |
| 売掛金 |
売掛金の価額は、元本の価額(その返済されるべき金額)と利息の価額(課税時期現在の既経過利息として支払を受けるべき金額)との合計額によって評価します(評基通204)。 |
| 営業権 |
営業権の価額は、次の算式によって計算した金額によって評価します(評基通165)。なお、医師、弁護士等のようにその者の技術、手腕又は才能等を主とする事業に係る営業権で、その事業者の死亡と共に消滅するものは、評価しません。 超過利益金額※1 × 営業権の持続年数※2に応ずる基準年利率による複利年金現価率
|
| 永小作権 |
永小作権の価額は、その残存期間に応じ、その目的となっている土地のこれらの権利を取得した時におけるこれらの権利が設定されていない場合の価額に、一定の割合を乗じて算出した金額によって評価します(相法23)。 |
| 衛生設備 |
衛生設備(棚卸資産を除きます。)は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。ただし、売買実例価額等が明らかでない場合は、同種及び同規格の新品の小売価額から、取得時期から課税時期までの償却費の額を控除した金額によって評価します(評基通129)。なお、家屋と構造上一体となっている設備については、その家屋の価額に含めて評価します(評基通92)。 |
| 永代供養料 |
永代供養料は、寺院・霊園が永代にわたって管理又は供養するための支払いであり、葬式の前後に生じる出費で通常葬式に伴うものとは認められないため、葬式費用として債務控除できません(東京地裁 平成30年11月30日)。 |
| ABS |
ABS(資産担保証券)とは、商業用不動産担保ローンや住宅ローン、自動車ローン、クレジットカードなどに関する貸付金銭債権などの資産を裏付けとして発行される証券の総称で、「利付公社債の評価」(評基通197-2)に準じて評価します。 |
| 液状化現象により被害を受けた土地等 |
災害等に伴う液状化現象により被害を受けた土地等の価額は、被害がないものとした場合の土地等の価額から原状回復費用相当額を控除して評価することができます。なお、この場合の原状回復費用相当額については、①原状回復費用の見積額の80%に相当する金額、又は②市街地農地等を宅地に転用する場合において通常必要とされる宅地造成費相当額から算定した金額として差し支えありません(平成30年1月15日「特定非常災害発生日以後に相続等により取得した財産の評価に関する質疑応答事例集」Q5)。 |
| NFT(非代替トークン) |
NFT(Non-Fungible Token)とは、ブロックチェーン上で、デジタルデータに唯一の性質を付与して真贋性を担保する機能や、取引履歴を追跡できる機能をもつトークンをいいます。NFTの評価方法については、評価通達に定めがないことから、評価通達5(評価方法の定めのない財産の評価)の定めに基づき、その内容や性質、取引実態等を勘案し、その価額を個別に評価します。例えば、評価通達135(書画骨とう品の評価)に準じ、その内容や性質、取引実態等を勘案し、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。 また、課税時期における市場取引価格が存在するNFTについては、当該市場取引価格により評価して差し支えありません。 |
| FX取引 |
相続開始日でFX取引の未決済の取引がある場合は、その日の最終価格で決済した場合の差損益額が相続財産債務となります。つまり、課税時期において未決済差損益額がプラス(利益)である場合は相続財産となり、マイナス(損失)である場合は債務控除することができます。なお、差し入れてある証拠金は相続財産(預け金)となります。 |
| MRF |
MRF(マネー・リザーブ・ファンド)とは、オープン型の公社債投資信託であることから、課税時期において解約請求又は買取請求により、証券会社等から支払いを受けることができる価額で評価します(評基通199)。 |
| MMF |
MMF(マネー・マネージメント・ファンド)とは、オープン型の公社債投資信託であることから、課税時期において解約請求又は買取請求により、証券会社等から支払いを受けることができる価額で評価します(評基通199) |
| 延滞税・延滞金 |
被相続人に係る延滞税や延滞金を負担した相続人(制限納税義務者は、相続により取得した財産でこの法律の施行地にあるものについて負担した公租公課に限ります。)は、債務控除することができます(相法13、14)。ただし、相続人などの責任に基づいて納付されることになった附帯税(延滞税、利子税及び加算税)は、債務控除することができません。 |
| 黄金株 |
黄金株(拒否権付き株式)とは、株主総会や取締役会などの決議に対して、強力な拒否権を有している種類株式のことですが、拒否権を考慮せずに評価することとされており、普通株式と同様に評価します。 |
| 欧州復興開発銀行債 |
欧州復興開発銀行債(主に外貨建てで発行される外国債券)の価額は、①金融商品取引所等に上場している場合、② 上場していない場合に区分し、次の算式により評価します(評基通197~197-5)。なお、邦貨換算は、対顧客直物電信買相場(TTB)により計算します(評基通4-3)。
|
| お供物 |
相続人(無制限納税義務者)又は包括受遺者が支出した通夜、告別式の際の供花、供物は、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるものであり、葬式費用として債務控除できます(相基通13-4)。 |
| おたまや |
おたまや(先祖の霊や貴人の霊を祭っておく建物)は、相続税法第12条(相続税の非課税財産)第2号の「墓所、霊びょう、及び祭具並びにこれらに準ずるもの」に該当し、相続税の課税価格には算入しません(相法12、相基通12-2)。 |
| お通夜の費用 |
相続人(無制限納税義務者)又は包括受遺者が支出したお通夜の費用は、通常葬式に伴うものと認められる範囲内のものは、葬式費用として債務控除できます(相基通13-4)。 |
| お墓 |
墓地や墓石などは、相続税の非課税財産となります(相法12①二、相基通12-1)。 なお、被相続人の生存中に墓碑などを買い入れ、その代金が相続開始時点で未払であるような場合には、当該未払代金は債務控除できません(相法13③、相基通13-6)。 |
| オプション付き定期預金 |
オプション付き定期預金(円定期預金に条件付為替予約が付加された仕組預金)の価額は、「預貯金の評価」(評基通203)により評価します。 課税時期における預入高 + 解約利子の額(源泉徴収後の金額) |
| オプション料 |
オプション料(オプション取引の際に、買い手が売り手に対して支払う金額)の価額は、被相続人が①オプションの買い手の場合は、課税時期のオプション価格が相続財産となり、②オプションの売り手の場合は、課税時期のオプション価格が相続債務となります。 |
| お布施 |
相続人(無制限納税義務者)又は包括受遺者が支出した葬式に際し、僧侶等に謝礼として渡す金銭で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるお布施は、葬式費用として債務控除できます(相基通13-4)。 |
| 温湿度調整設備 |
温湿度調整設備(棚卸資産を除きます。)は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。ただし、売買実例価額等が明らかでない場合は、同種及び同規格の新品の小売価額から、償却費の額を控除した金額によって評価します。なお、家屋と構造上一体となっている設備については、その家屋の価額に含めて評価します(評基通92、128~130)。 |
| 温泉権 |
温泉権の価額は、その温泉権の設定の条件に応じ、温泉権の売買実例価額(ネットなどのその温泉権の取引情報など)、精通者意見価格等を参酌して評価します(評基通78)。 |
| 温泉権が設定されている鉱泉地 |
温泉権が設定されている鉱泉地の価額は、その鉱泉地の価額から温泉権の価額を控除した価額によって評価します(評基通77)。 温泉権が設定されている鉱泉地 = 鉱泉地の価額 - 温泉権の価額 |
| 外貨(通貨) |
金融機関が外貨を円に交換する場合には、対顧客直物電信買相場から金融機関が現金を保有するコスト等を差し引いたところの外国通貨買相場が適用されることになりますが、財産評価に当たっては、納税義務者の取引金融機関が公表する課税時期における最終の対顧客直物電信買相場(TTB)により換算することになります(評基通4-3)。 |
| 海外ETF |
海外ETF(海外の株価指数などに連動する外国上場投資信託)の価額は、外国上場株式の評価に準じて評価します。また、金銭分配期待権の価額は、配当期待権の評価に準じて評価します。なお、邦貨換算は、納税義務者の取引金融機関が公表する課税時期における最終の対顧客直物電信買相場(TTB)によります(評基通199、4-3)。 |
| 海外の生命保険 |
海外の保険業者と締結する生命保険契約又は損害保険契約に基づく保険金等については、これまで相続税の課税対象とはされず、保険金等を受け取った者の一時所得とされていましたが、平成19年4月からは相続税の課税対象とされ、国内の生命保険等と同様に扱われます(相令1の2②)。なお、邦貨換算は、納税義務者の取引金融機関が公表する課税時期における最終の対顧客直物電信買相場(TTB)によります(評基通199、4-3)。 |
| 外貨建てMRF |
外貨MRF(換金性・流動性の高い公共債型投資信託の一種)の価額は、解約請求等により証券会社などから支払いを受けることができる価額で評価します。なお、邦貨換算は、納税義務者の取引金融機関が公表する課税時期における最終の対顧客直物電信買相場(TTB)によります(評基通199、4-3)。 |
| 外貨建てMMF |
外貨MMF(換金性・流動性の高い公共債型投資信託の一種)の価額は、解約請求等により証券会社などから支払いを受けることができる価額で評価します。なお、邦貨換算は、納税義務者の取引金融機関が公表する課税時期における最終の対顧客直物電信買相場(TTB)によります(評基通199⑴、4-3)。 |
| 外貨建て保険 |
外貨建て保険(保険料を外貨で払い込み、保険金や解約返戻金を外貨で受け取る保険)の価額は、生命保険金の金額又は解約返戻金の金額で評価します。なお、邦貨換算は、納税義務者の取引金融機関が公表する課税時期における最終の対顧客直物電信買相場(TTB)によります(評基通214、4-3)。 |
| 外貨預金 |
外貨預金の価額は、預入残高と解約するとした場合に既経過利子の額として支払を受けることができる金額から当該金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額との合計額によって評価します。なお、邦貨換算は、納税義務者の取引金融機関が公表する課税時期における最終の対顧客時直物電信買相場(TTB)によります(評基通214、4-3)。 外貨預金 = ( 預入残高 + 解約利息の額(源泉税控除後)) × TTB |
| 開業後3年未満の会社の株式 |
課税時期において、開業後3年未満の会社の株式の価額は、会社規模にかかわらず、純資産価額方式で評価します。なお、同族株主以外の株主等については、配当還元方式により評価することもできます(評基通189-4)。 |
| 開業前の会社の株式 |
課税時期において、開業していない会社の株式の価額は、純資産価額方式により評価します(評基通189-5)。なお、同族株主以外の株主等が取得した株式に該当する場合や議決権の合計数が評価会社の議決権総数の50%以下である場合であっても特別な扱いはありません。 |
| 外国株 |
外国株の価額は、①取引相場がない株式は、純資産価額方式に準じて評価し(評基通185)、②外国の証券取引所に上場されている株式は「上場株式の評価」(評基通185)に準じて評価します。(評基通169)に準じて評価します(評基通4-3、5-2)。なお、邦貨換算は、納税義務者の取引金融機関が公表する課税時期における最終の対顧客時直物電信買相場(TTB)によります(評基通4-3、203) |
| 外国為替証拠金取引 |
相続開始日に外国為替証拠金取引の未決済額がある場合は、相続開始日の差益金額が相続財産となり、差損金額が相続債務となります。なお、差し入れてある証拠金は相続財産(預け金)となります。 |
| 外国債券 |
外国債券の価額は、①金融商品取引所等に上場している場合は、課税時期の最終価格と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価し、②上場していない場合は、公社債の発行価額と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価します(評基通197)。なお、邦貨換算は、納税義務者の取引金融機関が公表する課税時期における最終の対顧客直物電信買相場(TTB)によります(評基通4-3)。 |
| 外国市場に上場している株式 |
外国の証券取引所に上場されている株式の価額は、「上場株式の評価」(評基通169)に準じて評価します(評基通4-3、5-2)。なお、邦貨換算は、納税義務者の取引金融機関が公表する課税時期における最終の対顧客直物電信買相場(TTB)によります(評基通4-3、203)。 |
| 介護施設未精算金 |
相続人(無制限納税義務者)が相続開始後に支払った介護施設の未精算金は、未払費用として債務控除の対象となります。なお、入居時に一時金を支払っている場合はその全部又は一部が返還される場合には、その返還金が相続財産となります。 |
| 介護保険料 |
相続人(無制限納税義務者)が相続開始後に納付した介護保険料は、未払費用として債務控除の対象となります。また、介護保険料が納め過ぎとなった場合に還付される金額(過誤納金)はその他財産として相続財産に計上します。 |
| 介在山林 |
介在山林(固定資産税の課税区分)とは、市街化区域にある山林のことで、「市街地山林の評価」(評基通49)により、①比準方式、②倍率方式(評基通21)で評価します。
|
| 回収不能な貸付金などの債権 |
回収不能な貸付金などの債権の価額は、課税時期に破産や倒産などにより、債権回収の見込みがないか又は著しく困難と客観的に認められるときは、元本の価額に算入しないことができます(評基通204、205)。 |
| 買取価格が定められている株式 |
買取価格(退職時には、額面価額をもって所有株式を譲渡するという誓約書があるもの)が定められている取引相場のない株式の価額は、その買取価格が時価を表しているものと認められない限り、財産評価基本通達に従って評価します(評基通1)。 平成2年6月18日裁決 |
| 戒名料 |
相続人(無制限納税義務者)又は包括受遺者がお寺に支払った戒名料は、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められる範囲内のものは、葬式費用として債務控除できます(相基通13-4)。 |
| 家屋 |
家屋の価額は、その家屋の固定資産税評価額(地方税法第381条の規定により家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登録された基準年度の価格又は比準価格)に財産評価基本通達「別表1」に定める倍率1.0を乗じて計算した金額によって評価します(評基通89)。 家屋 = 固定資産税評価額 × 財産評価基本通達の倍率(1.0) |
| 確定給付年金の遺族が受領する年金又は一時金 |
加入者が死亡した場合は、相続税法3条1項2号(退職手当金)に該当し、(相令1の3四)確定給付企業年金の老齢給付金の支給を受けている者が死亡した場合は、相続税法3条1項6号(契約に基づかない定期金に関する権利)に該当します(評基通3-29)。 |
| 確定拠出年金の遺族が受領する死亡一時金 |
死亡一時金は、企業型年金又は個人型年金の加入者又は加入者であった者が死亡した場合にその遺族に支給され、相続税法3条1項2号(退職手当金)に該当します(相令1の3七)。 |
| がけ地等を有する宅地 |
がけ地等で通常の用途に供することができないと認められる部分を有する宅地(「土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価」(評基通20-6)に該当するものを除きます。)の価額は、その宅地の総地積に対するがけ地部分等の地積の割合に応じる「がけ地補正率表」を乗じて評価します(評基通20-5)。 がけ地等を有する宅地 = 宅地価額 × がけ地補正率表 |
| 加算税 |
被相続人の申告に係る加算税を負担した相続人又は包括受遺者(制限納税義務者は、取得した財産でこの法律の施行地にあるものについて負担した公租公課に限ります。)は、債務控除することができます(相法13)。ただし、相続人などの責任に基づいて納付することになった被相続人の附帯税(延滞税、利子税及び加算税)は差し引くことはできません(相法14)。 |
| 貸宅地(貸地) |
貸宅地(借地権など宅地の上に存する権利の目的となっている宅地)の価額は、その宅地の上に存する権利の区分(①借地権、②定期借地権、③地上権、④区分地上権、⑤区分地上権に準ずる地役権)に応じて評価します(評基通25)。 |
| 果実 |
天然果実の価額は、元物の価額に含めて評価します。ただし、これと異なる取引の慣行がある場合又は財産評価基本通達通第2章以下に特別の定めのある場合においては、その慣行又はその定めによって評価します(評基通4)。 |
| 貸付金 |
貸付金の価額は、元本の価額(その返済されるべき金額)と利息の価額(課税時期現在の既経過利息として支払を受けるべき金額)との合計額によって評価します(評基通204)。 貸付金 = 元本の価額 + 既経過利息 |
| 貸付信託受益証券 |
貸付信託の受益証券の価額は、その証券の受託者が課税時期においてその証券を買い取るとした場合における次の算式により計算した金額で評価します(評基通198)。 元本の額 + 既経過収益の額 -源泉徴収税額 - 買取割引料 |
| 貸家 |
課税時期において貸家の用に供されている家屋の価額は、その家屋の固定資産税評価額に借家権割合と賃貸割合を乗じた価額を、その家屋の評価額から控除して評価します(評基通93)。 固定資産税評価額 - 固定資産税評価額 × 借家権割合(0.3) × 賃貸割合 |
| 貸家建築中の宅地 |
敷地に貸家用の家屋を建築中である場合において相続が開始したときのその敷地の価額は、貸家建付地として考慮すべき借家人の事実上の支配権は存在しないので、原則として自用地価額で評価します。 |
| 貸家建付借地権 |
貸家建付借地権の価額は、その借地権の価額にその貸家に係る借家権割合と賃貸割合を乗じて計算した価額をその借地権の価額から控除した金額によって評価します(評基通28)。 借地権の価額 - 借地権の価額 × 借家権割合0.3 × 賃貸割合 |
| 貸家建付地 |
貸家建付地の価額は、その自用地の価額に借地権割合とその貸家に係る借家権割合と賃貸割合を乗じて計算した価額をその自用地の価額から控除した金額によって評価します(評基通26)。 自用地価額 - 自用地価額 × 借地権割合 × 借家権割合0.3 × 賃貸割合 |
| 果樹 |
果樹の価額は、樹種ごとに、①幼齢樹(成熟樹に達しない樹齢のもの)又は②成熟樹の区分ごとに次の算式により評価します(評基通99)。なお、屋敷内にある果樹等でその数量が少なく、かつ、収益を目的として所有するものでないものについては、評価しません(評基通110)。
|
| 過少申告加算税 |
被相続人の申告に係る過少申告加算税を負担した相続人(制限納税義務者は、取得した財産でこの法律の施行地にあるものについて負担した公租公課に限ります。)又は包括受遺者は、債務控除することができます(相法13)。ただし、相続人などの責任に基づいて納付されることになった附帯税(延滞税、利子税及び加算税)は差し引くことはできません(相法14)。 |
| ガス設備 |
ガス設備(棚卸資産を除きます。)は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。ただし、売買実例価額等が明らかでない場合は、同種及び同規格の新品の小売価額から、償却費の額を控除した金額によって評価します。なお、家屋と構造上一体となっている設備については、その家屋の価額に含めて評価します(評基通92、128~130)。 |
| 河川を隔てて路線に接している土地 |
土地、川及び橋を一体として評価した価額から川及び橋部分の価額を差し引き、その後川及び橋をかげ地として不整形地補正等により評価します。なお、橋が架設されていない場合には、上記の評価を行った後に通路に相当する部分の価額を控除しますが、その価額は接道義務を満たす最低限の幅の橋の架設費用相当額(不整形地補正した後の価額の40%相当額を限度)とします。 |
| 仮想通貨 |
仮想通貨の価額は、原則として、納税義務者が取引を行っている仮想通貨交換業者が公表する課税時期における取引価格によって評価します。なお、活発な市場が存在しない仮想通貨の場合には、その仮想通貨の内容や性質、取引実態等を勘案し、個別に評価します(評基通4-3、5)。 |
| 火葬場使用料 |
相続人(無制限納税義務者)又は包括受遺者が支出した火葬場使用料は、葬式若しくは葬送に際し要した費用と認められることから、葬式費用として債務控除できます(相基通13-4)。 |
| 火葬費用 |
相続人(無制限納税義務者)又は包括受遺者が支出した火葬費用は、葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において要した費用と認められるので、葬式費用として債務控除できます(相基通13-4)。 |
| 家庭菜園 |
家庭菜園は、一般的に耕作面積が広くなく、それだけでは農地としての存在価値が見いだせないため、宅地と一体としてみなされます。そのため、住宅の敷地全部分を宅地として評価住宅の敷地全体に含め宅地として評価します。 |
| 家庭用動産 |
家庭用動産の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない動産については、その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、課税時期までの期間の償却費の額の合計額又は減価の額(定率法)を控除した金額によって評価します(評基通128、130)。 |
| 過納金 |
過納金とは、いったん有効な納税申告・更正処分・賦課決定等によって確定された税額が納付又は徴収された後、減額更正処分・取消判決等がなされることによって減少した税額に相当する金額で、被相続人の過誤納金は相続財産となります。 |
| 株価指数連動債 |
株価指数連動債(日経平均株価やS&P500種指数等の指数の変動によって、償還額や利率が変動する仕組債)の価額は、課税時期において、①償還が確定している場合には、償還される金額で評価し、②確定していない場合は、利付公社債として評価しますが、課税時期において元本割れが生じている場合は、その損失を見込んで評価しても差し支えありません。 |
| 株式 |
株式の価額は、①上場株式、②気配相場等のある株式、③取引相場のない株式、④株式の割当てを受ける権利、⑤株主となる権利、⑥株式無償交付期待権、⑦配当期待権、⑧ストックオプション、⑨上場新株予約権の区分に従い、その1株又は1個ごとに評価します。 |
| 株式制のゴルフ会員権 |
株式制のゴルフ会員権の価額は、①取引相場のあるものは、通常の取引価格の70%相当額で評価し、②取引相場のないものは、「取引相場のない株式の評価」(評基通179)により評価します(評基通211)。 |
| 株式等保有特定会社 |
株式等保有特定会社(会社の総資産価額のうちに占める株式等の価額の割合(相続税評価額ベース)が50%以上である会社の株式)の価額は、原則として、純資産価額方式に準じた方法により評価します(評基通189-3)。 |
| 株式無償交付期待権の発生している株式 |
株式無償交付期待権(株式の無償交付の基準日の翌日から株式の無償交付の効力が発生する日までの間における株式の無償交付を受けることができる権利)の発生している株式の価額は、①取引相場のない株式である場合は、「取引相場のない株式の評価」(評基通179)、②上場株式の場合は「上場株式の評価」(評基通169)の定めにより評価した金額に「株式の割当てを受ける権利等の発生している株式の価額の修正」(評基通187)をして評価します(評基通192)。 株式の価額 + 割当てを受けた株式1株につき払い込むべき金額 × 株式1株に対する割当株式数1 + 株式1株に対する割当株式数又は交付株式数 |
| 株式の割当てを受ける権利 |
株式の割当てを受ける権利(株式の割当基準日の翌日から株式の割当ての日までの間における株式の割当てを受ける権利)の価額は、財産評価基本通達の定めにより評価した価額に相当する金額(権利落等後の株式の評価額)から割当てを受けた株式1株について払い込むべき金額を控除した価額によって評価します(評基通168⑷、190)。 株式の価額(権利落等後の株式の評価額)- 株式1株について払い込むべき金額 |
| 株主となる権利 |
株主となる権利の価額は、①会社設立の場合は、課税時期以前にその株式1株につき払い込んだ金額によって評価し、②それ以外の場合は、各種株式の評価方法の定めにより評価した価額に相当する金額によって評価します(評基通191)。 |
| 株主優待券 |
商品券や旅行券、ギフト券、クオカード、株主優待券などの金券は、相続財産となり、その価額は額面金額又は売買実例価額(ネットなどの相続開始日の買取価格)で評価します(相法22)。 |
| 寡婦年金 |
寡婦年金(国民年金の1号被保険者(自営業者)として10年以上保険料を納めた夫が10年以上連れ添った妻に対して支払われる年金)⇒ 夫の死亡に際して、10年以上連れ添った妻が受け取れる年金)は、相続税の課税対象となりません。 |
| 神棚 |
神棚は、相続税法第12条(相続税の非課税財産)第2号の「墓所、霊びょう、及び祭具並びにこれらに準ずるもの」に該当し、相続税の課税価格には算入しません(相法12、相基通12-2)。なお、その代金が相続開始時点で未払であるような場合には、当該未払代金は債務控除できません(相法13③、相基通13-6)。 |
| 仮位牌 (白木位牌 |
相続人(無制限納税義務者)又は包括受遺者が葬儀の際に使用する仮位牌の購入費用は、通常葬式に伴うものと認められる範囲内のものは、葬式費用として債務控除できます。なお、仏壇にお祀りする本位牌の購入費用は葬式費用として債務控除できません(相基通13-4)。 |
| 借入金 |
被相続人の借入金を引き継いだ相続人(相続を放棄した者及び相続権を失った者を除きます。)又は受遺者(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈)の課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額からその者の負担した部分の金額を控除した金額となります(相法13、相基通13-1)。 |
| 仮葬式 |
相続人(無制限納税義務者)又は包括受遺者が支出した仮葬式の費用は、葬式費用として債務控除できます(相基通13-4)。 |
| 仮払金 |
仮払金の価額は、元本の価額(その返済されるべき金額)と利息の価額(課税時期現在の既経過利息として支払を受けるべき金額)との合計額によって評価します。 |
| 勧進 |
勧進(寺院や仏像などの新造・修復・再建のため寄付)は、被相続人の遺贈による勧進であれば勧進した財産は相続財産に含まれませんが、相続人が相続財産を勧進したのであれば相続して寄附したものとされるため相続財産として課税されます。また、不動産や有価証券のように値上がり益があるものは、原則として譲渡所得が課税されます。 |
| 還付加算金 |
相続開始前に被相続人が還付請求していた還付金に係る還付加算金は相続財産として計上します。なお、相続開始後の準確定申告に係る還付金の還付加算金は相続税の対象とはならずに相続人の所得(雑所得)となります。 |
| 還付金 |
被相続人に係る所得税、住民税、消費税等の還付金、後期高齢者医療保険、介護保険、健康保険などの還付金は、相続財産となります。 |
| 元利均等償還が行われる公社債 |
元利均等償還が行われる公社債は、相続税法第24条(定期金に関する権利の評価)第1項第1号(有期定期金)の規定を準用して、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額で評価します(評基通197-4)。
|
| 期間付終身年金 |
保証期間付終身年金(終身年金のひとつで、被保険者が生存している限り継続して年金を受け取ることができるタイプの年金)の価額は、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額で評価します(相法24⑤)。
|
| 企業組合の出資金 |
企業組合、漁業生産組合その他これに類似する組合等に対する出資の価額は、①組合等の純資産価額を基として「純資産価額」(評基通185)の定めを準用して評価します(評基通196)。なお、出資持分を承継することなく、相続人等が現実に出資払戻請求権を行使して出資の払戻しを受けたときには、その払戻しを受けた出資の金額によって評価します。 |
| 議決権のない株式 |
議決権のない株式の価額は、原則として、議決権の有無を考慮せずに原則的評価方式により評価します。なお、一定の要件を満たす場合は原則的評価方式により評価した価額から、その価額に5%を乗じて計算した金額を控除した金額により評価するとともに、当該控除した金額を当該相続又は遺贈により同族株主が取得した当該会社の議決権のある株式の価額に加算して申告することを選択することができます。 |
| 記念メダル |
記念メダルの価額は、一般動産、骨董品の評価を斟酌し、売買実例価額(ネットなどの相続開始日の買取価格)、精通者意見価格等を参酌して評価します(評基通129、135) |
| ギフト券 |
商品券や旅行券、ギフト券、クオカード、株主優待券などの金券は、相続財産になり、その価額は、額面金額又は売買実例価額(ネットなどの相続開始日の買取価格)で評価します(相法22)。 |
| 休業中の会社の株式 |
休業中の会社の株式の価額は、純資産価額方式によって評価します。なお、同族株主以外の者が相続した場合には、通常、配当還元方式によって評価しますが、休業中の会社については、純資産価額によって評価することとされており、配当還元方式は適用できません(評基通189-5)。 |
| 給排水設備 |
給排水設備(棚卸資産を除きます。)の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。ただし、売買実例価額等が明らかでない場合は、同種及び同規格の新品の小売価額から、取得時期から課税時期までの償却費の額を控除した金額によって評価します(評基通129)。なお、家屋と構造上一体となっている設備については、その家屋の価額に含めて評価します(評基通92)。 |
| 教育資金の一括贈与を受けた財産 |
教育資金の一括贈与を受けた財産は、契約期間中に贈与者が死亡した場合には、原則として、その死亡日における非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額に、一定期間内にその贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等のうち、この非課税制度の適用を受けたものに相当する部分の価額がその非課税拠出額のうちに占める割合を乗じて算出した金額(管理残額)を、相続財産に加算します(措法70の2の2)。 |
| 教育用財産 |
教育用財産(幼稚園等における教育又は保育の用に供するもの)は、被相続人により当該被相続人からの相続の開始の年の5年前の年の1月1日前から引き続いて行われてきた幼稚園等の事業を承継し、当該相続の開始の年以後の年も当該事業を引き続いて行うことが確実であると認められるものは、相続税の課税価格に算入しません(相規附則③)。 |
| 協業組合の出資 |
協業組合の出資の価額は、持分会社の出資の評価に準じて評価します。ただし、各組合員の議決権は原則として平等であり、出資と議決権が結びついていないことから、同族株主等の議決権の割合が50%以下の場合の20%評価減、配当還元方式等の定めは適用がありません。 |
| 供託金 |
供託とは、金銭、有価証券などを法務局(供託所)に提出して、その管理を委ね、最終的には供託所がその財産をある人に取得させることによって、一定の法律上の目的を達成しようとするために設けられている制度です。供託当事者(供託者又は被供託者)が死亡した場合は,その相続人が供託金払渡請求を行うことができます。供託当事者が被相続人の場合は供託事由を勘案して相続財産に計上します。 |
| 共同ビルの敷地 |
共同ビルの敷地のように個々の宅地が他の筆の宅地と一体となって利用されているのであれば、他の筆の宅地をも併せた、利用の単位となっている1画地の宅地の価額を評価した上で、個々の宅地を評価します(評基通7-2)。 |
| 共有地 |
共有地の価額は、共有地全体を評価した価額に共有持分の割合を乗じて、被相続人の持分の価額を算出して評価します(評基通2)。 共有地 = 共有地全体の価額 × 持分割合 |
| 共有持分者が死亡した場合 |
共有財産の共有者の一人が死亡した場合、①死亡した共有者に相続人がいる場合はその相続人が相続しますが、②相続人がいない場合は共有者が遺贈により取得します(民法255)。なお、この場合の申告期限は、特別縁故者の財産分与の請求期限の満了の日の翌日から10月以内となります。国税庁HP質疑応答「民法第255条の規定により共有持分を取得した場合の相続税の課税関係」 |
| 漁業権 |
漁業権(漁業権とは、一定の水面で、一定の期間、他人に妨害されることなく特定の漁業を営むことができる権利で、漁業法第60条の定める定置漁業権、区画漁業権及び共同漁業権をいいます。)の価額は、営業権の価額に含めて評価します(評基通163、164)。 |
| 居住建物 |
居住建物(配偶者居住権の目的となっている建物)の価額は、次の算式により評価します(相法23の2)。 居住建物 = 居住建物の相続税評価額 - 配偶者居住権の価額 |
| 居住建物の敷地の用に供されている土地 |
居住建物(配偶者居住権の目的となっている建物)の敷地の用に供されている土地の価額は、次の算式により評価します(相法23の2)。 居住建物の敷地 = 居住建物の敷地の相続税評価額 - 敷地利用権の価額 |
| 居住用の区分所有財産 |
特定の要件を満たす居住用の区分所有財産(分譲マンション)の価額については、「居住用の区分所有財産の評価について」(法令解釈通達)により評価します。 |
| 漁船 |
漁船の価額は、売買実例価額(ネットなどの相続開始日の取引価格等)、精通者意見価格等を参酌して評価します。これらが明らかでない場合は、同種同型の船舶を新造する場合の価額から経過年数に応ずる償却費の額を控除した価額によって評価します(評基通136)。 |
| 拒否権付株式 |
拒否権付株式(株主総会などにおける決議事項について拒否権を発動できる株式をいい別名「黄金株」ともいわれます。)の価額は、拒否権を考慮せずに一般の株式と同様に評価します。「拒否権付株式の評価(資産評価企画官情報)(平成19年3月9日)」 |
| 金貨 |
金貨の価額は、一般動産(棚卸資産を除きます。)の評価に準じて、売買実例価額(ネットなどの相続開始日の買取価格)、精通者意見価格等を参酌して評価します。 |
| 金地金 |
金地金の価額は、一般動産(棚卸資産を除きます。)の評価に準じて、売買実例価額(貴金属業者などの相続開始日の買取価格)等を参酌して評価します(評基通129)。 |
| クオカード |
商品券や旅行券、ギフト券、クオカード、株主優待券などの金券は、相続財産となり、額面金額又は売買実例価額(ネットなどの相続開始日の買取価格)で評価します(相法22)。 |
| 国に寄附(遺贈)した相続財産 |
相続又は遺贈により財産を取得した者が、取得した財産を申告期限までに国若しくは地方公共団体に贈与をした場合には、相続税の課税価格の計算の基礎に算入しません(措法70①)。また、国に遺贈された財産も相続税の課税価格の計算の基礎に算入しません(相法1の3)。 |
| 区分所有財産 |
区分所有に係る財産の各部分の価額は、財産評価基本通達の定めによって評価したその財産の価額を基とし、各部分の使用収益等の状況を勘案して計算した各部分に対応する価額によって評価します(評基通3)。 |
| 区分地上権 |
区分地上権の価額は、その区分地上権の目的となっている宅地(山林)の自用地としての価額に、区分地上権の割合を乗じて計算した金額によって評価します(評基通27-4、53-2、相基通23-1)。 |
| 区分地上権に準ずる地役権 |
区分地上権に準ずる地役権の価額は、その承役地である自用地としての価額に、その地役権の設定契約の内容に応じた土地利用制限率を基とした次の割合を乗じて評価します(評基通27-5)。
|
| クラウドファンディング |
クラウドファンディング(インターネット上で広く資金を集める仕組)は、①「購入型」「寄付型」といった、支援者に請求権などの権利がないものについては評価の対象とならないと考えられますが、②「投資型」「融資型」のような支援金に対して権利を有する形態は投資物件や融資金額で評価すべきものと考えられます。 |
| クラッシックカー |
クラッシックカー(ビンテージカー)の価額は、原則として、相続開始時の売買実例価額(ネットなどの相続開始日の買取価格)、精通者意見価格等を参酌して評価します(評基通129、135)。 |
| クレジットカードの未払額 |
相続人(無制限納税義務者)又は包括受遺者が負担した被相続人のクレジットカードの未払金額は、債務控除の対象となります(相法13)。 |
| 景観重要建造物である家屋及びその敷地 |
景観法に基づき景観重要建造物に指定された建造物である家屋及びその敷地の用に供されている宅地は、「伝統的建造物である家屋及びその敷地の用に供されている宅地の評価方法」(評基通24-8、89-2)に準じ、次の算式により評価します。 景観重要建造物である家屋及びその敷地の用でないものとした場合の価額 × 70% |
| 傾斜地 |
宅地及び宅地比準方式により評価する傾斜地(傾斜度3度以上の市街地農地、市街地周辺農地、市街地山林及び市街地原野)を評価する場合、その評価額から国税局長の定める造成費を控除して評価します(評基通40)。なお、宅地への転用が見込めないと認められる場合(近隣の純山林の価額に比準して評価した価額を下回る場合、又は傾斜度30%以上)は、純山林、純農地、純原野により評価します。 比準宅地の評価額 -国税局長の定める造成費 - 伐採・抜根費 |
| 競馬場敷地 |
競馬場敷地の評価額は、原則として、①「雑種地の評価」(評基通82)を準用して評価しますが、②その規模等の状況からゴルフ場用地と同様に評価することが相当と認められる場合は、「ゴルフ場の用に供されている土地の評価」(評基通83)を準用して評価します。この場合において、造成費に相当する金額については、「市街地山林の評価」(評基通49)の定めにより国税局長が定める金額とします(評基通83-2)。 |
| 下宿家屋 |
下宿(一般的には一定期間の契約で家屋の一部(部屋)を間借りさせるもので、厳密には旅館業法が適用になります。)は、居室の賃貸借ですが借家権がないことから、その敷地はホテルや宿屋の敷地と同様に、自用地価額で評価します。なお、その建物についても自用家屋として評価します。 |
| 結婚・子育て資金の一括贈与を受けた財産 |
結婚・子育て資金の一括贈与を受けた財産は、契約期間中に贈与者が死亡した場合には、原則として、その死亡日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額(管理残額)を、相続財産に加算します(措法70の2の3)。 |
| 気配相場のある株式 |
気配相場等のある株式(①登録銘柄及び店頭管理銘柄、②公開途上にある株式)の価額は、①日本証券業協会の公表する課税時期の取引価格又は課税時期の属する月以前3か月間の月平均額、②公開価格又は課税時期以前の買取価格を勘案して評価します(評基通168、174)。 |
| 原材料 |
原材料の価額は、製造業者が課税時期においてこれを購入する場合の仕入価額に、その原材料の引取り等に要する運賃その他の経費の額を加算した金額によって評価します。ただし、個々の価額を算定し難いものは、たな卸資産の評価の方法(所令99、法令28)に定める方法のうちその企業が所得の金額の計算上選定している方法によることができます(評基通132、133)。 |
| 建設協力金 |
建設協力金の価額は、①無利息又は低利である経済的利益相当額を考慮して賃貸料の額を定めている場合は、建設協力金の全額、②それ以外の場合は、元本額から無利息による経済的利益の額(国税庁の定める基準利率による複利現価率により計算した額)を控除した金額が債務控除の金額となります。平成19年4月26日、裁決事例 |
| 建造中の船舶 |
建造中の船舶の価額は、未完成の状態で、類似ないし同種の売買実例はないことから、「建築中の家屋の評価方法」(評基通91)に準じて、課税時期までに投下された費用の額の合計額の70%に相当する金額によって評価して差し支えないものと考えられます。 |
| 建築中のアパートの敷地 |
建築中のアパートの敷地の価額は、原則として自用地として評価します(評基通89、91)。ただし、古い建物を取り壊して新しい建物に建て替える場合で、旧建物の賃借人が引き続き入居すること、立退料の支払いがないことなど、一定の要件を満たす場合には貸家建付地としての評価が認められます。 |
| 建築中の家屋 |
建築中の家屋には、固定資産税評価額が付けられていませんので、その家屋の費用現価(亡くなった日までに投下された建築費用)の70%に相当する金額によって評価します。また、業者へ支払済みの代金が費用現価よりも多ければ前渡金として相続財産に計上し、少なければ未払金として債務控除します(評基通91)。 |
| 限定承認をした場合の債務控除 |
限定承認を行った場合には、本来の相続財産の価額を超えて債務を弁済する義務を負わないこととされていますから、本来の相続財産の価額を超える部分(生命保険金、退職手当金などのみなし相続財産から支出した金額)の金額については、債務控除をすることはできません。 |
| 原野 |
原野の価額は、①純原野及び中間原野(通常の原野と状況を異にするため純原野として評価することを不適当と認めるもの)は、倍率方式、②市街地原野は、宅地比準方式又は倍率方式により評価します(評基通57)。 |
| 原野の賃借権 |
原野に係る賃借権の価額は、「耕作権の評価」(評基通42)の定めを準用して、①純原野及び中原野に係る賃借権は原野の価額の50%、②市街地原野に係る賃借権は通常支払われるべき立退料、その付近にある宅地に係る借地権の価額等を参酌して求めた金額で評価します(評基通60)。 |
| コインパーキングの敷地 |
コインパーキングの敷地の価額は、①自らが経営している場合は自用地で評価し、②業者に貸し付けている場合は自用地価額からその契約内容に応じた賃借権割合を控除した金額で評価します(評基通86)。 |
| 高圧線が架設されている宅地 |
高圧線が架設されている宅地の価額は、承役地である部分も含め全体を評価した価額から、その承役地である部分を1画地として計算した自用地価額を基に、土地利用制限率を基に評価した区分地上権に準ずる地役権の価額を控除して評価します(評基通25、27-5)。 全体の評価額 - 承役地部分の自用地価額 × 区分地上権に準ずる地役権割合 |
| 公開空地となっている土地 |
いわゆる総合設計制度(建築基準法59の2)により容積率の割増しを受け建物を建築する場合には、敷地内に一定の空地を設け、日常一般に公開することが許可の基準となっています。このようないわゆる公開空地として利用されている宅地については、建物の敷地として評価します。 |
| 公開途上にある株式 |
公開途上にある株式の価額は、①株式の公募又は売出し(公募等)が行われる場合は、その公開価格により評価し、②公募等が行われない場合は、課税時期以前の取引価格等を勘案して評価します(評基通174)。 |
| 高額療養費 |
高額療養費とは、医療費の自己負担額が高額になった場合において、自己負担限度額を超えたときに支給されるものになりますが、この高額療養費の支給が死亡後にあったときは未収金として相続財産に計上します。 |
| 後期高齢者医療保険料 |
相続開始後に納付した後期高齢者医療保険料は、未払費用として債務控除の対象となります。また、後期高齢者医療保険料が納め過ぎとなった場合に還付される金額(過誤納金)はその他財産として相続財産に計上します。 |
| 鉱業権 |
鉱業権(租鉱権の設定されている鉱山の鉱業権を除きます。)の価額は、①操業している鉱山の鉱業権、②休業している鉱山等で近く所得を得る見込の鉱業権、③休業している鉱山等で近く所得を得る見込がない鉱業権、④探鉱中の鉱山の鉱業権ごとに評価します(評基通156)。 |
| 公共料金 |
被相続人に係る電気、ガス、水道、電話などの公共料金(相続開始前に使用したものに限ります。)を負担した相続人(制限納税義務者は、取得した財産でこの法律の施行地にあるものについて負担した公租公課に限ります。)又は包括受遺者は、債務控除することができます(相法13)。 |
| 公債 |
公債(国や地方公共団体が発行する発行者の債務を表示する有価証券)の価額は、銘柄が異なるごとに①「利付公社債の評価」(評基通197-2)や②「割引発行の公社債の評価」(評基通197-3)などの区分に従い評価します(評基通197~197-3)。 |
| 耕作権 |
耕作権の価額は、①純農地及び中間農地に係る耕作権は農地の価額の50%、②市街地周辺農地、市街地農地に係る耕作権はその農地が転用される場合に通常支払われるべき離作料の額、その農地の付近にある宅地に係る借地権の価額等を参酌して求めた金額で評価します(評基通42、43)。なお、やみ小作(農業委員会の許可を受けていないもの)については評価しません。 |
| 合資会社の出資金 |
合資会社の出資金の価額は、原則として、「取引相場のない株式の評価方法」(評基通178)に準じて評価しますが、無限責任社員の有する出資金の評価が債務超過額の場合は債務超過額を債務控除します(評基通194)。 |
| 公社債投資信託 |
公社債投資信託(証券投資信託のうち、その信託財産を公社債に対する投資として運用することを目的とするもの)の価額は、「証券投資信託受益証券」(評基通199)により評価します。 課税時期の基準価額 × 口数 - 源泉徴収税額 - 信託財産保留額及び解約手数料 |
| 公衆用道路 |
公衆用道路は、原則として評価しません。なお、固定資産税評価地目が「公衆用道路」であっても、専ら特定の者の通行の用に供するもの(袋小路のような場合)は、その宅地が私道でないものとして評価した価額の30%相当額で評価します(評基通24)。 |
| 甲種農地 |
甲種農地は、原則として純農地に分類され、その農地の固定資産税評価額に、田又は畑の別に、国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価します(評基通34、37)。 甲種農地 = 固定資産税評価額 × 国税局長の定める田又は畑の倍率 |
| 工場用地 |
工場用地の価額は、①大規模工場用地(一団の工場用地の地積が5万㎡以上のもの。ただし、路線価地域においては、大工場地区として定められている地域に所在するもの)は、路線価に地積を乗じて計算した価額、倍率地域は固定資産税評価額に大規模工場用地の倍率を乗じて計算した価額。なお、地積が20万㎡以上の場合は、95%を乗じた価額で評価します。② ①以外の工場用地の価額は、通常の宅地と同様に評価します(評基通22)。 |
| 鉱泉地 |
鉱泉地の価額は、①利用者が、旅館、料理店等の営業者の場合は、その鉱泉地の固定資産税評価額に、一定の割合を乗じた金額により評価し、②営業者以外の場合はその価額からその価額の30%の範囲内において相当と認める金額を控除した価額によって評価します(評基通69、75)。
① 固定資産税評価額 × |
| 公租公課 |
被相続人に係る公租公課を負担した相続人(制限納税義務者は、取得した財産でこの法律の施行地にあるものについて負担した公租公課に限ります。)又は包括受遺者は、債務控除することができます(相法13)。ただし、相続人などの責任に基づいて納付されることになった附帯税(延滞税、利子税及び加算税)は差し引くことはできません。 |
| 広大地 |
広大地の評価方法は、課税時期が平成29年12月31日以前の場合に適用があり、平成30年1月1日以降は、「地積規模の大きな宅地の評価方法」(評基通20-2)により評価します。なお、広大地の価額は、次の算式により評価します。 宅地の評価額 × 広大地補正率(0.6 - 0.05 × 広大地の地積 ÷ 1,000㎡) |
| 構築物 |
構築物の価額は、その構築物の再建築価額から、建築の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年)の償却費の額(償却方法は定率法)の合計額を控除した金額の70%に相当する金額によって評価します(評基通97)。 ( 構築物の再建築価額 - 償却費の額の合計額 ) × 70% |
| 構築物の所有を目的とする土地の賃借権 |
構築物の所有を目的とする土地の賃借権の価額は、「賃借権の評価(評基通87)」の定めにより評価することになります。なお、財産評価基本通達上の借地権は、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権に限られます。 |
| 構築物の賃借人の土地に対する権利 |
構築物の賃貸借については法律上の特別の保護を与えられたものでないこと等から、原則として、構築物の賃借人の構築物の敷地に対する権利は評価しません。また、構築物の賃借人の構築物に対する権利についても評価しません(評基通31)。 |
| 交通費(葬式に関連する) |
相続人(無制限納税義務者)又は包括受遺者が負担する交通費については、喪主や僧侶などの交通費は「葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの」と考えられますので、葬式費用として債務控除できますが、親族が遠隔地から葬式に参列するための交通費を負担した場合は、葬式費用として債務控除できないものと考えられます(相法13、相基通13-5)。 |
| 高低差のある土地 |
高低差により利用価値が著しく低下している土地に該当する場合に限り、10%の減額補正の適用を検討します。すでに路線価に高低差の影響が加味されていれば、「利用価値が著しく低下している宅地」の減額補正は適用できません。 |
| 校庭として貸している土地 |
校庭として市に賃貸された土地が単に校庭の用に供することのみを目的として賃貸されたものであり、建物の所有を目的とするものでない場合、その賃借権は借地権に該当しませんので、「貸し付けられている雑種地」(評基通86)により評価します。 |
| 香典 |
香典は遺族への贈与であり相続財産に該当しません。なお、社会通念上相当と認められるものについては、個人からのもの、法人からのものを問わず、贈与税も所得税も課税されません(相基通21の3-9)。 |
| 香典返戻費用 |
香典返戻費用は、香典を受けた遺族が支出すべき費用であり、葬式費用として債務控除できません(相基通13-5)。 |
| 公務(職務)遺族年金(公務員及び教職員 |
平成27年10月1日以後、公務員及び教職員の共済組合から組合員の遺族に支給される「公務(職務)遺族年金」は、相続税法3条1項2号(退職手当金)に該当します |
| 合名会社の出資金 |
合名会社(持分会社(会社法575①)のうち、無限責任社員のみで構成される会社形態)の出資金の価額は、「取引相場のない株式の評価」(評基通178)に準じて評価し、債務超過額の場合は被相続人の持分に応ずる債務超過額を債務控除します(評基通194)。 |
| 国外に所在する土地 |
国外に所在する土地の価額は、原則として、売買実例価額、鑑定評価額等を参考に評価します。なお、課税上弊害がない限り、取得価額に時点修正するための合理的な価額変動率を乗じて評価ことができます。また、この場合の合理的な価額変動率は公表されている諸外国における不動産に関する統計指標等を参考とすることができます(評基通5-2)。 |
| 国宝 |
国宝については通達に特に定めがなく、個別に評価します |
| 国民健康保険料 |
相続人(無制限納税義務者)が納付した被相続人の国民健康保険料は、債務控除の対象となります。また、国民健康保険料が納め過ぎとなった場合に還付される金額(過誤納金)は、相続財産となります。 |
| 国民年金死亡一時金 |
国民年金などを受給していた人が死亡したときに遺族に支給される国民年金死亡一時金は、遺族が受け取るべきものであり、相続財産とはなりません。また、国民年金法により支給される国民年金死亡一時金は、非課税と規定されていますので相続人の所得にもなりません。 |
| 心付け |
相続人(無制限納税義務者)又は包括受遺者が、葬儀の際に支出した火葬場のスタッフや霊柩車などの運転手など支払った心付けは、通常葬式に伴うものと認められる範囲内のものは、葬式費用として債務控除できます(相基通13-4)。 |
| 個人向け国債 |
個人向け国債の価額は、課税時期において中途換金した場合に取扱機関から支払いを受けることのできる価額により評価します(評基通5、197-2)。 個人向け国債 = 額面金額 + 経過利子相当額 - 中途換金調整額 |
| 古銭 |
古銭の評価は、①古銭の販売業者が有するものの価額は、たな卸商品等の評価、②上記以外の古銭の価額は、売買実例価額(ネットなどの相続開始日の買取価格)、精通者意見価格等を参酌して評価します(評基通133、135) |
| 国庫短期証券 |
国庫短期証券(日本政府が発行する発行時に割り引いた金額で発行される償還期限が1年以内の割引債)の価額は、「割引発行の公社債の評価」(評基通197-3)により評価します。なお、具体的には国庫短期証券市場の公表している価格により評価します。 |
| 骨とう品 |
書画骨とう品等の評価は、①書画骨とう品の販売業者が有するものの価額は、たな卸商品等の評価、②上記以外の書画骨とう品の価額は、売買実例価額(ネットなどの相続開始日の取引価格等)、精通者意見価格等を参酌して評価します(評基通133、135)。 |
| 固定資産税 |
相続人(制限納税義務者は、取得した財産でこの法律の施行地にあるものについて負担した公租公課に限ります。)又は包括受遺者が負担した被相続人に係る固定資産税や都市計画税は、債務控除の対象となります(相基通13-7)。なお、共有不動産である場合はその共有割合に応じて債務控除します。 |
| 固定資産税評価額が付されていない土地 |
倍率方式により評価する土地について、固定資産税評価額が付されていない場合及び地目の変更等により現況に応じた固定資産税評価額が付されていない場合には、その土地の現況に応じ、状況が類似する付近の土地の固定資産税評価額を基とし、付近の土地とその土地との位置、形状等の条件差を考慮して固定資産税評価額に相当する額を算出して評価します。 |
| ゴルフ会員権 |
預託金制のゴルフ会員権で、①取引相場のあるものは、通常の取引価格の70%相当額で評価し、②取引相場のないものは、返還時期に応じた預託金等の額で評価します(評基通211)。 |
| ゴルフ場敷地 |
ゴルフ場の用に供されている土地(ゴルフ場用地)は、①市街化区域及びそれに近接する地域にあるものは、宅地であるとした場合の金額の60%に相当する金額から、国税局長の定める造成費の金額にそのゴルフ場用地の地積を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価し、②上記以外の地域にあるものは、そのゴルフ場用地の固定資産税評価額に、国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価します(評基通83)。 |
| 災害家屋 |
被災後の現況に応じた固定資産税評価額が付されていない場合には、特定非常災害の発生直前の家屋の価額から、条例に定めるところによりその被災した家屋に適用された固定資産税の軽減又は免除の割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価することができます(「特定非常災害発生日以後に相続等により取得した財産の評価に関する質疑応答事例集」の送付について(情報))。 災害家屋 = 特定非常災害の発生直前の家屋の価額 ×(1-固定資産税の減免割合) |
| 再開発事業施行地内の土地 |
再開発事業施行地内の土地は、①権利変換前の場合は、従前土地について評価し、②権利変換後の場合は、従後土地について評価します。 |
| 祭具 |
祭具や神具などは、相続税法第12条(相続税の非課税財産)第2号の「祭具並びにこれらに準ずるもの」に該当し、相続税の課税価格には算入しません(相法12、相基通12-2)。ただし、金の祭具、神具など、日常崇拝の目的に供されず趣味、観賞用又は投資のために保有されるものについては、非課税財産とはなりません(相基通12-2)。 |
| 財形住宅(一般、年金)貯蓄 |
勤労者財産形成(住宅)貯蓄の価額は、次の算式により評価します。ただし、課税時期の既経過利子の額が少額なものに限り、同時期現在の預入高によって評価できます。 財形住宅貯蓄 = 預入高 + 解約利息(源泉税額控除後) |
| 採石権 |
採石権とは、他人の土地において岩石や砂利などを採取する権利(採石法4)のことで、鉱業権及び租鉱権の評価に準じて評価します(評基通160)。 |
| 財投機関債 |
財投機関債(財投機関が民間の金融市場において個別に発行する債券)は、①金融商品取引所等に上場している場合は、課税時期の最終価格と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価し、②上場していない場合は、公社債の発行価額と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価します(評基通197~197-5)。 |
| 魚 |
魚の価額は、①販売業者が販売の目的をもって有するものは、「たな卸商品等の評価」(評基通133)によって評価し、②それ以外のものは、売買実例価額(ネットなどの取引情報など)、精通者意見価格等を参酌して評価します(評基通134)。 |
| 先物取引保証金 |
先物取引保証金は、先物取引を行う際に商品取引会社や証券会社に差し入れる担保であり、担保財産が金銭であればその金額が相続財産となり、有価証券であればその有価証券を評価した額が相続財産となります。 |
| 雑種地 |
雑種地の価額は、①国税局長が倍率を定めている地域にある雑種地の価額は、その雑種地の固定資産税評価額にその倍率を乗じて計算した金額によって評価し、② ①以外の雑種地は、状況が類似する付近の土地の価額を基とし、その土地とその雑種地との位置、形状等の条件の差を考慮して評定した価額によって評価します(評基通82)。 |
| 雑種地の賃借権 |
雑種地の賃借権の価額は、その賃貸借契約の内容、利用の状況等を勘案して、①地上権に準ずる権利として評価することが相当と認められる賃借権、② ①以外の賃借権に区分して、下記の算式により評価します(評基通87)。
|
| サブリース契約している敷地 |
賃貸物件(貸アパート・マンションなど)をサブリース契約(一括借上げ契約)で貸し付けている家屋の敷地の価額は、原則として「貸家建付地の評価」(評基通26)により評価します。なお、相続開始時点で空室があったとしても、サブリース会社に全部を賃貸していることから賃貸割合は100%となります。 |
| サムライ債 |
サムライ債(海外の発行体が日本の国内市場で円建て発行する債券)の価額は、①金融商品取引所等に上場、②上場していない場合に区分し次の算式により評価します(評基通197~197-5)。
|
| 産業廃棄物の存する土地 |
課税時期において、産業廃棄物が地中に埋設されているのは明らかである場合は、産業廃棄物が埋設されていないものとした場合の評価額から産業廃棄物除去費用に相当する金額を控除して評価します。 |
| 残存期間の不確定な地上権 |
立木一代限りとして設定された地上権などのように残存期間の不確定な地上権の価額は、課税時期の現況により、立木の伐採に至るまでの期間をその残存期間として「地上権の評価」及び「永小作権の評価」の規定(相法23、地価税法24)によって評価します(評基通53)。 |
| 3年以内 贈与財産 |
相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前3年以内(令和6年1月1日以後の暦年課税に係る贈与により取得した財産の場合は、その加算対象期間が相続開始前7年以内)に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産(特定贈与財産を除きます。)の価額(当該財産に係る贈与の時における価額)を相続税の課税価格に加算します(相法19、相基通19-1)。 |
| 山林(土地) |
山林の価額は、その地区について評価倍率表で定める区分により、①純山林及び中間山林は倍率方式、②市街地山林は宅地比準方式又は倍率方式により評価します(評基通45)。 |
| 市街化調整区域内の雑種地 |
市街化調整区域内の雑種地は、状況が類似する付近の土地の価額を基として評価しますが、宅地に比準して評価する場合、法的規制等(開発行為の可否、建築制限、位置等)に係る斟酌割合(減価率)は、市街化の影響度と雑種地の利用状況によって個別に判定します。 状況が類似する付近の土地の価額 ×( 1 - 宅地に比準して評価した場合の斟酌割合 ) |
| 市街地原野 |
市街地原野の価額は、原則としてその原野が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額から、その原野を宅地に転用する場合において通常必要と認められる1㎡当たりの造成費(国税局長の定める金額)を控除した金額に、地積を乗じて計算した金額により評価します(評基通58-3)。 宅地であるとした場合の価額 - 宅地転用に通常必要と認められる国税局長の定める造成費 |
| 市街地山林(土地) |
市街地山林の価額は、原則として、次の算式により評価します。なお、宅地への転用が見込めないと認められる場合には、近隣の純山林の価額に比準して評価します(評基通49)。 宅地であるとした場合の価額 - 宅地転用に通常必要と認められる国税局長の定める造成費 |
| 市街地周辺農地 |
市街地周辺農地とは、市街地農地を除く、①第3種農地に該当するもの、②近傍農地の売買実例価額、精通者意見価格等に照らし、第3種農地に準ずる農地と認められるものをいい、その農地が市街地農地であるとした場合の価額の80%に相当する金額によって評価します(評基通34、36~40)。 市街地周辺農地 = 市街地農地の価額 × 80% |
| 市街地農地 |
市街地農地とは、農地法に規定する許可(転用許可)を受けた農地、市街化区域内にある農地、転用許可を要しない農地として、都道府県知事の指定を受けたものをいい、①宅地比準方式又は②倍率方式により評価します(評基通34、36~40)。
|
| 仕掛品 |
仕掛品の価額は、製造業者がその仕掛品の原材料を課税時期において購入する場合における仕入価額に、その原材料の引取り、加工等に要する運賃、加工費その他の経費の額を加算した金額によって評価します。ただし、個々の価額を算定し難い場合は、所得税の計算上選定している方法によることができます(評基通133)。 |
| 敷金 |
被相続人が賃借人から預かっている敷金は、債務控除の対象となります。また、預かり期間が5年を超える無利息又は低利のものは、その敷金に係る相続開始時現在の経済的利益の金額を複利現価率で計算し、敷金の金額からこの経済的利益の額を控除した金額が債務控除の対象となります。なお、被相続人が賃貸人に預けている敷金は、相続財産となります。 |
| 敷地権 |
敷地権(マンションなどの区分所有建物において、建物と一体化した土地に対する権利)の価額は、敷地権の対象となっている土地全体について評価した価額に、敷地権に係る権利(借地権、地上権、定期借地権等)の種類に応じた評価を行い、その評価額に区分所有者が有する敷地権の割合を乗じて評価します。 敷地権 = 敷地権対象地全体の権利に応じた評価額 × 敷地権割合 |
| 事業用定期借地権 |
事業用定期借地権の価額は、原則として、課税時期において借地人に帰属する経済的利益及びその存続期間を基として評定した価額によって評価します。ただし、課税上弊害がない場合に限り、その定期借地権等の目的となっている宅地の課税時期における自用地としての価額に、一定の算式により計算した数値を乗じて評価することができます(評基通27-2)。 |
| 地金 |
金(地金)の価額は、原則として、売買実例価額(ネットなどの相続開始日の買取価格)、精通者意見価格等を参酌して評価します(評基通129)。 |
| 仕組債 |
仕組債(株価や為替などの変動リスクを背負うことにより、大きな利回りのリターンを得られるもの)の価額は、原則として、その仕組債の内容(ノックイン又はノックアウト価格やその時の償還資産、残存期間など)により評価方法が異なりますが、相続開始日の販売会社の買取価額が合理的なものである限り、その価額で評価してよいものと考えられます。 |
| 事業税 |
被相続人に係る事業税を負担した相続人(制限納税義務者は、取得した財産でこの法律の施行地にあるものについて負担した公租公課に限ります。)又は包括受遺者は、その負担した金額を債務控除することができます(相法13)。 |
| 市県民税 |
被相続人に係る市県民税を負担した相続人(制限納税義務者は、取得した財産でこの法律の施行地にあるものについて負担した公租公課に限ります。)は、その負担した金額を債務控除することができます(相法13)。 |
| 時効取得した土地 |
被相続人が占有してきた土地について、相続人が時効取得を主張して訴訟を提起し、裁判で認められた場合、その効力は時効の起算日に遡及しますが、被相続人が時効を援用していなかったので、相続税の課税財産に算入しません。なお、相続人が時効を援用したときに一時所得として所得税が課されます。 |
| 自己株式 |
評価会社が自己株式を所有している場合の株主区分の判定は、その自己株式に係る議決権の数は無いものとして計算した議決権の数をもって評価会社の議決権の総数となります。なお、自己株式は、取引相場のない株式の評価明細書第5表には記載を要しません(評基通188-3) |
| 資材置き場 |
第三者に貸し付けている資材置き場は、賃借権が設定されている雑種地として評価します。ただし、農地等の価額を基として評価した場合は、原則として、農業用施設用地の評価(評基通24-5)に準じて、農地等の価額に造成費相当額を加算した価額により評価します(ただし、その価額は宅地の価額を基として評価した価額を上回りません。)(評基通7、82)。 |
| 資産担保証券 |
資産担保証券(ABS)とは、商業用不動産担保ローンや住宅ローン、自動車ローン、リース、クレジットカードなどに関する貸付金銭債権などの資産を裏付けとして発行される証券の総称で、「利付公社債の評価」(評基通197-2)に準じて評価します。 |
| 四十九日の費用 |
「四十九日」とは、命日から数えて49日目に行う追善法要(法会)のことで、財産評価基本通達の「葬式費用でないもの」に記載のある「法会に要する費用」に該当しますので、葬式費用として債務控除できません(相基通13-5)。 |
| 死体捜索費用 |
相続人(無制限納税義務者)又は包括受遺者が支出した遺体の捜索、死体や遺骨の運搬費は、葬式費用として債務控除できます(相基通13-4)。なお、遺体解剖費用は、医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用とされ葬式費用として債務控除できません(相基通13-5)。 |
| 自治会に寄附(遺贈)した相続財産 |
自治会は、その構成員である町又は字の区域その他市町村内の一定の区域内に住所を有する者の利益のために活動するものであることから、相続税法第12条第1項第3号に規定する「公益を目的とする事業を行う者」に該当しません。したがって、相続税法第66条第1項の規定により、自治会に相続税が課税されます(相法12①、66)。 |
| 失踪宣告が行われたことに伴い死亡退職金が支払われた場合 |
従業員が行方不明となり、失踪期間満了後に死亡退職金を支給した場合は、死亡したとみなされた日から3年を経過した日以後に支払われることになりますが、従業員が死亡した場合には、退職手当金等の額は、退職給与規程の定めるところに基づいて自動的に確定すると解されますので、相続税法第3条第1項第2号に規定する退職手当金等に該当します。なお、役員の場合は株主総会等の決議により決まりますので、遺族の一時所得に該当します。 |
| 実用新案権 |
実用新案権は、「特許権の評価」(評基通140~145)の定めを準用して、その権利に基づき将来受ける補償金の額の基準年利率による複利現価の額の合計額によって評価します。なお、権利者が自ら実用新案を実施している場合は、その者の営業権の価額に含めて評価します(評基通146)。 |
| 私道 |
私道の価額は、①専ら特定の者の通行の用に供されている私道は、宅地として評価した価額の30%に相当する価額によって評価し、②その私道が不特定多数の者の通行の用に供されているときは、その私道の価額は評価しません(評基通24)。 |
| 自動積立定額貯金 |
自動積立定額貯金の価額は、課税時期における預入高と解約利率により計算した既経過利子の額(源泉徴収されるべき所得税等の額に相当する金額を控除した金額)との合計額により評価します(評基通203)。 自動積立定額貯金 = 預入高 + 解約利息(源泉税額控除後) |
| 支払期日未到来の既経過賃料 |
賃貸料の支払期日を毎月末日とする賃貸借契約において、その月の初めから相続開始までの期間に対応する既経過分の賃料相当額については、その賃料の支払期日が到来していないので、相続税の課税価格に算入しなくて差し支えありません(評基通208)。 |
| 地盤に甚だしい凹凸のある宅地 |
地盤に甚だしい凹凸のある宅地の価額は、同一路線価の土地に比べ利用価値が低下していると認められる部分の面積に対応する部分の価額に10%を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価することができます。 宅地の価額 - 利用価値が低下していると認められる部分の面積に対応する価額 × 10% |
| 死亡広告 |
相続人(無制限納税義務者)又は包括受遺者が支出した死亡広告費用は、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるので、葬式費用として債務控除できます(相基通13-4)。 |
| 死亡診断書 |
相続人(無制限納税義務者)又は包括受遺者が医療機関に支払った死亡診断書の費用は、火葬の際に必要な書類であり、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるので、葬式費用として債務控除できます(相基通13-4)。 |
| 死亡退職金を辞退した場合 |
遺族が受領した退職金は、その支給について正当な権限を有する株主総会及び取締役会の決議に基づいて支給されたものであることから、受領した退職金を返還したとしても相続税が課税されることにかわりはありません。 |
| 死亡退職時に遺族補償金として支給された金額 |
死亡退職時に遺族補償金として支給された金額は、名目はどうであれ、被相続人の勤務に基づいて支給されるものですから、相続税法基本通達3-17のただし書に該当し、相続税法第3条第1項第2号に規定する退職手当金等に該当します。 |
| 市民農園として貸し付けている農地(生産緑地地区内) |
市民農園の用に供されている農地(生産緑地地区内)は耕作権の目的となっている農地には該当しません。このため、当該市民農園は、生産緑地としての利用制限に係る斟酌と賃貸借契約の期間制限に係る斟酌をして評価します(評基通41、87⑵)。 農地の価額 ×( 1 - 法定地上権割合×0.5※ )
|
| 市民緑地契約が締結されている土地 |
一定の要件(都市緑地法第55条第1項に規定する市民緑地で貸付期間が20年以上など)を満たす市民緑地契約が締結されている土地の価額は、次の算式により評価します。 市民緑地契約が締結されていないものとして評価した価額 × 80% |
| 借地権 |
借地権の価額は、自用地の価額に国税局長の定める借地権割合を乗じて求めます。ただし、借地権の設定に際しその設定の対価として通常権利金その他の一時金を支払うなど借地権の取引慣行があると認められる地域以外の地域にある借地権の価額は評価しません(評基通27)。 |
| 借地権と区分地上権に準ずる地役権とが競合する土地 |
借地権と区分地上権に準ずる地役権などが設定されている宅地の価額は、その宅地の自用地価額から区分地上権に準ずる地役権の価額とその宅地に区分地上権に準ずる地役権が設定されていることに伴う調整をした後の借地権の価額を控除した価額によって評価します(評基通25-3⑶、27-5、27-6⑵)。 自用地価額 -( 自用地価額 × 地役権割合)-( 自用地価額 × 借地権割合 ×( 1 - 地役権割合 ) |
| 借家権 |
借家権の価額は、家屋の評価又は附属設備等の評価等の定めにより評価したその借家権の目的となっている家屋の価額に、国税局長の定める借家権割合(30%)を乗じて計算した金額によって評価します。ただし、借家権の価額は、その権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものについては、評価しません(評基通94)。 |
| 借家人の有する宅地等に対する権利 |
借家人がその借家の敷地である宅地等に対して有する権利の価額は、原則として、次に掲げる算式により計算した価額によって評価します。ただし、これらの権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものについては、評価しません(評基通31)。 借家の敷地である宅地に係る借地権の価額 × 借家権割合(30%) × 賃借割合 |
| 社債 |
公社債の価額は、①利付公社債、②割引発行の公社債、③元利均等償還が行われる公社債、④転換社債型新株予約権付社債の区分に従い、券面額100円当たりの価額に公社債の券面額を100で除した数を乗じて計算した金額によって評価します(評基通197)。 |
| 社債類似株式 |
社債類似株式(一定期日後に発行価額で償還される、議決権を有しないなどの条件を満たす株式)の価額は、社債に類似していることから、「利付公社債の評価」(評基通197-2)に準じて評価します。 公社債の発行価額 + 既経過利息の額(源泉税控除後) |
| 社宅の敷地 |
社宅は、一般の家屋の賃貸借と異なり賃料が極めて低廉であるなどその使用関係は従業員の身分を保有する期間に限られることから、一般的に借地借家法の適用はないとされています。したがって、社宅の敷地の価額は、自用地として評価します(評基通26)。 |
| 重加算税 |
相続開始後に納付した被相続人に係る重加算税を負担した相続人(制限納税義務者は、取得した財産でこの法律の施行地にあるものについて負担した公租公課に限ります。)又は包括受遺者は、相続人の責めに帰すべき事由により納付することとなったものを除き、債務控除の対象となります(相法13)。 |
| 終身定期金 |
終身定期金は、次の①~③のいずれか多い金額によって評価します(相法24①三)。
|
| 終身保険 |
終身保険(一般的に一定額の死亡保障・高度障害保障が一生続く保険)は、保険事故発生の有無により①「生命保険金」(相法3、12)又は②「生命保険契約に関する権利の評価」(評基通214)により評価します。 |
| 住宅取得等資金の贈与 |
住宅取得等資金の贈与の特例(措法70の2)により贈与税の課税価格に算入されなかった住宅取得資金の金額は、相続の開始前3年以内(令和6年1月1日以後の暦年課税に係る贈与により取得した財産の場合、その加算対象期間が相続開始前7年以内)に被相続人から贈与により取得した場合においても、贈与税の申告書を提出していれば相続税の課税価格に加算する必要がありません(措通70の2-14)。 |
| 重度心身障害者医療費助成金 |
重度心身障害者医療費助成金は、医療機関を受診した場合の医療費の一部を都道府県や市が助成する制度で、被相続人に係る当該助成金が相続開始後に支払われた場合は、相続財産として計上します。 |
| 収入保障保険金 |
収入保障保険(死亡保険金を分割で受け取ることのできる保険)は、給付金を受け取る権利(定期金に関する権利)の評価額が課税対象となります。なお、相続人(相続放棄者や相続権を失った者を除きます。)の給付金を受け取る権利の評価額に対しては、一定額が非課税(500万円×法定相続人の数)とされます(相法3、12、15)。 |
| 住民税 |
相続開始後に納付した被相続人に係る住民税を負担した相続人(制限納税義務者は、取得した財産でこの法律の施行地にあるものについて負担した公租公課に限ります。)又は包括受遺者は債務控除の対象となります(相法13)。なお、住民税は死亡した年度分についてはかかりません。 |
| 住民税の還付金 |
被相続人に係る所得税、住民税、消費税等の還付金、後期高齢者医療保険、介護保険、健康保険などの還付金は、相続財産となります。 |
| 重要文化財建造物 |
重要文化財建造物である家屋の価額は、当該家屋の固定資産税評価額の30%で評価します。なお、固定資産税評価額が付されていない場合には、その文化財建造物の再建築価額から、経過年数に応ずる減価の額を控除した価額の70%に相当する金額で評価します(評基通89-2)。 |
| 重要文化財建造物の敷地 |
重要文化財建造物の敷地は、それが重要文化財建造物の敷地でないものとした場合の価額の30%で評価します。なお、倍率地域で固定資産税評価額が付されていない場合には、その宅地と状況が類似する付近の宅地の固定資産税評価額を基とし評価します(評基通24-8、83-3)。 |
| 重要有形民俗文化財 |
重要有形民俗文化財に評価については、通達に特に定めがなく、個別に評価します |
| 受益証券発行信託の受益証券 |
受益証券発行信託の受益証券のうち、上場されているもの(ETF、ETN)の価額は、1口ごとに評価するものとし、「上場株式の評価」(評基通169)から「上場株式についての最終価格の月平均額の特例」(評基通172)までの定めに準じて評価し、受益証券発行信託証券に係る金銭分配期待権の価額は、「配当期待権の評価」(評基通193)に準じて評価します(評基通213-2)。 |
| 出資金 |
出資金は、出資先の企業形態により、持分会社の出資、医療法人の出資、農業協同組合等の出資、企業組合等の出資などの区分により評価します(評基通194~196)。 |
| 出版権 |
出版権の価額は、出版業を営んでいる者の有するものにあっては、営業権の価額に含めて評価し、その他の者の有するものにあっては、評価しません(評基通154)。 |
| 種類株式 |
種類株式とは、会社法108条に基づき、株式会社が剰余金の配当その他の権利の内容が異なる2種類以上の株式を発行した場合の各株式をいい、配当優先株式、無議決権株式、社債類似株式、拒否権付株式について評価の定めがあります。 |
| 準確定申告に係る還付加算金 |
被相続人の準確定申告に係る還付加算金は、確定申告書の提出により原始的に取得するものであることから相続人の固有財産となります。したがって、相続税の対象とはならずに相続人の雑所得の対象となります。 |
| 純金積立て |
純金積立て(毎月一定金額の純金を少しずつ購入する投資方法)の価額は、原則として、売買実例価額(純金積立を利用している業者の買取価格)、精通者意見価格等を参酌して評価します(評基通129)。 |
| 純原野 |
純原野の価額は、その原野の固定資産税評価額に、状況の類似する地域ごとに、その地域にある原野の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価します(評基通58)。 純原野 = 固定資産税評価額 × 国税局長の定める倍率 |
| 純山林 |
純山林の価額は、その山林の固定資産税評価額に、地勢、土層、林産物の搬出の便等の状況の類似する地域ごとに、その地域にある山林の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価します(評基通47)。 純山林 = 固定資産税評価額 × 国税局長の定める倍率 |
| 純農地 |
純農地の価額は、その農地の固定資産税評価額に、田又は畑の別に、地勢、土性、水利等の状況の類似する地域ごとに、その地域にある農地の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価します(評基通37)。 純農地 = 固定資産税評価額 × 国税局長の定める倍率 |
| ジョイント・テナンシー (合有不動産) |
合有不動産権者の相続開始による生存合有不動産権者への合有不動産権の移転は、死因贈与契約によるものであるといえるため、被相続人から死因贈与(遺贈)により取得したものとして相続税の課税対象となります。 |
| 傷害疾病定額保険 |
傷害疾病定額保険の死亡保険金は、相続税法第3条第1項第1号に規定する生命保険契約に含まれます(相基通3-4)。なお、相続人(相続放棄者や相続権を失った者を除きます。)が受け取った生命保険金には非課税限度額(500万円×法定相続人の数)があります(相法3、12、15)。 |
| 消火設備 |
消火設備は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。ただし、売買実例価額等が明らかでない場合は、同種及び同規格の新品の小売価額から、取得時期から課税時期までの償却費の額を控除した金額によって評価します。なお、家屋と構造上一体となっている設備については、その家屋の価額に含めて評価します(評基通92、128~130)。 |
| 小規模企業共済制度の遺族が受領する一時金 |
共済契約者の死亡による事業の廃止等の事由により、独立行政法人中小企業基盤整備機構から遺族に支払われる一時金は、相続税法3条1項2号(退職手当金)に該当し(相令1の3十)、共済金を分割払の方法により支給を受けていた共済契約者の死亡により、遺族に支払われる支給期月末到来分につき一括繰上支給される一時金は、相続税法3条1項6号(契約に基づかない定期金に関する権利)に該当します。(相基通3-29) |
| 小規模宅地 |
個人が、相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた建物等の敷地となっている宅地等のうち一定のものがある場合には、その宅地等のうち一定の面積までの部分については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定額を減額します(措法69の4)。 |
| 証券CFD |
証券CFD(差金決済)とは、証拠金を預託し、株価指数、債券先物等の指数価格に連動する商品に投資し、差金決済が行われる取引であり、相続発生日で未決済の取引がある場合は、その日の最終価格で決済した場合の利益又は損失の金額が相続税財産となります。 |
| 証券投資信託 |
証券投資信託の評価は、①金融商品取引所に上場されている証券投資信託の受益証券については、上場株式の評価の定めに準じて評価し、②それ以外の証券投資信託の受益証券は、解約請求等により、証券会社等から支払いを受けることができる価額で評価します(評基通199)。 |
| 昇降設備 |
昇降設備は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。ただし、売買実例価額等が明らかでない場合は、同種及び同規格の新品の小売価額から、取得時期から課税時期までの償却費の額を控除した金額によって評価します。なお、家屋と構造上一体となっている設備については、その家屋の価額に含めて評価します(評基通92、128~130)。 |
| 上場株式 |
上場株式は原則として、①課税時期の最終価格、②課税時期の属する月の月中平均額、③課税時期の属する前月の月中平均額、④課税時期の属する前々月の月中平均額のうち、最も低い価額によって評価します(評基通168~172)。 |
| 上場新株予約権 |
上場新株予約権は、①金融商品取引所に上場されているものは、課税時期の最終価格と上場期間中の新株予約権の毎日の最終価格の平均額のいずれか低い価額によって評価し、②上場廃止後権利行使期間内にあるものは、課税時期におけるその目的たる上場株式の評価額から権利行使価額を控除した金額に、新株予約権1個の行使により取得することができる株式数を乗じて計算した金額によって評価します(評基通193-3)。 |
| 上場投資証券 |
ETNや指標連動証券とも呼ばれ(受益証券発行信託証券)、特定の指標に連動する金融商品で、「上場株式の評価」(評基通169)に準じて評価します。また受益証券発行信託証券に係る権利の価額は、「配当期待権の評価」(評基通193)に準じて評価します(評基通199⑵注)。 |
| 上場不動産投資信託 |
上場不動産投資信託(J-REIT)は、「上場株式の評価」(評基通169)に準じて評価します。なお、不動産投資信託証券に係る投資口の分割等に伴う無償交付期待権の価額は「株式無償交付期待権の評価」(評基通192)に準じて評価し、金銭分配期待権の価額は「配当期待権の評価」(評基通193)に準じて評価します(評基通213)。 |
| 使用貸借している土地 |
使用貸借に係る使用借権の価額は、零として取り扱われるので、使用貸借により貸し付けられている土地について、使用借人が賃貸建物等の敷地として利用していても自用地の価額により評価します。また、所有する宅地の一部を自ら使用し、他の部分を使用貸借により貸し付けている場合には、その全体を1画地の宅地として評価します(昭和48年11月1日付直資2-189)。 |
| 譲渡担保 |
譲渡担保(金銭消費貸借の担保として当該担保物の所有権を移転したもの又は債務金額によって買戻しする特約のあるもの)については、①債権者は、債権金額を課税価格計算の基礎に算入し、当該譲渡担保財産は算入しません。②債務者は、当該譲渡担保の目的たる財産を課税価格計算の基礎に算入し、債務金額に相当する金額は控除します(相基通11の2-6) |
| 消費税 |
被相続人に係る消費税を負担した相続人(制限納税義務者は、取得した財産でこの法律の施行地にあるものについて負担した公租公課に限ります。)又は包括受遺者は、債務控除することができます(相基通13-8)。なお、準確定申告に係る消費税についても債務控除が可能です。 |
| 消費税の還付金 |
被相続人に係る所得税、住民税、消費税等の還付金、後期高齢者医療保険、介護保険、健康保険などの還付金は、相続財産となります。 |
| 商標権 |
商標権は、特許権の評価(評基通140~145)の定めを準用して、その権利に基づき将来受ける補償金の額の基準年利率による複利現価の額の合計額によって評価します。なお、権利者が自ら実用新案を実施している場合は、その者の営業権の価額に含めて評価します(評基通146)。 |
| 商品 |
棚卸商品の価額は、販売価額から、適正利潤の額、予定経費の額及びその商品につき納付すべき消費税額を控除した金額によって評価します。ただし、個々の価額を算定し難い場合は、所得税の計算上選定している方法によることができます(評基通133)。 |
| 商品券 |
商品券や旅行券、ギフト券、クオカード、株主優待券などの金券は、相続財産になり、額面金額又は売買実例価額(ネットなどの相続開始日の買取価格)で評価します(相法22)。 |
| 消滅時効の完成した債務 |
相続の開始の時において、既に消滅時効の完成した債務は、「確実と認められる債務」(相法14①)に該当しないものであり、債務控除できません(相基通14-4)。 |
| 賞与 |
相続開始の時において支給期の到来していない賞与、俸給、給料等は、本来の相続財産に該当します(相基通3-32、3-33)ので、相続税法第12条第1項第6号に規定する退職手当金等の非課税規定の適用がありません。 |
| ショーグン債 |
ショーグン債(外国の発行者が日本国内で発行する外貨建ての債券)の価額は、①金融商品取引所等に上場、②上場していない場合に区分し次の算式により評価します(評基通197~197-5)。なお、邦貨換算は、対顧客直物電信買相場(TTB)により計算します(評基通4-3)。
|
| 書画 |
アンティーク品や書画骨とう品等の評価は、①書画骨とう品の販売業者が有するものの価額は、たな卸商品等の評価、②上記以外の書画骨とう品の価額は、売買実例価額(ネットなどの相続開始日の取引価格等)、精通者意見価格等を参酌して評価します(評基通133、135)。 |
| 所得税 |
被相続人に係る所得税を負担した相続人(制限納税義務者は、取得した財産でこの法律の施行地にあるものについて負担した公租公課に限ります。)又は包括受遺者は、債務控除することができます(相法13)。なお、準確定申告に係る所得税についても債務控除が可能です。 |
| 所得税の還付金 |
被相続人に係る所得税、住民税、消費税等の還付金は、相続財産となります。なお、還付加算金は相続人の請求によって原始的に取得するものであり、所得税(雑所得)の課税対象となり、相続税の課税価格には算入されません。 |
| 所得補償保険金 |
死亡後に支払われた所得補償保険(自営業の方などが病気やケガによって仕事ができなくなった場合に備えるために、年収の一定割合を補償する保険)は、本来の相続財産であり、非課税規定の適用がありません(相基通3-7)。⇔ 収入保障保険金 |
| 初七日の費用 |
「初七日」は、追善法要(法会)のことで、財産評価基本通達の「葬式費用でないもの」に記載のある「法会に要する費用」に該当しますので、葬式費用として債務控除できません(相基通13-5)。なお、初七日の際に納骨を行ったときは、納骨費用と初七日の法会費用が明確に区分できる場合には、納骨費用を葬式費用として債務控除することができます。 |
| 所有権留保契約に基づく不動産 |
購入代金を完済していないため、所有権留保契約により所有権移転登記を受けていない不動産は、その不動産を自己の財産と同様に使用・収益・処分することが可能であると認められる限り、相続財産としてその相続税評価額を課税価格に算入します。 |
| じんかい処理設備 |
じんかい処理設備(棚卸資産を除きます。)は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。ただし、売買実例価額等が明らかでない場合は、同種及び同規格の新品の小売価額から、償却費の額を控除した金額によって評価します。なお、家屋と構造上一体となっている設備については、その家屋の価額に含めて評価します(評基通92、128~130)。 |
| 新株引受権 |
新株引受権は、その株式の割当てを受ける権利の発生している株式について、各種株式の評価方法の定めにより評価した価額から割当てを受けた株式1株につき払い込むべき金額を控除した金額によって評価します(評基通191)。 |
| 新規公開株 |
IPO(Initial Public Offering)株式とは、証券市場に新規公開する株式で、①株式の公募又は売出し(公募等)が行われる場合は、その公開価格により評価し、②公募等が行われない場合は、課税時期以前の取引価格等を勘案して評価します(評基通174)。 |
| 神具 |
神具は、相続税法第12条(相続税の非課税財産)第2号の「祭具並びにこれらに準ずるもの」に該当し、相続税の課税価格には算入しません。 |
| 心身障害者扶養共済制度に基づく受給権 |
心身障害者扶養共済制度(条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるもの)に基づいて支給される給付金を受ける権利は、相続税の課税価格に算入しません(相法12①四)。 |
| 信託受益権 |
信託受益権の価額は、次により評価します(評基通202)。
|
| 震動の甚だしい宅地 |
震動の甚だしい宅地は、同一路線価の土地に比べ利用価値が低下していると認められる部分の面積に対応する部分の価額に10%を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価することができます。 宅地の価額 - 利用価値が低下していると認められる部分の面積に対応する価額 × 10% |
| 信用金庫、信用組合の出資金 |
信用金庫、信用組合のように、その組合の行う事業によって、その組合員及び会員のために最大の奉仕をすることを目的とし営利を目的として事業を行わない組合等に対する出資金は、払済出資金額によって評価します(評基通195)。 |
| 信用取引配当金 |
信用取引で建玉を保有している場合、決算日の概ね3~4か月後に配当落調整額の授受が行われます。配当落調整額は、被相続人が買建てしていた場合は相続財産となり、売建ての場合は相続債務となります。 |
| 水道施設利用権 |
水道施設利用権とは、水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して水の供給を受ける権利をいい、税法上は繰延資産に計上されますが、財産性がなく、相続税の課税財産に該当しません。 |
| 水没した土地 |
災害等によって海面下に没した(水没した)土地等の価額は、その状態が一時的なものである場合を除いて、評価しないこととします。(平成30年1月15日「特定非常災害発生日以後に相続等により取得した財産の評価に関する質疑応答事例集」Q4) |
| 水路のある宅地 |
水路や河川を隔てて土地がある場合、評価対象地が接道義務を満たしているものと認められれば、評価対象地と橋そして水路を含めた全体を想定整形地とし、そこから評価対象地を除いた橋と水路の部分をかげ地として不整形地の斟酌を行い評価します。 |
| ストックオプション |
その目的たる株式が上場株式又は気配相場等のある株式であり、課税時期が権利行使可能期間内にあるストックオプションの価額は、次の算式によって評価します(評基通193-2)(非上場会社が発行するストックオプションの価額については、その発行内容等を勘案し個別に評価)。 ( 課税時期における株式の価額 − 権利行使価額 ) × ストックオプション1個の行使可能株式数 |
| ストリップス国債 |
ストリップス国債とは、国債の元本部分と利金部分が分離して別々に流通するゼロクーポン債であり、割引債の評価の定めに準じた次の算式で評価します(評基通197-2)。 発行価額 + 既経過償還差益 + 既経過利息(源泉所得税相当額控除後) |
| 清算中の会社 |
清算中の会社の株式は、清算の結果分配を受ける見込みの金額の課税時期から分配を受けると見込まれる日までの期間(その期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、これを1年とします。)に応ずる基準年利率による複利現価の額によって評価します(評基通189⑹)。 |
| 生産品 |
生産品の価額は、販売価額から、その販売価額のうちに含まれる適正利潤の額、予定経費の額及び製品につき納付すべき消費税額を控除した金額によって評価します。ただし、個々の価額を算定し難い場合は、所得税の計算上選定している方法によることができます(評基通133)。 |
| 生産緑地 |
生産緑地の価額は、課税時期において、①買取りの申出をすることができない生産緑地と、②買取りの申出ができる生産緑地に区分により、次の算式で評価します(評基通40-3)。
|
| 生存条件付定期金 |
定期金給付契約に関する権利で、その権利者に対し、一定期間、かつ、その目的とされた者の生存中、定期金を給付する契約(生存条件付定期金)に基づくものの価額は、有期定期金として算出した金額又は終身定期金として算出した金額のいずれか少ない金額により評価します(相法24③)。⇔収入保障保険金 |
| 製品 |
製品の価額は、販売価額から、その販売価額のうちに含まれる適正利潤の額、予定経費の額及び製品につき納付すべき消費税額を控除した金額によって評価します。ただし、個々の価額を算定し難い場合は、所得税の計算上選定している方法によることができます(評基通133)。 |
| セイフティ共済の解約手当金 |
経営セイフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、加入者の死亡と同時にその時点で解約されたものとみなされ、加入者の事業所得等の収入となります。この解約手当金の支給を受ける権利は、亡くなられた加入者の相続財産となります。なお、解約手当金を含む被相続人の準確定申告に係る所得税額は債務として相続財産の価額から控除することができます。 |
| 政府保証債 |
政府保証債(特別の法律によって設立された政府関係機関や株式会社などが事業資金を調達するために発行する債券)は、①金融商品取引所等に上場している場合、②上場していない場合により次の算式により評価します(評基通197~197-5)。
|
| 生命保険金 |
被相続人の死亡により生命保険金を取得した場合においては、当該保険金のうち被相続人が負担した保険料等の金額の当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分が相続又は遺贈により取得したものとみなされます。なお、相続人(相続放棄者や相続権を失った者を除きます。)が受け取った生命保険金には非課税限度額(500万円×法定相続人の数)があります(相法3、12、15)。 |
| 生命保険の権利 |
相続開始の時において、まだ保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、解約返戻金の額によって評価します。解約返戻金(源泉徴収税額控除後の金額)のほかに支払われることになる前納保険料(前払保険料)の金額、剰余金の分配等がある場合にはこれらの金額を加算した金額によって評価します(評基通214)。 |
| 生命保険料の返還金(払戻金) |
生命保険契約の定めるところにより生命保険契約の解除又は失効によって支払を受ける金額又は一定の事由(被保険者の自殺等)に基づき保険金の支払をしない場合において支払を受ける払戻金等は、「生命保険契約に関する権利」(相法3①三)に該当します(相基通3-39)。なお、相続人(相続放棄者や相続権を失った者を除きます。)が受け取った生命保険金には非課税限度額(500万円×法定相続人の数)があります(相法3、12、15)。 |
| 税理士費用 |
相続税の申告のために支出した税理士費用は、相続開始後に発生する費用であり、被相続人に係る費用ではなく相続人が負担すべき費用ですので債務控除の対象とはなりません。 |
| 世界銀行債 |
世界銀行債の価額は、①金融商品取引所等に上場、②上場していない場合に区分し次の算式により評価します(評基通197~197-5)。なお、邦貨換算は、対顧客直物電信買相場(TTB)により計算します(評基通4-3)。
|
| 接道義務を満たさない土地 |
建築基準法では、「建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならない。」と定められており接道義務を果たしていない宅地は、「無道路地の評価」(評基通20-3)に準じて評価します。 |
| セットバックが必要な土地 |
建築基準法第42条第2項に規定する道路に面しており、将来、建物の建替え時等に同法の規定に基づき道路敷きとして提供しなければならない部分を有する宅地の価額は、次の算式により計算した金額によって評価します(評基通24-6)。
宅地の評価額 -宅地の評価額 × |
| ゼロクーポン債 |
ゼロクーポン債とは、額面金額より割り引いて発行される利息がゼロ(利札クーポンがない)の債券で、割引債の評価の定めに準じた次の算式で評価します(評基通197-2)。 ゼロクーポン債 = 発行価額 + 既経過償還差益 + 既経過利息(源泉税控除後) |
| 前納保険料 |
相続や遺贈によって取得したものとみなされる保険金には、本来の保険金のほか、保険契約に基づき分配を受ける剰余金、割戻しを受ける割戻金及び払戻しを受ける前納保険料で、保険金とともに受け取るものも含まれますので、一定額の非課税の適用があります(相基通3-8)。 |
| 船舶 |
船舶は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。これらが明らかでない場合は、同種同型の船舶を新造する場合の価額から経過年数に応ずる償却費の額を控除した価額によって評価します(評基通136)。 |
| 占用権 |
占用権の価額は、占用権の目的となっている土地の価額に、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる割合を乗じて計算した金額によって評価します。①取引事例のある占用権は国税局長が定める割合、②地下街又は家屋の所有を目的とする占用権は借地権割合の3分の1に相当する割合、③上記以外の占用権は法定地上権割合の3分の1に相当する割合により評価します(評基通87-5)。 |
| 占用権の目的となっている土地 |
占用権の目的となっている土地は、その占用権の目的となっている土地の付近にある土地の評価額を基とし、その土地とその占用権の目的となっている土地との位置、形状等の条件差及び占用の許可の内容を勘案して評価します(評基通87-6)。 |
| 騒音のある宅地 |
評価対象地が線路沿いにあるなどして、生活環境を損なわせ、騒音が取引金額に影響を受ける場合には、利用価値が著しく低下している宅地として評価減をすることができます。騒音による評価減が認められるかどうかは、路線価に織り込み済みか否かで判断します。 |
| 増改築後の家屋 |
増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない場合の家屋は、①状況の類似した付近の家屋の固定資産税評価額を基として、その付近の家屋との構造、経過年数、用途等の差を考慮して評定した価額を加算した価額に基づき評価します。②状況の類似した付近の家屋がない場合には、その増改築等に係る部分の再建築価額から課税時期までの間における償却費相当額を控除した価額の70%に相当する金額を加算した価額で評価します。 |
| 葬祭費 |
葬祭費は、被相続人ではなく相続人が受け取るべきものであり、相続財産とはなりません。なお、国民健康保険法により支給される葬祭費は、非課税と規定されていますので相続人の所得にもなりません。 |
| 葬式会場使用料 |
相続人(無制限納税義務者)又は包括受遺者が支出した会場使用料は、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるので、葬式費用として債務控除できます(相基通13-4)。 |
| 葬式費用 |
葬式費用として債務控除できるものは、①葬式、若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用、②葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当と認められるもの、③そのほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの、④死体捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用とされています(相基通13-4)。 |
| 造成中の宅地 |
造成中の宅地の価額は、その土地の造成工事着手直前の地目により評価した価額に、その宅地の造成に係る費用現価(課税時期までに投下した日等の額を課税時期の価額に引き直した額の合計額)の80%に相当する金額を加算した金額によって評価します(評基通24-3)。 造成工事着手直前の地目により評価した価額 + 造成に係る費用現価 × 80% |
| 相続開始前3年以内に贈与があった財産 |
相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前3年以内(令和6年1月1日以後の暦年課税に係る贈与により取得した財産の場合は、その加算対象期間が相続開始前7年以内)に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産(特定贈与財産を除きます。)の価額(当該財産に係る贈与の時における価額)を相続税の課税価格に加算します(相法19、相基通19-1)。 |
| 相続財産に関する費用 |
相続財産に関する費用(民法第885条に規定する相続財産の中から支弁する相続財産に関する費用)は、債務控除できません(相基通13-2)。 |
| 相続時精算課税適用財産 |
相続時精算課税の制度を適用した贈与財産の価額は、相続時精算課税に係る贈与者である父母又は祖父母が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額に加算するとともに、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して計算します(相法21の15)。 |
| 相続登記費用 |
相続した不動産を登記するために支出した相続登記費用は、相続開始後に発生する費用であり、被相続人に係る費用ではなく相続人が負担すべき費用ですので債務控除の対象とはなりません。 |
| 相当地代に満たない地代を支払っている貸宅地 |
相当地代に満たない地代を支払っている場合の貸宅地の価額は、自用地としての価額から「相当の地代に満たない地代を支払っている場合の借地権の評価」を控除した金額(地代調整貸宅地価額)によって評価します。ただし、その金額が自用地価額の80%を超える場合は、80%に相当する金額によって評価します(課資2-58(例規)直評7)。 |
| 相当地代に満たない地代を支払っている借地権 |
相当地代に満たない地代を支払っている場合の借地権の価額は、原則として、次に定める算式に準じて計算した金額によって評価します(課資2-58(例規)直評4)。
自用地価額 ×{ 借地権割合 ×( 1 - |
| 相当地代を支払っている借地権 |
相当の地代を支払っている場合の当該土地に係る借地権の価額は、①権利金等を供与していない場合は借地権の価値はないものとして評価しません。② ①以外の場合は「相当の地代に満たない地代を支払って土地の借受けがあった場合」に準じて評価します(課資2-58(例規)直評3)。 |
| 相当地代を収受している貸宅地 |
相当の地代を収受している貸宅地の価額は、①権利金等を収受していない場合は自用地価額の80%に相当する金額により評価し、② ①以外の場合は自用地価額から「相当の地代を支払っている場合の借地権の評価額」を控除した金額により評価します(課資2-58(例規)直評6)。 |
| 側方路線に一部接している宅地 |
評価する宅地の一部分のみが側方路線に接している場合には、土地価格に影響を及ぼすのは、その側方路線に直接面している部分であるので、側方路線影響加算額を調整の上、評価します。 |
| 訴訟中の権利 |
訴訟中の権利の価額は、課税時期の現況により係争関係の真相を調査し、訴訟進行の状況をも参酌して原告と被告との主張を公平に判断して適正に評価することとされています(評基通210)。なお、勝訴の可能性が高い場合、訴訟物や訴訟額から勝訴した場合の弁護士報酬額等を控除した金額により評価するものと考えられます。 |
| 損害賠償金債権 |
被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は相続税の対象とはなりません。この損害賠償金は遺族の所得になりますが、非課税規定により所得税も課税されません(昭和57年5月17日直資2-178)。なお、被相続人が損害賠償金を受け取ることに生存中決まっていたが、受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利、すなわち債権が相続財産となります。 |
| 損害賠償金債務 |
損害を与えた原因が被相続人の行為に基づくものであれば、相続人は、責任を相続により承継することになります(民法896)ので、相手に支払うべき損害賠償金は被相続人の債務に該当します。 |
| 損害保険の解約返戻金 |
損害保険契約である定期金給付契約に関する権利を取得した時において、その契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金や前納保険料が相続財産となります。 |
| 存続期間の定めのない永小作権 |
存続期間の定めのない永小作権の価額は、存続期間を30年(別段の慣習があるときは、それによる。)とみなし、その目的となっている農地の価額に「地上権及び永小作権の評価」(相法23)割合(40%)を乗じて算出した金額によって評価します(評基通43)。 農地の価額 × 40%(存続期間30年とする永小作権の割合) |
| 田 |
田や畑などの農地は、①純農地、中間農地は固定資産税評価額に国税局長の定める倍率を乗じて評価し、②市街地農地は宅地であるとした場合の価額から国税局長の定める造成費を控除した金額によって評価し、③市街地周辺農地は、②で評価した金額の80%で評価します(評基通34他)。 |
| 第1種農地 |
第1種農地は、原則として純農地に分類され、その農地の固定資産税評価額に、田又は畑の別に、国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価します(評基通34、37)。 第1種農地 = 固定資産税評価額 × 国税局長の定める田畑の倍率 |
| 大規模工場用地 |
大規模工場用地(5万㎡以上のもの)の価額は、①路線価地域に所在するもの、②倍率地域に所在するものの区分に従い、次の算式により評価します。ただし、その地積が20万㎡以上のものの価額は、次により計算した価額の95%に相当する価額によって評価します(評基通22)。
|
| 第3種農地 |
第3種農地は、原則として市街地周辺農地に分類され、市街地農地であるとした場合の価額の80%に相当する金額によって評価します(評基通34、39)。 第3種農地 = 市街地農地の価額 × 80% |
| 代償財産 |
代償財産の価額は、代償分割の対象となった財産を現物で取得した者が他の共同相続人又は包括受遺者に対して負担した債務(代償債務)の額の相続開始の時における金額によります。ただし、次の算式に準じる合理的な方法によることもできます(相基通11の2-9、10)。 代償債務の額 × 代償財産の相続開始時の評価額 ÷ 代償財産の時価 |
| 退職金 |
退職手当金等で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定(支給額が確定していないものを除きます。)したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となります(相法3二、相基通3-30、3-31)。なお、相続人(相続放棄者や相続権を失った者を除きます。)が受け取った退職手当金等には非課税限度額(500万円×法定相続人の数)があります(相令1の3)。 |
| 退職金を支給した場合 |
被相続人の死亡によって事業を廃止して被相続人が雇用していた従業員を解雇する場合において、その者に退職金を支払っているときは、その支給された退職金は、被相続人の生前事業を営む期間中の労務の対価であり、被相続人の債務として確実なものであると認められますから、その金額を債務控除することができます。 |
| 退職手当金等を定期金として受給した場合 |
被相続人の退職手当金等を定期金として受給した場合は、契約に基づかない定期金に関する権利に該当せず、退職手当金等として課税されます(相法3①二、六、相基通3-47)。なお、相続人(相続放棄者や相続権を失った者を除く)が受け取った退職手当金等には非課税限度額 (500万円×法定相続人の数)があります(相令1の3)。 |
| 退職年金の継続受取人が取得する権利 |
退職年金を受けている者の死亡により、その相続人その他の者が当該年金を継続して受けることとなった場合(これに係る一時金を受けることとなった場合を含みます。)においては、当該年金の受給に関する権利は、その継続受取人となった者が相続又は遺贈により取得したものとみなされ、定期金の評価に基づき評価します(相法3①六、24、相基通3-29)。 |
| 第2種農地 |
第2種農地は、原則として中間農地に分類され、その農地の固定資産税評価額に、田又は畑の別に、国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価します(評基通34、38)。 第2種農地 = 固定資産税評価額 × 国税局長の定める田畑の倍率 |
| 太陽光発電敷地 |
太陽光発電敷地の価額は、①自己の居住用家屋の上に太陽光発電設備を設置している場合は自用地評価し、②賃貸アパートの家屋の屋根の上に太陽光発電設備を設置している場合は太陽光発電設備による電力を賃貸アパートに使用せず、自ら使用するか又は一部を売電している場合でも、全体を「貸家建付地」として評価しても差し支えないものと考えられます。 |
| 太陽光発電設備 |
屋根に設置する太陽光発電設備(太陽光パネル)の価額は、財産評価基本通達に定める「一般動産」として評価します。償却費の額を計算する場合における耐用年数は、耐用年数省令別表第二「31電気業用設備」「その他の設備」「主として金属製のもの」17年で計算します。 |
| 宅地 |
宅地の評価は、原則として、その所在する地域について国税庁が定めた評価方法である①路線価方式(市街地的形態を形成する地域にある宅地)②倍率方式(路線価方式以外の宅地)によって評価します(評基通11)。 |
| 宅地比準方式 |
宅地比準方式とは、その農地等が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額からその農地等を宅地に転用する場合にかかる通常必要と認められる1㎡当たりの造成費に相当する金額を控除した金額に、その農地等の地積を乗じて計算した金額により評価する方法をいいます。 ( 農地等が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額 - 1㎡当たりの造成費) × 地積 |
| 他社株転換 可能債 |
他社株転換可能債(EB債)とは、デリバティブにより株価や為替などの変動リスクを背負うことにより、大きな利回りのリターンを得られるもので、その仕組債の内容(ノックイン又はノックアウト価格やその時の償還資産、残存期間など)により評価方法は異なります。 |
| 多数の路線に接する宅地 |
多数の路線に接する宅地の価額は、各路線が正面路線に対し側方路線としての効用を果たすのか、裏面路線としての効用を果たすのかを個々に検討し、それぞれの路線価にその適用すべき側方路線影響加算率又は二方路線影響加算率を乗じた金額を基に評価します。 |
| 建物 |
建物の価額は、その建物の固定資産税評価額(地方税法第381条の規定により家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登録された基準年度の価格又は比準価格)に財産評価基本通達「別表1」に定める倍率1.0を乗じて計算した金額によって評価します(評基通89)。 固定資産税評価額 × 財産評価基本通達の倍率(1.0) |
| 建物更生共済に関する権利 |
建物更生共済契約は、積立型の損害保険で、共済契約者について相続が開始した場合には、共済契約者の相続人に契約が承継されることから、建物更生共済契約に関する権利が相続税の課税対象となり、その評価額は、相続開始時における解約返戻金相当額となります。 |
| 建物譲渡特約付借地権 |
建物譲渡特約付借地権の価額は、定期借地権等に分類され原則として、課税時期において借地人に帰属する経済的利益及びその存続期間を基として評定した価額によって評価します。ただし、課税上弊害がない場合に限り、その定期借地権等の目的となっている宅地の課税時期における自用地としての価額に、一定の算式により計算した数値を乗じて評価することができます(評基通27-2)。 |
| 建物附属設備 |
建物附属設備等は、①家屋と構造上一体となっている設備はその家屋の価額に含めて評価、②門、塀等の設備の価額は、その附属設備の再建築価額から、建築の時から課税時期までの期間の償却費の額を控除した金額の70%に相当する金額によって評価、③庭園設備の価額は、その庭園設備の調達価額の70%に相当する価額によって評価します(評基通92)。 |
| 棚卸資産 |
棚卸資産は、①商品、②原材料、③半製品及び仕掛品、④製品及び生産品の区分により評価し、原則として、販売価額から、適正利潤の額、予定経費の額及びその商品につき納付すべき消費税額を控除した金額によって評価します。ただし、個々の価額を算定し難い場合は、所得税の計算上選定している方法によることができます(評基通133)。 |
| 頼母子 |
頼母子(複数の個人や法人等が講等の組織に加盟して、金品を定期又は不定期に講等に対して払い込み、利息の額で競合う競りや抽選によって金品の給付を受ける権利)の価額は、課税時期までの掛金総額によって評価します(評基通207)。 |
| タワーマンション |
居住用超高層建築物(タワーマンション)の評価は、原則として、通常の分譲マンションの評価と同様ですが、通達に基づく評価額が著しく不適当と認められる場合(市場価格との乖離率の幅、個別的な要素も考慮)は、国税庁長官の指示を受けて評価することになっています(評基通6)。なお、令和6年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した特定の要件を満たす居住用の区分所有財産(分譲マンション)の価額については、「居住用の区分所有財産の評価について」(法令解釈通達)により評価します。 |
| 単位型投信 |
単位型投資信託(ユニット型投資信託)とは、最初の募集期間にしか購入することができない投資信託のことで、課税時期において解約請求等により、証券会社等から支払いを受けることができる価額として次の算式により計算した金額によって評価します(評基通199⑵)。 基準価額 × 口数 - 源泉徴収されるべき金額 - 信託財産留保額及び解約手数料 |
| 団体信用保険の住宅ローン |
団体信用保険の付された住宅ローンは、債務者の死亡により保険金でその債務が補填されることになるため、債務控除の対象とはなりません。 |
| 地役権 |
区分地上権に準ずる地役権は、その承役地である自用地としての価額に、その地役権の設定契約の内容に応じた土地利用制限率を基とした次の割合を乗じて評価します(評基通27-5)。
|
| 遅延利息 |
生命保険金の支払いが遅れたことに伴い発生する遅延利息は、生命保険金とともに支払われますが、受取人に対する遅延損害金であり、相続財産に含まれません。遅延利息は、受け取った相続人等の雑所得となります(相基通3-8)。 |
| 地下鉄のトンネルが通っている土地 |
地下鉄のトンネルの所有を目的とする区分地上権が設定されている宅地の価額は、その宅地の自用地としての価額から、区分地上権の価額を控除した金額によって評価します。なお、地下鉄等のずい道の所有を目的として設定した区分地上権を評価するときにおける区分地上権の割合は、30%とすることができます(評基通25⑷、27-4)。 宅地の自用地評価額 - 宅地の自用地評価額 × 30% |
| 池沼 |
池沼の価額は、「評価単位」(評基通7-2)及び「評価の方式」(評基通57)から「土地の上に存する権利が競合する場合の賃借権又は地上権の評価」(評基通60-4)までの定めを準用して評価します(評基通62)。なお、池沼が路線価地域に所在する場合は、造成費用を控除します。 |
| 地上権 |
地上権とは、「他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利」です(民法265)。地上権(区分地上権を除きます。)の価額は、その残存期間に応じ、その土地の評価額に、相続税法第23条に定める割合を乗じて算出した金額によって評価します(相法23)。 |
| 地積規模の大きな宅地 |
地積規模の大きな宅地とは、面積が広いことで市場性が低下すると見なされ、相続税評価額が減額される宅地です。三大都市圏では500㎡以上、その他地域では1,000㎡以上が目安となり、「規模格差補正率」を乗じて評価します。 路線価 × 奥行価格補正率 × 不整形地補正率など × 規模格差補正率 × 地積 |
| 地方公共団体に寄附した相続財産 |
相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産を申告期限までに国若しくは地方公共団体に贈与をした場合には、相続税の課税価格の計算の基礎に算入しません(措法70①)。 |
| 地方公社債 |
地方公社債の価額は、①金融商品取引所等に上場、②上場していない場合に区分し次の算式により評価します(評基通197~197-5)。
|
| 地方税 |
住民税及び固定資産税等の地方税は、地方税法に賦課期日が1月1日と定められており、地方税法第9条第1項により被相続人に課されるべき地方税を納める義務を承継することになっていることから、承継した相続人(制限納税義務者は、取得した財産でこの法律の施行地にあるものについて負担した公租公課に限ります。)又は包括受遺者は債務控除できます(相法13①一、14①)。 |
| 中間原野 |
中間原野の価額は、その原野の固定資産税評価額に、地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある原野の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価します(評基通58-2)。 固定資産税評価額 × 国税局長の定める原野の倍率 |
| 中間山林 |
中間山林の価額は、その山林の固定資産税評価額に、地価事情の類似する地域ごとに、売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率(評価倍率表には例えば「中28」のように記載されています。)を乗じて計算した金額によって評価します(評基通48)。 固定資産税評価額 × 国税局長の定める山林の倍率 |
| 中間農地 |
中間農地の価額は、その農地の固定資産税評価額に、田又は畑の別に、地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある農地の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価します(評基通36-2、38)。 固定資産税評価額 × 国税局長の定める田畑の倍率 |
| 中期国債ファンド |
中期国債ファンドの価額は、課税時期において解約請求等により、証券会社等から支払いを受けることができる価額で評価します(評基通199⑴)。 |
| 駐車場 |
駐車場の価額は、①一般的な駐車場として契約している場合には、自用地価額により評価、②車庫などの施設を駐車場の利用者の費用で造ることを認めるような契約の場合には、その土地の自用地価額から賃借権の価額を控除した金額によって評価します(評基通82、86、87)。 |
| 中小企業退職金共済制度(中退共)の遺族が受領する年金又は一時金 |
被共済者の死亡退職により、独立行政法人勤労者退職共済機構から遺族に支払われる一時金は、相続税法3条1項2号(退職手当金)に該当し(相令1の3九)、退職年金を分割払の方法により支給を受けていた被共済者の死亡により、遺族に支払われる支給期月末到来分につき一括繰上支給される一時金は、相続税法3条1項6号(契約に基づかない定期金に関する権利)に該当します。(相基通3-29) |
| 弔慰金 |
弔慰金は、①業務上の死亡であるとき、②業務上の死亡でないときに区分し、下記の金額の範囲内であれば課税財産となりませんが、当該金額を超える部分の金額は退職手当金等に該当するものとされます(相法3、相基通3-20)。
|
| 長期国債 |
長期国債(償還期間が5年超10年以下の国債)の価額は、①金融商品取引所等に上場、②上場していない場合に区分し次の算式により評価します(評基通197~197-5)。 ① 課税時期の最終価格 + 既経過利息の額(源泉税控除後)② 公社債の発行価額 + 既経過利息の額(源泉税控除後) |
| 長期平準定期保険金(契約に関する権利) |
長期平準定期保険(保険満了時の被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、加入時の被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が105を超えるもの)の保険金は、保険事故発生の有無により、①「生命保険金」(相法3、12)又は②「生命保険契約に関する権利の評価」(評基通214)により評価します。 |
| 町内会に寄附(遺贈)した相続財産 |
町内会は、その構成員である町又は字の区域その他市町村内の一定の区域内に住所を有する者の利益のために活動するものであることから、相続税法第12条第1項第3号に規定する「公益を目的とする事業を行う者」に該当しません。したがって、相続税法第66条第1項の規定により、町内会に相続税が課税されます(相法12①、66)。 |
| 貯金 |
貯金の価額は、次の算式によって評価します。ただし、定期預金、定期郵便貯金及び定額郵便貯金以外の預貯金については、課税時期の既経過利子の額が少額なものに限り、同時期現在の預入高によって評価することができます(評基通203)。 貯金 = 預入高 + 解約利息の額(源泉税控除後) |
| 著作権 |
著作権の価額は、著作者の別に一括して次の算式によって計算した金額によって評価します。ただし、個々の著作物に係る著作権について評価する場合には、その著作権ごとに次の算式によって計算した金額によって評価します(評基通148)。 著作権 = 年平均印税収入の額 × 0.5 × 課税時期後の印税収入推算年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率 |
| 著作隣接権 |
著作隣接権(俳優、歌手などの実演家、レコード製作者及び放送事業者等を保護するためのもので、著作隣接権の存続期間は、その属する年の翌年から起算して |
| 貯蓄預金 |
貯蓄預金とは、普通預金より金利が高く、定期預金より換金性が高い預金で、次の算式によって評価します。ただし、定期性預貯金以外の既経過利子の額が少額なものに限り、同時期現在の預入高によって評価することができます(評基通203)。 貯蓄預金 = 預入高 + 解約利息の額(源泉税控除後) |
| 追加型投信 |
追加型投信(オープン型投資信託)とは、運用開始後も購入できる投資信託のことで、課税時期において解約請求等により、証券会社等から支払いを受けることができる価額として次の算式により計算した金額によって評価します(評基通199)。 基準価額 × 口数 - 源泉徴収されるべき金額 - 信託財産留保額及び解約手数料 |
| 追加預託金のあるゴルフ会員権 |
名義変更時に追加の預託金を支払うゴルフ会員権には、退会又は譲渡の際に追加預託金の返還を受けられるものと、当初の預託金と一体化してその後の取引価格の中に織り込まれるものがあります。①取引相場のあるゴルフ会員権は次の算式により評価し、②取引相場のないゴルフ会員権はゴルフ会員権の評価額と返還時期に応じた預託金の合計額で評価します(評基通211)。
|
| 追徴金 |
被相続人が刑の言渡しを受け、判決の確定した罰金、追徴金は、相続税の課税価格の計算上、債務控除することができます。 |
| 通院給付金 |
死亡後に支払われた被相続人が受取人の通院給付金は、本来の相続財産であり、非課税規定の適用がありません(相基通3-7)。なお、受取人が被相続人以外である場合は、その者が取得するものであり、相続税の課税財産になりません。 |
| 通常貯金 |
通常貯金は、次の算式によって評価します。ただし、定期性預貯金以外の既経過利子の額が少額なものに限り、同時期現在の預入高によって評価することができます(評基通203)。 通常貯金 = 預入高 + 解約利息の額(源泉税控除後) |
| 通常貯蓄預金 |
通常貯蓄預金(通常貯金よりも有利な利子が付く出し入れ自由な金融商品)は、次の算式によって評価します。ただし、定期性預貯金以外の既経過利子の額が少額なものに限り、同時期現在の預入高によって評価することができます(評基通203)。 通常貯蓄預金 = 預入高 + 解約利息の額(源泉税控除後) |
| 通常の地代を支払っている貸地 |
通常の地代が支払われている場合の貸地の価額については、通常の貸地の評価と同様に自用地価額から借地権価額を控除した金額によって評価します(評基通27、課資2-58(例規)直評(趣旨))。 通常の地代を支払っている貸地 = 自用地価額 - 自用地価額 × 借地権割合 |
| 通常の地代を支払っている借地 |
通常の地代が支払われている場合の借地権の価額については、通常の借地権の評価と同様に自用地価額に借地権割合を乗じた金額によって評価します(評基通27、課資2-58(例規)直評(趣旨))。 通常の地代を支払っている借地 = 自用地価額 × 借地権割合 |
| 通知預金 |
通知預金(7日間据え置いた後、2日前に通知をすれば自由に引き出せる預金)の価額は、次の算式によって評価します。ただし、定期性預貯金以外の既経過利子の額が少額なものに限り、同時期現在の預入高によって評価することができます(評基通203)。 通知預金 = 預入高 + 解約利息の額(源泉税控除後) |
| 積立貯金 |
積立貯金(通常貯金口座から定期的に定額貯金口座に貯蓄する預金)の価額は、次の算式によって評価します。ただし、定期性預貯金以外の既経過利子の額が少額なものに限り、同時期現在の預入高によって評価することができます(評基通203)。 積立貯金 = 預入高 + 解約利息の額(源泉税控除後) |
| 積立利率変動型終身保険金(契約に関する権利) |
積立利率変動型終身保険(市場の金利動向によって積立利率が変動し、積立に対する保険金や解約返戻金が変動する保険)は、保険事故発生の有無により、①「生命保険金」(相法3、12)又は②「生命保険契約に関する権利の評価」(評基通214)により評価します。 |
| 庭園設備 |
庭園設備(庭木、庭石、あずまや、庭池等)の価額は、その庭園設備の調達価額(課税時期においてその財産をその財産の現況により取得する場合の価額)の70%に相当する価額によって評価します(評基通92⑶)。 |
| 低解約返戻金型終身保険金(契約に関する権利) |
低解約返戻金型終身保険(保険料の支払期間中の解約返戻金の返戻率を低く抑えてある終身保険)は、保険事故発生の有無により、①「生命保険金」(相法3、12)又は②「生命保険契約に関する権利の評価」(評基通214)により評価します。 |
| 定額貯金 |
定額貯金の価額は、次の算式によって評価します。ただし、既経過利子の額が少額なものに限り、同時期現在の預入高によって評価することができます(評基通203)。 定額貯金 = 預入高 + 解約利息の額(源泉税控除後) |
| 定期金(定期金に関する権利) |
定期金に関する権利とは、契約によりある期間定期的に金銭その他の給付を受けることを目的とする債権をいい、権利を取得した時において定期金給付事由が、①発生しているものと、②発生していないものに区分して評価します(相法24、25)。 |
| 定期借地権 |
定期借地権の価額は、原則として、課税時期において借地権者に帰属する経済的利益及びその存続期間を基として評定した価額によって評価します。ただし、課税上弊害(権利金の追加払いがある場合や地価の上昇による自然発生的な差額地代が明確に生じている場合)がない限り、その定期借地権等の目的となっている宅地の自用地としての価額に、一定の算式により計算した数値を乗じて計算した金額によって評価することができます(評基通27-2)。 |
| 定期付終身保険金(契約に関する権利) |
定期付終身保険(終身保険契約に定期保険を特約の形で付加した保険)は、保険事故発生の有無により、①「生命保険金」(相法3、12)又は②「生命保険契約に関する権利の評価」(評基通214)により評価します。なお、相続人(相続放棄者や相続権を失った者を除きます。)が受け取った生命保険金には非課税限度額(500万円×法定相続人の数)があります(相法3、12、15)。 |
| 定期積金 |
定期積金の価額は、課税時期における預入高と解約利息の額から源泉徴収される額を控除した金額との合計額により評価。ただし、課税時期の既経過利子の額が少額なものに限り、同時期現在の預入高によって評価します(評基通203)。 定期積金 = 預入高 + 解約利息の額(源泉税控除後) |
| 定期保険の死亡保険金 |
定期保険(保障期間を契約時に定め、契約終了時に返戻金のない保険)の死亡保険金は、相続財産とみなされます。なお、相続人(相続放棄者や相続権を失った者を除きます。)が受け取った生命保険金には非課税限度額(500万円×法定相続人の数)があります(相法3、12、15)。 |
| 提供公園 |
提供公園(開発面積3000㎡以上の大規模なマンションを建築する際に都市計画法によりマンション側が整備をしなければならない公園)は、自治体に無償提供していますので、相続税の課税財産となりません(非課税財産)。 |
| 定期預金 |
定期預金の評価は、課税時期における預入高と解約利息の額から源泉徴収される額を控除した金額との合計額により評価。ただし、課税時期の既経過利子の額が少額なものに限り、同時期現在の預入高によって評価します(評基通203)。 定期積金 = 預入高 + 解約利息の額(源泉税控除後) |
| 逓減定期保険金(契約に関する権利) |
逓減定期保険(保険料は一定であるが、契約時の保険金が契約期間の年数が経つごとに一定金額まで減少するもの)は、①「生命保険金」(相法3、12)又は②「生命保険契約に関する権利の評価方法」(評基通214)により評価します。なお、相続人(相続放棄者や相続権を失った者を除きます。)が受け取った生命保険金には非課税限度額(500万円×法定相続人の数)があります(相法3、12、15)。 |
| 停止条件付遺贈財産 |
停止条件付遺贈の成就前に相続税の申告書を提出するときは、当該遺贈の目的となった財産については、相続人が民法第900条から第902条まで及び第903条の規定による相続分によって課税価格を計算します。ただし、当該財産の分割があり、その分割がこの割合に従ってされなかった場合においても当該分割により申告することもできます(相基通11の2-8) |
| ディスカウント債 |
ディスカウント債(通常よりも低い利率で、発行価額が額面金額よりも低く設定されており、償還時には額面で償還される債券)は、次の算式によって評価します。ただし、課税時期の予想売却価格が、評価額を下回る場合は、予想売却価格によって評価することができます。 ディスカウント債 = 発行価額 + 既経過償還差益 + 既経過利息(源泉税控除後) |
| 逓増定期保険金(契約に関する権利) |
逓増定期保険(定期保険の一種であり、保険料は変わらずに保障が段階的に増えていくもの)は、「生命保険金」(相法3、12)又は「生命保険契約に関する権利の評価方法」(評基通214)により評価します。なお、相続人(相続放棄者や相続権を失った者を除きます。)が受け取った生命保険金には非課税限度額(500万円×法定相続人の数)があります(相法3、12、15)。 |
| 抵当権が設定されている土地 |
抵当権が設定されている土地については、原則として抵当権が設定されていることを考慮しないで評価します。ただし、課税時期において、債務者が弁済不能の状態にあるため、抵当権が実行されることが確実であり、かつ、債務者に求償しても弁済を受ける見込みがない場合に限り、債務者の弁済不能と認められる部分の金額が債務控除できます(相基通14-3⑴、11の2-1⑶)。 |
| 抵当証券 |
抵当証券(不動産の抵当権付き貸付債権を、小口に証券化した金融商品)は、①金融商品取引業者等の販売するものは、次の算式により評価し、② ①以外の抵当証券は、「貸付金の評価」(評基通204、205)に準じて評価します(評基通212)。 抵当証券 = 元本の額 + 既経過利息(源泉税控除後)- 解約手数料 |
| 庭内神しの敷地 |
庭内神し(屋敷内にある神の社や祠等)敷地は、その建立の経緯・目的、現在の礼拝の態様等も踏まえ、日常礼拝の対象とされている場合には、その敷地及び附属設備は、相続税の非課税財産に該当します。 |
| 鉄道、軌道地 |
鉄道又は軌道の用に供する土地(鉄軌道用地)の価額は、その鉄軌道用地に沿接する土地の価額※の3分の1に相当する金額によって評価します(評基通84)。 鉄道、軌道地 = その鉄軌道用地に沿接する土地の価額※× 1/3
|
| 鉄道の高架下の賃借権 |
建物の所有を目的とする鉄道の高架下の土地の賃借権の価額は、その賃借権の目的となっている宅地の自用地評価額にその設定契約の内容に応じた土地利用制限率を基とした割合(区分地上権の割合)を乗じて評価するものと解されます(評基通25⑷、27-4)。 鉄道の高架下の賃借権 = 宅地の自用地評価額 × 区分地上権の割合 |
| デュアル・カレンシー債 |
デュアル・カレンシー債(元本の払込みと償還が同じ通貨で、利息の支払通貨が異なる債券)は、金融商品取引所等に、①上場しているもの、②上場していないものに区分し、次の算式により評価します(評基通197~197-5)。なお、邦貨換算は、対顧客直物電信買相場(TTB)により計算します(評基通4-3)。
|
| 転換社債型新株予約権付社債 |
転換社債型新株予約権付社債(一定価格(転換価格)で株式に転換できる権利の付いた社債)は、①金融商品取引所等に上場しているもの、② ①以外のもので株価が転換価格を超えるもの、③ ②以外のものに区分し、次の算式により評価します(評基通197-5)。
|
| 電気設備 |
電気設備(棚卸資産を除きます。)は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。ただし、売買実例価額等が明らかでない場合は、同種及び同規格の新品の小売価額から、取得時期から課税時期までの償却費の額を控除した金額によって評価します。なお、家屋と構造上一体となっている設備については、その家屋の価額に含めて評価します(評基通92、128~130)。 |
| 電子マネー |
電子マネーのうち、①前払い式(プリペイドタイプ)のもの(SuicaやICOCAなどの交通系、nanacoや楽天Edy、WAONなどの流通系、PayPayやau PAY、LINE PAY)は、チャージ残高が相続財産となり、②後払い式(ポストペイタイプ)のもの(QUICPay、iDなど)は、相続開始後に支払期日が到来するものが債務控除の対象になります。 |
| 転借権 |
転借権(借地権の目的となっている宅地の転借権)の価額は、次の①の算式により評価し、その転借権が貸家の敷地の用に供されている場合は、②の算式によって評価します(評基通30)。
|
| 転貸借地権 |
転貸借地権(他から借り受けている宅地を自己の用に供することなく、他に転貸している場合の借地権)の価額は、次の算式によって評価します(評基通29)。 転貸借地権 = 借地権の価額 - 転借権の価額 |
| 店頭FX |
相続開始日で未決済の取引がある場合は、その日の最終価格で決済した場合の差益金額が相続財産となります。課税時期において差益金額が利益である場合は相続財産となり、損失である場合は債務控除できます。なお、差し入れてある証拠金は相続財産(預け金)となります。 |
| 伝統的建造物 |
伝統的建造物である家屋の価額は、当該家屋の固定資産税評価額の70%で評価します。なお、固定資産税評価額が付されていない場合には、その文化財建造物の再建築価額から、経過年数に応ずる減価の額を控除した価額の70%に相当する金額で評価します(評基通89-2)。 |
| 伝統的建造物の敷地 |
伝統的建造物の敷地は、それが重要文化財建造物の敷地でないものとした場合の価額の70%で評価します。なお、倍率地域で固定資産税評価額が付されていない場合には、その宅地と状況が類似する付近の宅地の固定資産税評価額を基とし評価します(評基通24-8)。 |
| 電話加入権 |
電話加入権の評価は、売買事例、精通者意見等を参酌して評価することになります(評基通161)。なお、相続税等の申告に当たっては、一般動産についての財産評価基本通達128《評価単位》の定めに基づき、一括して評価する家庭用財産等に電話加入権を含めることとして差し支えありません。 |
| 同族株式 |
株式を取得した株主が、その会社の経営支配力を有している株主(同族株主等)かそれ以外の株主かの区分により、それぞれ、類似業種比準方式、純資産価額方式若しくはその併用方式による原則的評価方式か、特例的な評価方式の配当還元方式により評価します。また、資産保有状況、営業の状態が一般の会社と異なると認められる特定の会社は、特定の評価会社の株式として純資産価額方式を基本として評価します。 |
| 登録美術品 |
「登録美術品」とは、重要文化財や国宝,その他,世界的に優れた美術品について国が登録したものをいいます。登録美術品については、相続人からの申請により文化庁長官がその登録美術品の価格を評価します。なお、登録美術品については、第一順位の物納財産として許可を受けることができます(相法41②、措法70の12①)。また、美術館等に寄託していた一定の要件を満たす特定美術品で、相続人が寄託先美術館への寄託を継続するときは、その特定美術品に係る評価額の80%に対応する相続税の納税が猶予されます(措法70の6の7)。 |
| 登録有形文化財建造物 |
登録有形文化財建造物である家屋の価額は、当該家屋の固定資産税評価額の70%で評価します。なお、固定資産税評価額が付されていない場合には、その文化財建造物の再建築価額から、経過年数に応ずる減価の額を控除した価額の70%に相当する金額で評価します(評基通24-8、89-2)。 |
| 登録有形文化財建造物の敷地 |
登録有形文化財建造物の敷地は、それが重要文化財建造物の敷地でないものとした場合の価額の70%で評価します。なお、倍率地域で固定資産税評価額が付されていない場合には、その宅地と状況が類似する付近の宅地の固定資産税評価額を基とし評価します(評基通24-8)。 |
| 道路との高低差がある宅地 |
道路より高い位置にある宅地又は低い位置にある宅地で、同一路線価の土地に比べ利用価値が低下していると認められる部分の面積に対応する部分の価額に10%を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価することができます。 宅地の価額 - 利用価値が低下していると認められる部分の面積に対応する価額 × 10% |
| 特定公益信託に支出した金銭 |
相続や遺贈で取得した財産(生命保険金や退職手当金も含まれます。)を特定の公益信託の信託財産とするために申告期限までに支出した場合は、その支出した金銭は相続税の対象とはなりません(措法70③)。 |
| 特定疾病保障保険金(契約に関する権利) |
特定疾病保障保険(生存中に保険金が受け取れる保険)は、「生命保険金」(相法3、12)又は「生命保険契約に関する権利の評価方法」(評基通214)により評価します。なお、相続人(相続放棄者や相続権を失った者を除く)が受け取った死亡保険金には非課税限度額(500万円×法定相続人の数)があります(相法3、12、15)。また、生前に支払われる「特定疾病保険金」は、非課税所得となります(所基通9-21)。 |
| 特定市民農園の用地 |
特定市民農園の用地として貸し付けられている土地の価額は、その土地が特定市民農園の用地として貸し付けられていないものとして評価した価額から、その価額に30%を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価します。 |
| 特定退職金共済制度の遺族が受領する年金又は一時金 |
各特定退職金共済団体の退職金共済規定により若干異なりますが、公益社団法人東法連特定退職金共済会における制度は次のとおりです。被共済者の死亡退職により遺族に支払われる一時金は、相続税法3条1項2号(退職手当金)に該当し(相令1の3九)、退職年金を分割払の方法により支給を受けていた被共済者の死亡により、遺族に支払われる支給期月末到来分につき一括繰上支給される一時金は、相続税法3条1項6号(契約に基づかない定期金に関する権利)に該当します。(相基通3-29) |
| 特定非常災害により被災した土地等 |
特定非常災害発生日の属する年末までの間に相続等により取得した特定非常災害により被災した特定地域内にある土地等の価額は、路線価及び倍率に「国税局長が特定地域内の一定の地域ごとに定めた調整率」を乗じて評価することができます(特定非常災害発生日以後に相続等により取得した財産の評価について(法令解釈通達))。 |
| 特別縁故者が取得した財産 |
特別縁故者(相続人がいない場合に家庭裁判所から相続財産の分与を受けた者)が相続財産の分与を受けた場合、①申告期限は分与を受けた日から10か月以内で、②財産の評価時点は分与時の相続税評価額に基づいて評価し、③基礎控除額(平成27年以降は3,000万円)及び相続税額の計算等は相続開始日の法令によります(相法4、民法958の3)。なお、④相続税額の2割加算が適用され、⑤小規模宅地等の特例の適用はできません。 |
| 特別寄与料 |
特別寄与者(相続人以外の親族)が支払いを受けるべき特別寄与料の額(民法1050)については、分与を受けた金額又は特別寄与料の額から、葬式費用又は療養看護のための入院費用等の金額を控除した価額をもって、当該分与された価額又は特別寄与料の額とします(相基通4-3)。なお、特別寄与料を支払った相続人はその金額を債務控除します(相法13)。 |
| 特別弔慰金等を元の勤務先から受けた場合 |
元の勤務先から支給された特別弔慰金等は、雇用者以外の者から支払われるもので被相続人の生前の役務の対価とはいえませんから、その特別弔慰金は相続税法第3条第1項第2号に規定する退職手当金等に該当しません。遺族の一時所得となります。 |
| 特別夫婦年金保険 |
年金支払開始年齢に達する前に保険契約者が死亡した場合には、被保険者が保険契約者から生命保険契約に関する権利(いわゆる本来の相続財産)を相続しますので相続税の課税対象となります。 |
| 特別緑地保全区域内の原野 |
特別緑地保全区域内にある原野の価額は、原野の評価額から、その価額に80%を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価します(評基通50-5)。 原野の評価額 - 原野の評価額 × 80% |
| 特別緑地保全区域内の山林 |
都市緑地法第12条に規定する特別緑地保全地区内にある山林(林業を営むために立木の伐採が認められる山林で、純山林に該当するものを除きます。)の価額は、次の算式①によって評価します(評基通50-2)。なお、管理協定が締結されている山林については、次の算式②によって評価します。
|
| 匿名組合契約に係る権利 |
匿名組合とは、当事者の一方(匿名組合員)が、相手方(営業者)のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約する契約をいいます。匿名組合員の有する財産は、利益配当請求権と匿名組合契約終了時における出資金返還請求権が一体となった債権的権利であり、その価額は、営業者が匿名組合契約に基づき管理している全ての財産・債務を対象として、課税時期において、その匿名組合契約が終了したものとした場合に、匿名組合員が分配を受けることができる清算金の額に相当する金額により評価します。 |
| 都市計画道路予定の区域内にある宅地 |
都市計画道路予定地の区域内となる部分を有する宅地の価額は、都市計画道路予定地でないものとした場合の価額に、地区区分、容積率、地積割合の別に応じて財産評価基本通達で定める補正率を乗じて計算した価額によって評価します(評基通24-7)。 都市計画道路予定地でないものとした場合の価額 × 財産評価基本通達で定める補正率 |
| 都市公園の用地 |
都市公園の用地として貸し付けられている土地の価額は、その土地が都市公園の用地として貸し付けられていないものとして評価した価額から、その価額に40%を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価します(平成4年4月22日「都市公園の用地として貸し付けられている土地の評価について」) 都市公園の用地 = その土地の評価額 - その土地の評価額 × 40% |
| 土砂災害特別警戒区域内にある宅地 |
土砂災害特別警戒区域内となる部分を有する宅地の価額は、土砂災害特別警戒区域内でないものとした場合の価額に、その宅地の総地積に対する土砂災害特別警戒区域内となる部分の地積の割合に応じて付表9「特別警戒区域補正率表」に定める補正率を乗じて評価します(評基通20-6)。 土砂災害特別警戒区域内でないものとした場合の価額 × 特別警戒区域補正率 |
| 土壌汚染地 |
土壌汚染地の評価額は、その土地の評価した価額から、浄化・改善費用の80%相当額や使用制限による減価、心理要因による減価などを控除して計算するものと考えられます(令和6年6月21日「土壌汚染地等の評価の考え方について(情報)」)。 その土地の評価額 - 浄化・改善費用 × 80% -(その他の減価要因) |
| 土地区画整理事業施行中の宅地の評価 |
仮換地が指定されている宅地の価額は、①その仮換地の価額(清算金が徴収されるものは減算し、交付されるものは加算)によって評価します。ただし、当該工事が完了するまでの期間が1年を超えると見込まれる場合は、その仮換地の価額の95%で評価します。②仮換地の造成工事前で、仮換地について使用収益ができないときには、従前の宅地の価額により評価します(評基通24-2)。なお、仮換地が指定されていない宅地は、従前の宅地の価額により評価します。
|
| 土地保有特定会社の株式 |
土地保有特定会社の株式の価額は、①同族株主が取得した株式は純資産価額方式によって評価します。また、議決権割合が50%以下の同族株主グループは、その金額に80%を乗じて計算した金額とします(評基通189-4)。なお、②同族株主以外の株主等が取得した株式は、配当還元方式により計算した金額又は純資産価額方式によって評価します。 |
| 読経料 |
相続人(無制限納税義務者)又は包括受遺者が支出した読経料は、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるものであり葬式費用として債務控除できます(相基通13-4)。 |
| 特許権 |
特許権の価額は、権利者が自ら特許発明を実施している場合を除き、その権利に基づき将来受ける補償金の額の基準年利率による複利現価の額の合計額によって評価します(50万円に満たない場合は評価しません。)。なお、特許権者が自ら特許発明を実施している場合の特許権はその者の営業権の価額に含めて評価します(評基通140~145)。 |
| TOPIXオプション |
TOPIXオプション(東証株価指数(TOPIX)を対象原資産とする株価指数のオプション取引)は、オプションの買い手は課税時期の市場のオプション価格が相続財産となり、オプションの売り手は引受価格(オプション料)から課税時期の市場のオプション価格を差し引いた金額が相続財産又は債務となります。 |
| 鳥 |
鳥の価額は、①販売業者が販売の目的をもって有するものは、「たな卸商品等の評価」(評基通133)によって評価し、②それ以外のものは、売買実例価額(ネットなどの取引情報など)、精通者意見価格等を参酌して評価します(評基通134)。 |
| 取引相場のない株式 |
取引相場のない株式は、相続や贈与などで株式を取得した株主が、その株式発行会社の経営支配力を有している株主(同族株主等)かそれ以外の株主かの区分により、それぞれ類似業種比準方式、純資産価額方式若しくはその併用方式による原則的評価方式か特例的な評価方式の配当還元方式により評価します(評基通178)。 |
| 取引相場のないゴルフ会員権 |
取引相場のないゴルフ会員権は、次の区分に応じて評価します(評基通211)。
|
| 2項道路に面する土地 |
建築基準法第42条第2項に規定する道路に面しており、将来、建物の建替え時等に同法の規定に基づき道路敷きとして提供しなければならない部分を有する宅地の価額は、次の算式により計算した金額によって評価します(評基通24-6)。
宅地の評価額 - 宅地の評価額 × |
| 日経225オプション |
日経225オプション(日経平均株価を対象原資とするオプション取引)は、オプションの買い手は課税時期の市場のオプション価格が相続財産となり、オプションの売り手は引受価格(オプション料)から課税時期の市場のオプション価格を差し引いた金額が相続財産又は債務となります。 |
| 入院給付金 |
死亡後に支払われた被相続人が受取人の入院給付金は、本来の相続財産であり、非課税規定の適用がありません(相基通3-7)。なお、受取人が被相続人以外である場合は、その者が取得するものであり、相続税の課税財産になりません。 |
| 庭木、庭石、庭池 |
庭木、庭石等(庭木設備)の価額は、その庭園設備の調達価額(課税時期においてその財産をその財産の現況により取得する場合の価額)の70%に相当する価額によって評価します(評基通92⑶) |
| 認定事業計画に基づき貸し付けられている農地 |
認定事業計画(都市農地の貸借の円滑化に関する法律4)に従って賃借権が設定されている農地の価額は、その農地の自用地としての価額から、その価額に5%を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価します。 認定事業計画貸付農地 = 農地の自用地価額 - 農地の自用地価額 × 5% |
| 猫 |
猫の価額は、①販売業者が販売の目的をもって有するものは、「たな卸商品等の評価」(評基通133)によって評価し、②それ以外のものは、売買実例価額(ネットなどの取引情報など)、精通者意見価格等を参酌して評価します(評基通134)。 |
| 年金払いで受ける死亡退職金 |
年金払いで受ける死亡退職金の価額は、相続税法第24条の定期金の評価規定に基づき解約返戻金相当額などの金額で評価します(相法24①)。 |
| 農業協同組合の出資金 |
農業協同組合のように、その組合の行う事業によって、その組合員及び会員のために最大の奉仕をすることを目的とし、営利を目的として事業を行わない組合等に対する出資金は、払済出資金額によって評価します(評基通195)。 |
| 農業振興地域内の農地 |
農業振興地域内の農地は、①農用地区域内のものは「純農地の評価」(評基通36)によって評価し、②農用地区域外のものは農地法の分類(甲種農地、第1種農地から第3種農地)に従い評価します(評基通34)。 |
| 農業用施設用地 |
農業用施設用地の価額は、①農用地区域内又は市街化調整区域内に存する場合、その宅地が農地であるとした場合の1㎡当たりの価額に、宅地とする場合に通常必要と認められる1㎡当たりの造成費を加算した金額に、地積を乗じて評価し、②農用地区域内等以外の地域に存する場合、通常の宅地又は雑種地の評価方法により評価します(評基通24-5)。 ① (農地であるとした場合の1㎡当たりの価額 + 1㎡当たりの造成費 ) × 地積 ② 通常の宅地又は雑種地の評価 |
| 農用地利用増進法等による賃借権により貸付けられた農用地等 |
農用地利用増進法の農用地利用増進計画によって設定された賃貸借に基づき貸し付けられている農用地の価額は、その農用地が貸し付けられていないものとして評価した価額から、その価額に5%を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価します(昭和56年6月9日「農用地利用増進法等の規定により設定された賃貸借により貸付けられた農用地等の評価について」)。 |
| 納骨費用 |
相続人(無制限納税義務者)又は包括受遺者が支出した納骨費用は、葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において要する費用であり、葬式費用として債務控除できます(相基通13-4)。 |
| 農地 |
農地は、次の分類によりそれぞれ評価します(評基通36、36-2、37、38)。
|
| 農地中間管理機構に賃貸借により貸し付けられている農地 |
農地中間管理事業の推進に関する法律に規定する農地中間管理機構に賃貸している農地(農地法第3条第1項第14号の2の規定に基づき農地中間管理機構に貸し付けられている農地のうち、賃貸借期間が10年未満のものを除きます。)の価額は、次の算式により評価します(評基通41)。 農地中間管理機構に貸し付けられている農地 = 農地の自用地価額 × 95% |
| 農用地利用集積計画により賃借権が設定されている農地 |
農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の公告により賃借権が設定されている農地の価額は、その農地の自用地としての価額からその価額に5%を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価します。 農用地利用集積計画により賃借権が設定されている農地 = 農地の自用地価額 × 95% |
| 配偶者居住権 |
配偶者居住権の価額は、次の算式により評価します(相法23の2)。↓リンク挿入 敷地利用権(居住建物の敷地を配偶者居住権に基づき使用する権利)
居住建物の相続税評価額 - 居住建物の相続税評価額 × |
| 配偶者居住権の敷地利用権 |
配偶者居住権の敷地利用権の価額は、次の算式により評価します(相法23の2)。 居住建物の敷地の用に供される土地の相続税評価額 - 居住建物の敷地の用に供される土地の相続税評価額 × 存続年数に応じた法定利率による複利現価率 |
| 配偶者短期居住権 |
配偶者短期居住権とは、亡くなった人の所有する建物に、残された配偶者が一定期間無償で居住できる権利です。配偶者短期居住権は、財産評価額は0円(相続税申告の対象外)となります。 |
| 配当期待権 |
配当期待権(配当交付基準日の翌日から、配当金交付の効力が発生する日までの間における配当金の交付を受けることができる権利)の価額は、次の算式により評価します(評基通193)。 配当期待権 = 予想配当金額 - その配当から控除される源泉税額等 |
| 配当優先の無議決権株式 |
配当優先の無議決権株式の価額は、①類似業種比準方式で評価する場合は、1株当たりの配当金額について、株式の種類ごとに計算して評価、②配当還元方式は、株式の種類ごとに実際の配当金により評価します。なお、無議決権株式については、原則として、議決権の有無を考慮せずに評価することとなりますが、一定の要件に該当し、相続人から相続税の法定申告期限までに調整計算の選択届出書が提出された場合は、その計算により評価することができます。 |
| 売買契約中の土地 |
売買契約中の土地について、①売主に相続が開始した場合は、土地の所有権が売主に残っているとしても、課税財産となるのは売買残代金債権となります。②買主に相続が開始した場合は、相続税の課税財産に含まれるものは、土地の所有権移転請求権等の債権的権利であり、売買契約における売買価額となり、未払代金が債務となります。平成14年7月「資産税審理事例集」 |
| 畑 |
田や畑などの農地の価額は、次の分類によりそれぞれ評価します(評基通34他)。
|
| 罰金 |
被相続人が刑の言渡しを受け、判決の確定した罰金、追徴金は、相続税の課税価格の計算上、債務控除することができます。 |
| 花輪や生花の費用 |
相続人(無制限納税義務者)又は包括受遺者が葬儀の際に支払った花輪や生花の費用は、通常葬式に伴うものと認められる範囲内のものは、葬式費用として債務控除できます(相基通13-4)。なお、参列者の負担すべきものを支払った場合を除きます。 |
| パラジウム |
パラジウム地金の価額は、一般動産(棚卸資産を除きます。)の評価に準じて、売買実例価額(貴金属業者などの相続開始日の買取価格)等を参酌して評価します(評基通129)。 |
| 半製品 |
半製品の価額は、製造業者がその半製品の原材料を課税時期において購入する場合における仕入価額に、その原材料の引取り、加工等に要する運賃、加工費その他の経費の額を加算した金額によって評価します。ただし、個々の価額を算定し難い場合は、所得税の計算上選定している方法によることができます(評基通133)。 |
| ビール券 |
商品券や旅行券、ギフト券、クオカード、株主優待券などの金券は、相続財産になり、額面金額又は売買実例価額(ネットなどの相続開始日の買取価格)で評価します(相法22) |
| 引揚者国庫債券 |
引揚者国庫債券とは、戦没者などの遺族や強制引揚げを余儀なくされた引揚者などに対して、弔慰金、給付金などの金銭の支給に代えて交付される国債で、古銭などの評価に準じてネット上の取引価額や買取り業者価格を参考として評価するものと考えられます。 |
| 被災した家屋 |
被災家屋の価額は、被災後の現況に応じた固定資産税評価額が付されていない場合には、原則として、特定非常災害の発生直前の家屋の価額から、その被災した家屋に適用された固定資産税の軽減又は免除の割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価することができます(特定非常災害発生日以後に相続等により取得した財産の評価について(法令解釈通達))。 被災前の家屋の固定資産税評価額 - 被災前の家屋の固定資産税評価額 × 軽減又は免除の割合 |
| ヒット |
ヒットは契約締結日に満期日を定めず、据置期間1か月を経過した後は手数料なしで、いつでも自由に必要な額だけ引き出せる金銭信託で、次の算式によって評価します。ただし、既経過利子の額が少額なものに限り、同時期現在の預入高によって評価することができます(評基通203)。 ヒット = 預入高 + 解約利息の額(源泉税控除後) |
| ビットコイン |
仮想通貨の価額は、原則として、納税義務者が取引を行っている仮想通貨交換業者が公表する課税時期における取引価格によって評価します。なお、活発な市場が存在しない仮想通貨の場合には、その仮想通貨の内容や性質、取引実態等を勘案し、個別に評価します(評基通4-3、5)。 |
| 避雷針設備 |
避雷針設備(棚卸資産を除きます。)の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。ただし、売買実例価額等が明らかでない場合は、同種及び同規格の新品の小売価額から、取得時期から課税時期までの償却費の額を控除した金額によって評価します。なお、家屋と構造上一体となっている設備については、その家屋の価額に含めて評価します(評基通92、128~130)。 |
| 風景地保護協定が締結されている土地 |
一定の要件を満たす風景地保護協定が締結されている土地については、風景地保護協定区域内の土地でないものとして評価した価額から、その価額に20%を乗じて計算した金額を控除して評価します。 風景地保護協定区域内の土地でないものとして評価した価額 × 80% |
| 福祉共済保険制度により支払いを受ける死亡共済金 |
福祉共済保険制度により支払いを受ける死亡共済金は、相続税の課税財産とはなりません。なお、死亡共済金が共済契約に基づき、会員の死亡という給付事由が生じたことから、会員の遺族が給付金の支給を請求できるものと認められ、相続人の一時所得に該当するものと認められます。 |
| 袋地 |
通路部分だけが道路に接し、奥の方が広くなっている土地を袋地といいます。その土地の形状から旗竿地ということもあります。袋地の価額は、間口狭小補正率、奥行長大補正率又は不整形率補正率を適用して評価します。 |
| 不合理分割地 |
宅地は、1画地の宅地(利用の単位となっている1区画の宅地をいいます。)を評価単位とします。ただし、贈与、遺産分割等による宅地の分割が親族間等で行われた場合において、例えば、分割後の画地が宅地として通常の用途に供すことができないなど、その分割が著しく不合理であると認められるときは、その分割前の画地を「1区画の宅地」として評価します(評基通7-2)。 |
| 不整形地 |
不整形地の価額は、標準的な整形地の価格である路線価に、評価対象地の不整形の程度に応じ財産評価基本通達に定める「不整形補正率」(付表5)を乗じて評価します(評基通20)。 不整形地 = 路線価 × 不整形補正率 |
| 負担付遺贈財産 |
負担付遺贈により取得した財産の価額は、負担がないものとした場合における当該財産の価額から当該負担額(当該遺贈のあった時において確実と認められる金額に限ります。)を控除した価額によります(相基通11の2-7)。 |
| 負担付遺贈の負担による利益 |
負担付遺贈があった場合において当該負担額が第三者の利益に帰すときは、当該第三者が、当該負担額に相当する金額を、遺贈によって取得したこととなります(相基通9-11)。 |
| 普通預金 |
普通預金の価額は、次の算式によって評価します。ただし、定期預金、定期郵便貯金及び定額郵便貯金以外の預貯金については、課税時期の既経過利子の額が少額なものに限り、同時期現在の預入高によって評価することができます(評基通203)。 普通預金 = 預入高 + 解約利息の額(源泉税控除後) |
| 仏壇、仏具、仏像 |
仏壇等は、相続税法第12条(相続税の非課税財産)第2号の「墓所、霊びょう、及び祭具並びにこれらに準ずるもの」に該当し、相続税の課税価格には算入しません(相法12、相基通12-2)。ただし、金の仏壇、仏具、仏像など、日常崇拝の目的に供されず趣味、観賞用又は投資のために保有されるものについては、非課税財産とはなりません(相基通12-2)。 |
| 不動産所有権付リゾート会員権 |
不動産売買契約(土地及び建物並びに附属施設の共用部分)と施設相互利用契約とが一体として取引される不動産付施設利用権(リゾート会員権)(仲介業者等による取引相場があるもの)は、「取引相場のあるゴルフ会員権の評価方法」(評基通211)に準じて、課税時期における通常の取引価格の70%相当額により評価します。 |
| 不動産投資信託 |
上場不動産投資信託(J-REIT)の価額は、「上場株式の評価」(評基通169)に準じてします。なお、不動産投資信託証券に係る投資口の分割等に伴う無償交付期待権の価額は「株式無償交付期待権の評価」(評基通192)に準じて評価し、金銭分配期待権の価額は「配当期待権の価額」(評基通193)に準じて評価します(評基通213)。 |
| 不特定多数の者の通行の用に供されている私道 |
通り抜けできる私道や行き止まりの私道でもその私道を通行して不特定多数の者が集会所、地域センター及び公園などの公共施設や商店街等に出入りするために利用されているときは、その私道の価額は評価しません(評基通24)。 |
| プラチナ |
プラチナ地金の価額は、一般動産(棚卸資産を除きます。)の評価に準じて、売買実例価額(ネットなどの相続開始日の買取価格)等を参酌して評価します(評基通129)。 |
| プリペイドカード |
プリペイドカードの価額は、課税時期におけるカードの残高により評価します。 |
| プレジャーボート |
プレジャーボート(モーターボート、ヨット等海洋レクリエーションに使用される小型船舶)の価額は、売買実例価額(ネットの取引価格、買取業者の見積額など)、精通者意見価格等を参酌して評価します(評基通136)。 |
| 文化財建造物 |
文化財建造物である家屋の価額は、その固定資産税評価額に文化財建造物の種類に応じた倍率を乗じて計算した金額を控除した金額で評価します。なお、固定資産税評価額が付されていない場合には、その再建築価額から、経過年数に応ずる定額法の減価の額を控除した額の70%に相当する金額によって評価します(評基通89-2、24-8)。 文化財建造物 = 固定資産税評価額 ×( 1 - 倍率※) ※ 重要文化財は0.7、登録有形文化財、伝統的建造物は0.3 |
| 文化財建造物の敷地 |
文化財保護法に規定する家屋の敷地の用に供されている敷地の価額は、その敷地の価額から、その価額に文化財建造物の種類に応じて定める倍率を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価します。なお、倍率方式で評価する場合に固定資産税評価額が付されていない場合は、状況が類似する付近の宅地の固定資産税評価額を基として評価します(評基通24-8)。 文化財建造物の敷地 = 敷地の価額 ×( 1 - 倍率※) 重要文化財は0.7、登録有形文化財、伝統的建造物は0.3 |
| 分収林契約に基づいて貸し付けられている山林 |
立木の伐採又は譲渡による収益を一定の割合により分収することを目的として締結された分収林契約に基づいて設定された地上権又は賃借権の目的となっている山林の価額は、その分収林契約により定められた山林の所有者に係る分収割合に相当する部分の山林の自用地としての価額と、その他の部分の山林について貸し付けられている山林の評価等の定めにより評価した価額との合計額によって評価します(評基通51~52)。 自用地価額 × 分収割合 + ( 自用地価額 - 地上権又は賃借権の価額 ) × ( 1 - 分収割合 ) |
| 米州開発銀行債 |
米州開発銀行債は、金融商品取引所等に上場している場合は、課税時期の最終価格と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価し、上場していない場合は、公社債の発行価額と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価します(評基通197~197-5)。なお、邦貨換算は、対顧客直物電信買相場(TTB)により計算します(評基通4-3)。 |
| 塀等の設備 |
門、塀、外井戸、屋外じんかい処理設備等の附属設備の価額は、その附属設備の再建築価額から、建築の時から課税時期までの期間(1年未満の端数があるときは、その端数は1年)の定率法により計算した償却費の額の合計額を控除した金額の70%に相当する金額によって評価します(評基通92⑵) |
| 変額保険金(契約に関する権利) |
変額保険(保険金額と解約返戻金が運用に応じて変動する保険)は、「生命保険金」(相法3、12)又は「生命保険契約に関する権利の評価方法」(評基通214)により評価します。 |
| 変動金利定期預金 |
変動金利定期預金(適用金利が一定期間ごとに変更される定期預金)の価額は、次の算式によって評価します(評基通203)。 変動金利定期預金 = 預入高 + 解約利息の額(源泉税控除後) |
| 保安林等の土地 |
森林法その他の法令の規定に基づき土地の利用又は立木の伐採について制限を受けている山林の価額は、その山林の評価額(倍率方式により評価すべき場合は、近傍の固定資産税評価額)から、その価額に、それらの法令に基づき定められた伐採制限に基づく控除割合(一部皆伐0.3、択伐0.5、単木選伐0.7、禁伐0.8)を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価します(評基通50、123)。 保安林等の土地 = 山林の評価額 - ( 山林の評価額 × 伐採制限に基づく割合 ) |
| 保安林等の立木 |
森林法その他の法令に基づき伐採の禁止又は制限を受ける立木の価額は、森林等の立木の評価額から、その価額に、それらの法令に基づき定められた伐採制限に基づく控除割合(一部皆伐0.3、択伐0.5、単木選伐0.7、禁伐0.8)を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価します(評基通123)。 保安林等の立木 = 立木の評価額 -( 立木の評価額 × 伐採制限に基づく割合) |
| 法会費用 |
法会費用は、相続税法基本通達13-5に列挙されている「葬式費用とならないもの」に該当するので、葬式費用として債務控除できません。 |
| ボート |
プレジャーボート(モーターボート、ヨット等海洋レクリエーションに使用される小型船舶)は、売買実例価額(船舶業者等の買取価額など)、精通者意見価格等を参酌して評価します(評基通136)。 |
| 牧場 |
牧場の価額は、「原野の評価方法」(評基通57)に準じて、①純原野及び中間原野(通常の原野と状況を異にするため純原野として評価することを不適当と認めるもの)は、倍率方式、②市街地原野は、宅地比準方式又は倍率方式により評価します(評基通61)。 |
| 保証期間付終身年金 |
保証期間付終身年金(終身定期金のうち被保険者が年金支払期間の中途で死亡した場合であっても一定の保証期間内は死亡後に年金が支払われる年金)は、有期定期金として算出した金額と終身定期金として算出した金額のいずれか多い金額により評価します(相法24⑤)。 |
| 保証金 |
不動産賃貸の際に授受される保証金は、賃貸契約の内容に応じて、課税時期における返還すべき金額は、借主にとっては財産(債権)となり、貸主にとっては債務となります。定期借地権等の設定に際に保証金等(保証金、敷金などその名称のいかんを問わず借地契約の終了の時に返還を要するものとされる金銭等)の授受がある場合には、借地人にとっては、債権額を、地主にとっては債務額を計上しますが、この場合の保証金等は、次の①と②の合計額となります。
|
| 保証債務 |
保証債務は、原則として、債務控除できません。ただし、債務者が弁済不能の状態にあり、かつ、債務者に求償して返還を受ける見込みがない場合には、債務者が弁済不能の部分の金額は、当該保証債務者の債務として控除することができます(相基通14-3)。 |
| 墓石、墓地、墓碑、墓所 |
墓石、墓地、墓碑、墓所は、相続税法第12条(相続税の非課税財産)第1項第2号の「墓所、霊びょう、及び祭具並びにこれらに準ずるもの」の「墓所、霊びょう」に含まれ、相続税の課税財産とはなりません。 |
| 歩道状空地 |
歩道状空地(その宅地の位置関係、形状等や道路としての利用状況、これらを踏まえた道路以外の用途への転用の難易等に照らし、客観的交換価値に低下が認められるもの)は、私道の評価(評基通24)により評価します。 平成29年2月28日最高裁判例 |
| 埋蔵文化財包蔵地 |
埋蔵文化財包蔵地の価額は、その土地が埋蔵文化財包蔵地でないものとして評価した価額から、発掘調査費用相当額の80%相当額を控除して計算します(令和6年6月21日「土壌汚染地等の評価の考え方について(情報)」) 埋蔵文化財包蔵地 = その土地の評価額 - 発掘調査費用相当額 × 80% |
| 埋葬料、埋葬費 |
埋葬料、埋葬費は、被相続人ではなく相続人が受け取るべきものであり、相続財産とはなりません。なお、健康保険法により支給される埋葬料、埋葬費は、非課税と規定されていますので相続人の所得にもなりません。 |
| 前受賃料 |
相続開始日において、賃貸借契約の支払期日前に入金がある賃料は、前受賃料として債務控除します。なお、既に収入すべき期限が到来しているもので、まだ収入していない賃料は未収賃料として相続財産に加算します(評基通208)。 |
| 前払保険料 |
前払保険料は、原則として、本来の相続財産となりますが、死亡保険金とともに支払いを受ける前払保険料の額は、相続税法第3条第1項第1号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされる保険金とされます(相基通3-8)。 |
| 間口の狭い宅地 |
路線に接する間口の狭い宅地は、路線価に「奥行価格補正率」及び「間口狭小補正率」を乗じ、さらに奥行が長大な宅地については、「奥行長大補正率」を乗じた価額によって評価します。 間口狭小宅地 = 路線価 × 奥行価格補正率 × 間口狭小補正率 × 奥行長大補正率 × 地積 |
| マンション |
令和6年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した特定の要件を満たす居住用の区分所有財産(分譲マンション)の価額については、「居住用の区分所有財産の評価について」(法令解釈通達)により評価します。 |
| マンション敷地内の共有地 |
マンションの敷地の用に供されている宅地等で、多数の者により共有されている宅地の価額は、その敷地全体を評価した価額に、その共有者の共有持分の割合を乗じた金額で評価します。なお、そのマンション敷地に公衆化している道路等の施設の用に供されており、この評価方法により評価することが著しく不適当であると認められる場合には、その公衆化している道路等の施設の用に供されている宅地部分を除いて評価して差し支えないとされています。 庁事例集273←頁じゃないが削除か? |
| マンスリーマンション |
マンスリーマンション(一般的には、賃貸の住居を月単位で借りるサービスで、借地借家法の定期建物賃貸借契約に基づいて運営されています。)の価額は、居室の賃貸借ですが借家権がないことから、その敷地はホテルや宿屋の敷地と同様に、自用地価額で評価します。なお、その建物についても自用家屋として評価します。 |
| 未経過保険料 |
相続や遺贈によって取得したものとみなされる保険金には、本来の保険金のほか、保険契約に基づき分配を受ける剰余金、割戻しを受ける割戻金及び払戻しを受ける前納保険料で、保険金とともに受け取るものも含まれます(相基通3-8)。 |
| 未支給年金 |
未支給年金とは、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものをいい、死亡した受給権者の遺族の固有の権利であり、相続税の課税対象にはなりません。なお、未支給年金は、支給を受けた遺族の一時所得となります(所基通34-2) |
| 未収賃料 |
相続開始日において、賃貸借契約の支払期日が到来しているもので、まだ収入していない賃料は未収賃料として相続財産に加算します。なお、契約上の支払期日前に支払いのあった賃料は前受賃料として債務控除します(評基通208) |
| 未収天然果実 |
課税時期において、その後3か月以内に収穫することが予想される果実、立毛等の天然果実は、その天然果実の発生の基因となった財産とは別に評価するものとし、その価額は、課税時期における現況に応じ、収穫時において予想されるその天然果実の販売価額の70%に相当する金額の範囲内で相当と認める価額によって評価します(評基通209)。 |
| 未収入金 |
未収入金の価額は、元本の価額(その返済されるべき金額)と利息の価額(課税時期現在の既経過利息として支払を受けるべき金額)との合計額によって評価します(評基通204)。 |
| 未収配当金 |
配当金交付に関する株主総会決議の翌日から配当金を受け取るまでの間に相続が発生した場合の未収配当金は、予想配当の金額から当該金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額によって評価します(評基通193)。 |
| ミニ株 |
ミニ株(上場株式の取引単位未満株で売買できる制度)の価額は、「上場株式の評価」(評基通169)に準じて評価します。 |
| ミニゴルフ場の敷地 |
ミニゴルフ場と呼ばれるものは、その規模が千差万別であるため、個々のミニゴルフ場ごとにその規模等の状況から判定することになりますが、次のような規模を有するもの(大工場地区に所在するものを除きます。)については、「ゴルフ場用地の評価」(評基通83)を準用して評価し、これに該当しないものは、「雑種地の評価」(評基通82)の定めにより評価します。
|
| 未払金 |
被相続人の未払金を引き継いだ相続人(相続を放棄した者及び相続権を失った者を除きます。)又は受遺者(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈)は、債務控除することができます(相法13、相基通13-1)。なお、墓地や仏壇などの非課税財産に係る未払金は債務控除することができません。 |
| 民泊建物の敷地 |
民泊(一般的には、既存の住宅を1日単位で利用者に貸し出すもので、住宅宿泊事業法の規定に基づいて運営されています。)は、居室の賃貸借ですが借家権がないことから、その敷地はホテルや宿屋の敷地と同様に、自用地価額で評価します。なお、その建物についても自用家屋として評価します。 |
| 無議決権株式 |
無議決権株式の価額は、原則として、議決権の有無を考慮せずに原則的評価方式により評価します。なお、一定の要件を満たす場合は原則的評価方式により評価した価額から、その価額に5%を乗じて計算した金額を控除した金額により評価するとともに、当該控除した金額を当該相続又は遺贈により同族株主が取得した当該会社の議決権のある株式の価額に加算して申告することを選択することができます。 |
| 無期定期金 |
無期定期金は、次の①~③のいずれか多い金額によって評価します(相法24①二)。
|
| 無償返還の届出書が提出されている貸宅地 |
無償返還届出書が提出されている貸宅地の価額は、自用価額の80%で評価します。なお、使用貸借(権利金や地代のやり取りがなく借主が無償で利用している場合)に係る土地について無償返還届出書が提出されている場合は、自用地として評価します。 無償返還の届出書が提出されている貸宅地 = 自用価額 × 80% |
| 無償返還の届出書が提出されている借地権 |
無償返還届出書が提出されている借地権の価額は、評価しません。ただし、当該土地を借地している会社が被相続人の関係する同族会社である場合は、当該同族会社の株式の評価上、自用地の評価額×20%を純資産価額に算入します。 |
| 無尽 |
無尽(複数の個人や法人等が講等の組織に加盟して、金品を定期又は不定期に講等に対して払い込み、利息の額で競合う競りや抽選によって金品の給付を受ける権利)の価額は、課税時期までの掛金総額によって評価します(評基通207)。 |
| 無選択型終身保険金(契約に関する権利) |
無選択型終身保険(被保険者についての健康状態の告知のない生命保険)は、「生命保険金」(相法3、12)又は「生命保険契約に関する権利の評価」(評基通214)により評価します。 |
| 無道路地 |
無道路地とは、道路に接していない宅地(接道義務を満たしていない宅地を含みます。)をいい、実際に利用している路線の路線価に基づき不整形地の評価によって計算した価額から、接道義務を満たす通路部分の価額(その価額の40%の範囲内)を控除するなどして評価します(評基通20-3)。 |
| 無保険車傷害保険契約に係る保険金 |
無保険車傷害保険契約に基づいて取得する保険金は、損害賠償金としての性格を有することから、相続税法第3条第1項第1号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされる保険金には含まれません(相基通3-10)。 |
| 名義株 名義預金 |
相続税の対象となる財産は、財産の名義にかかわらず実質的に被相続人に帰属していたものです。名義財産の帰属の判定においては、①出捐者(資金の拠出者)は誰か、②通帳や印鑑の管理者は誰か、③利益の享受者は誰か、④処分者は誰か、⑤名義人、出捐者、管理者等との関係はどうかなどの事情を考慮して判断します。 |
| モーターボート |
プレジャーボート(モーターボート、ヨット等海洋レクリエーションに使用される小型船舶)は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します(評基通136)。 |
| 持株会 |
持株会(従業員が当該会社の株式を取得することを目的とする組織で、組織形態は民法第667条第1項に基づく組合)の所有する株式は組合員の共有となりますが、「取引相場のない株式の評価」(評基通178)においては、個々の組合員が所有しているものとして評価します。 |
| 持分会社の出資金 |
持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社)の出資金の価額は、①持分を承継する場合は、「取引相場のない株式の評価」(評基通178)に準じて評価し、②持分の払戻しを受ける場合は、持分の払戻請求権として評価し、評価すべき持分会社の課税時期における各資産を財産評価基本通達の定めにより評価した価額の合計額から課税時期における各負債の合計額を控除した金額に、持分を乗じて評価します(評基通194)。 |
| 門、塀等の設備 |
門、塀、外井戸、屋外じんかい処理設備等の附属設備の価額は、その附属設備の再建築価額から、建築の時から課税時期までの期間(1年未満の端数があるときは、その端数は1年)の定率法により計算した償却費の額の合計額を控除した金額の70%に相当する金額によって評価します(評基通92⑵)。 |
| 役員退職金 |
役員退職金は、①被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合は、相続又は遺贈により取得したものとみなされ(相法3①二)、②3年経過後に支給が確定したものは相続人の一時所得になります(所基通34-2)。 |
| やみ小作地 |
農地に賃借権等の権利を設定するためには農地法第3条の定めるところにより都道府県知事(現行原則として農業委員会)の許可を受けなければならないので、いわゆるやみ小作については、耕作権を認めることはできません。したがって、その農地は自用地として評価します。 |
| 遊園地用地 |
遊園地、運動場、競馬場その他これらに類似する施設の用に供されている土地の価額は、原則として、「雑種地の評価」(評基通82)を準用して評価します。その規模等の状況からゴルフ場用地と同様に評価することが相当と認められる遊園地等の用に供されている土地の価額は、「ゴルフ場用地の評価」(評基通83)の定めを準用して評価します(評基通83-2)。 |
| 有価証券オプション取引 |
有価証券オプション取引は、①オプションの買い手は課税時期の市場のオプション価格が相続財産となり、②オプションの売り手は引受価格(オプション料)から課税時期の市場のオプション価格を差し引いた金額が相続財産又は債務となります。 |
| 有期定期金 |
有期定期金は、次の①~③のいずれか多い金額によって評価します(相法24①一)
|
| 優先株 |
配当優先株式(利益配当に関して優先した取扱いを受ける株式)の価額は、①類似業種比準方式で評価する場合は、1株当たりの配当金額について、株式の種類ごとに計算して評価、②配当還元方式で評価する場合は、株式の種類ごとに実際の配当金により評価します。 |
| 養育年金付こども保険 |
養育年金付こども保険に係る保険契約者が死亡した場合の年金受給権は、保険契約者が負担した保険料に対応する部分は生命保険金とみなされ(相法3①一)、保険契約者以外の者が負担した保険料に対応する部分は、贈与により取得したものとみなされます(相法5①)。 |
| 容積率の異なる地域にわたる宅地 |
容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地は、その宅地の評価額から、その価額に次の算式により計算した割合を乗じて計算した金額を控除することにより評価します(評基通20-7)。
( 1 - |
| 養老保険 |
養老保険(被保険者が一定の年齢に達するまで生存したとき、又は保険期間内に死亡したときに保険金が支払われるもの)は、「生命保険金」(相法3、12)又は「生命保険契約に関する権利の評価」(評基通214)により評価します。 |
| 余剰容積率の移転を受けている宅地 |
自用地としての価額を基に、容積率の制限を超える延べ面積の建築物を建築するために設定している権利の内容、建築物の建築状況等を勘案して評価することとされていますが、次の算式により計算した金額によって評価できるとされています(評基通23、23-2)。 自用地価額 ×( 1 + 支払った対価の額 ÷ 移転前の宅地の通常の取引価額 ) |
| 余剰容積率を移転している宅地 |
余剰容積率を移転している宅地の価額は、自用地としての価額を基に、設定されている権利の内容、建築物の建築制限の内容等を勘案して評価することとされていますが、次の算式により計算した金額によって評価できるとされています(評基通23、23-2)。 自用地価額 ×( 1 - 収受した対価の額 ÷ 移転前の宅地の通常の取引価額 ) |
| 預託金 |
預託金(一定の金額を無利息で預け入れる金銭)は、貸付金債権(預貯金以外の預け金)の評価方法(評基通204)に準じて評価します。 |
| 預託金制のゴルフ会員権 |
預託金制のゴルフ会員権の価額は、①取引相場のあるものは、通常の取引価格の70%相当額で評価し、取引価格に含まれない預託金等があるときは、返還時期に応じた預託金等の評価額との合計額で評価し、②取引相場のないものは、返還時期に応じた預託金等で評価します(評基通211)。 |
| 預託保証金 |
預託保証金(信用取引、FX取引等で証券会社等に取引開始前に預託している金銭)は、貸付金債権(預貯金以外の預け金)の評価方法(評基通204)に準じて評価します。 |
| 預貯金 |
預貯金は、次の算式によって評価します。ただし、定期預金、定期郵便貯金及び定額郵便貯金以外の預貯金については、課税時期の既経過利子の額が少額なものに限り、同時期現在の預入高によって評価することができます(評基通203)。 預貯金 = 預入高 + 解約利息の額(源泉税控除後) |
| リート(REIT) |
上場不動産投資信託(J-REIT)は、上場株式に準じて評価します。なお、不動産投資信託証券に係る投資口の分割等に伴う無償交付期待権の価額は株式無償交付期待権の評価に準じて評価し、金銭分配期待権の価額は配当期待権の価額に準じて評価します(評基通169、192、193、213)。 |
| 利子税 |
被相続人に係る利子税を負担した相続人(制限納税義務者は、取得した財産でこの法律の施行地にあるものについて負担した公租公課に限ります。)は、債務控除することができます(相法13)。ただし、相続人などの責任に基づいて納付されることになった附帯税(延滞税、利子税及び加算税)は差し引くことはできません。 |
| 利付債 利付公社債 |
利付債の価額は、①金融商品取引所に上場しているもの、②証券業協会で公表しているもの、③上記以外のものとに区分して、次のように評価します(評基通197~197-5)。
|
| リバース・デュアル・カレンシー債 |
リバース・デュアル・カレンシー債(払込みと償還が日本円で、利払いが日本円以外の通貨の外国債券)は、利付債の評価方法に準じて評価します(評基通197~197-5)。なお、邦貨換算は、対顧客直物電信買相場(TTB)により計算します(評基通4-3)。 |
| 立竹 |
立竹(庭園にある立竹を除きます。)の価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します(評基通124)。なお、庭園にある立竹の価額は、庭園設備と一括して庭園設備の評価の定め(評基通92)により評価します(評基通125)。 |
| 立木 |
立木は、①森林の立木、② ①以外の立木、③庭園にある立木に区分して評価します(評基通111)。なお、相続又は包括遺贈により取得した立木の価額は、立木の評価額に85%を乗じた金額によることができます(相法26)。
|
| 利用価値の著しく低下している土地 |
普通住宅地区にある宅地で、その利用価値が付近にある他の宅地の利用状況からみて、著しく低下しているものの価額は、利用価値が低下していると認められる部分の面積に対応する価額に10%を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価することができます。ただし、路線価又は倍率が状況を考慮して付されている場合には、この斟酌はしません。 |
| 旅行券 |
商品券や旅行券、ギフト券、クオカード、株主優待券などの金券は、相続財産になり、額面金額又は売買実例価額(ネットなどの相続開始日の買取価格)で評価します(相法22)。 |
| 利率変動型積立終身保険 |
利率変動型積立終身保険(市場の金利動向によって積立利率が変動し、積立に対する保険金や解約返戻金が変動する保険)は、その契約内容によって生命保険金又は定期金に関する権利の評価方法により評価します(相法3、24)。 |
| 臨時的な使用に係る賃借権 |
臨時的な使用に係る賃借権及び賃貸借期間が1年以下の賃借権(賃借権の利用状況に照らして賃貸借契約の更新が見込まれるものを除きます。)については評価しません。また、この場合の賃借権の目的となっている雑種地の価額は、自用地価額で評価します。 |
| るいとう |
るいとう(選択した上場銘柄を毎月一定額購入していく株式取引)の評価額は、上場株式の評価方法に準じて評価します(評基通169)。 |
| 霊柩車費用 |
相続人(無制限納税義務者)又は包括受遺者が支出した霊柩車の費用は、葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において要する費用であり、葬式費用として債務控除できます(相基通13-4)。 |
| 礼状の作成費用 |
相続人(無制限納税義務者)が支出した会葬者へのお礼状に係る費用は、葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において要する費用であり、葬式費用として債務控除できます(相基通13-4)。 |
| 霊びょう |
霊廟は、相続税法第12条(相続税の非課税財産)第1項第2号の「墓所、霊びょう、及び祭具並びにこれらに準ずるもの」の「霊びょう」に該当し、相続税の課税価格には算入しません。 |
| 歴史的風致形成建造物である家屋及びその敷地 |
歴史的風致の維持及び向上に関する法律に基づき歴史的風致形成建造物に指定された家屋及びその敷地の用に供されている宅地は、「伝統的建造物である家屋及びその敷地の用に供されている宅地の評価方法」(評基通24-8、89-2)に準じ、次の算式により評価します。 歴史的風致形成建造物である家屋及びその敷地の用でないものとした場合の価額 × 70% |
| 連帯債務 |
連帯債務は、連帯債務者のうちで債務控除を受けようとする者の負担すべき金額が明らかとなっている場合には、当該負担金額を控除します。なお、連帯債務者のうちに弁済不能の状態にある者があり、かつ、求償して弁済を受ける見込みがない場合には、その負担しなければならない部分の金額も債務控除することができます(相基通14-3)。 |
| 老人ホームの入居保証金 |
老人ホームの入居保証金は、入居契約書の退去時受取人欄に記載された者への「みなし贈与」との裁決事例がありましたが、平成28年の東京高裁の判決により「本来の相続財産」であることになりました。 |
| 路線価の付されていない土地 |
路線価地域内において、相続税又は贈与税の課税上、路線価の設定されていない道路のみに接している宅地を評価する必要がある場合には、その宅地を評価するための路線価(特定路線価)の評価対象地を管轄する税務署に申請して評価します(評基通14-3)。 |
| 割引債 割引発行公社債 |
割引債の価額は、①金融商品取引所等に上場しているもの、②証券業協会で公表しているもの、③上記以外のものに区分して、次のように評価します(評基通197-3)。
|
文責:
-

- 税理士 天池 健治
- 天池 健治 税理士のプロフィール
- 税理士 / 証券アナリスト / 宅建士 / 公認コンサルタント