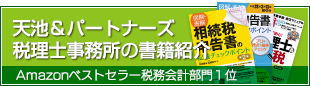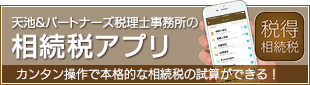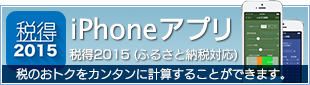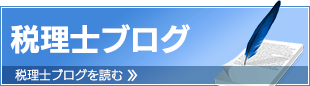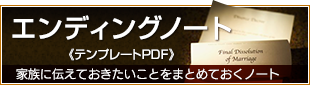税金お役立ち情報
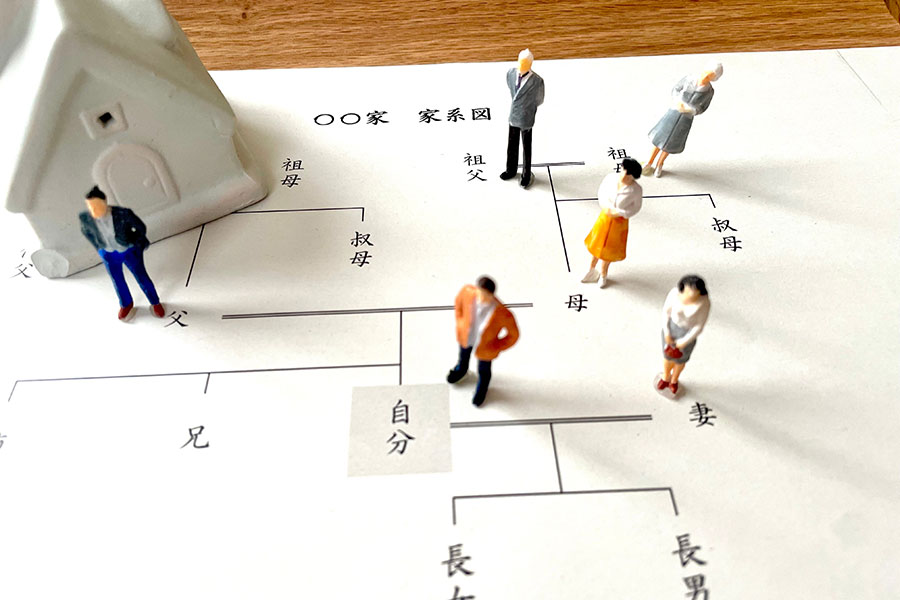
法定相続人の範囲と優先順位について詳しく解説
相続手続きを進める上で「法定相続人」の正確な理解は欠かせません。
誰が相続権を持ち、どのような順位で相続が行われるのかを把握しておく必要があります。
本記事では、法定相続人となれる人物の範囲と優先順位、代襲相続制度の概要、法定相続人に関する注意点について解説します。
法定相続人の定義
「法定相続人」とは民法によって定められた相続資格を持つひとのことです。
遺言書が存在しない場合、法定相続人全員による話し合いを通じて遺産分配の方法を決定していきます。
法定相続人と相続人に違いはあるのか?
法定相続人と相続人は、ほぼ同じような意味で使われることがありますが異なる考えです。
法定相続人は、被相続人が亡くなった時点で、法律上の相続権を持っているひとを指します。
これに対し、相続人は実際に被相続人の財産を受け継ぐひとのことです。
一般的には、法定相続人と相続人は同一人物となるケースが多いですが、法定相続人であっても相続放棄の手続きをした場合は相続人にはなりません。
法定相続人には範囲と優先順位が定められている
法定相続人となる資格を持つのは故人の配偶者と血族関係にあるひとたちです。
血族については明確な優先順位が設けられており、上位のひとが法定相続人としての地位を得ることになります。
以下では、法定相続人の範囲と順位について見ていきます。
必ず法定相続人となれる配偶者
配偶者(妻または夫)は、家族構成にかかわらず、常に法定相続人です。
家族の状況や他の親族関係にかかわらず、婚姻関係にある配偶者は常に相続の権利を持ちます。
ただし、婚姻届を提出していない内縁関係にある配偶者については、法律上の配偶者とは認められないため法定相続人にはなりません。
優先的に法定相続人となるのは子ども【第1順位】
血族の中でも被相続人の子どもは、最も高い第1順位の法定相続人です。
配偶者が存命の場合は、法定相続人は配偶者と子どもとなり、配偶者がいない状況では子どもだけが法定相続人となります。
なお、被相続人よりも先に子供が亡くなっているケースである「代襲相続」については後述します。
子どもがいない場合に法定相続人となるのは父母【第2順位】
父母の相続順位は第2順位で、被相続人の子どもが既にいない場合の法定相続人です。
この場合の父母とは、被相続人の親のことを指し、配偶者の父母は含まれないので注意しましょう。
父母の両方が既に亡くなっている状況では、さらに上の世代の祖父母へ、そして祖父母も存命でない場合は曾祖父母へと順に相続権が移行していきます。
子どもも父母もいなければ兄弟姉妹が法定相続人【第3順位】
被相続人の兄弟姉妹は、被相続人に子どもがおらず、両親や祖父母もいない場合に法定相続人になることができ、順位は第3順位です。
この場合、被相続人の配偶者がいれば、配偶者と一緒に兄弟姉妹が相続人となります。
相続において兄弟姉妹の優先順位は最後のため、第1順位や第2順位の相続人がいる場合には法定相続人とはなりません。
相続開始前に子どもや兄弟姉妹が死亡していると代襲相続が適用
代襲相続が適用されるのは、法定相続人である子どもや兄弟姉妹が、被相続人よりも先に亡くなっている場合です。
代襲相続について、以下で詳しく見ていきましょう。
代襲相続に関する基礎知識
本来、法定相続人になる人物が被相続人よりも先に亡くなっている場合に、その直系卑属が相続権を引き継ぐのが代襲相続制度です。
本来であるならば、子どもが第1順位、父母が第2順位、兄弟姉妹が第3順位となりますが、代襲相続が発生すると孫やひ孫、甥や姪が相続人になることがあります。
代襲相続人と優先順位の関係
代襲相続によって孫やひ孫、甥や姪が相続人となる場合、その代襲相続人は被代襲者と同じ優先順位を引き継ぎます。
つまり、代襲相続人は被代襲者が持っていたはずの相続順位をそのまま受け継ぐのです。
代襲相続が生じるケース・生じないケース
代襲相続は、相続人が被相続人より先に亡くなった場合に発生しますが、他の特定の状況でも適用されることがあります。
もともとの相続人が相続放棄した場合には代襲相続は発生しません。
しかし、相続人が相続欠格になったり、廃除になったりした際には代襲相続が発生します。
法定相続人の範囲と相続順位に関する注意点
多くの場合、被相続人が離婚経験があり、元配偶者との間に子どもがいる場合や、再婚して新しい配偶者との間に子どもがいるケースでは判断が難しくなるでしょう。
離婚と再婚のケースでは、以下の注意点に留意する必要があります。
離婚した元配偶者との間の子どもは相続権を持つ
被相続人が離婚していても、元配偶者との間の子どもは血縁関係があるため相続人になります。
再婚後に生まれた子どもも同様です。
ただし、元配偶者自身は、婚姻関係がないため相続人にはなれません。
再婚した配偶者の連れ子は相続権を持たない
子どもを連れて再婚した場合、再婚相手の連れ子の間には、自動的に法律上の親子関係が発しません。
そのため、連れ子には被相続人の遺産を相続する権利はありません。
連れ子に遺産を残したい場合、養子縁組を行って法的な親子関係を結ぶか、遺言書を作成して財産を譲るという手続きが必要です。
養子は実子と同等の相続権を持つ
被相続人の養子は法律によって法定相続人と定められています。
養子の相続順位は第1順位であり、相続の割合も実子とまったく同じです。
血縁関係ではありませんが、法的な親子関係が成立しており、実子と異なる扱いをされることはありません。
まとめ
民法で定められた相続権を持つひとが法定相続人です。
配偶者は必ず法定相続人になることが定められており、子ども、父母、兄弟姉妹の順に優先順位がつけられています。
代襲相続では、先に亡くなった相続人の子が権利を引き継ぎます。
また、養子は実子と同等の権利をもちますが、再婚した相手の子ども(連れ子)は相続権がないので注意しましょう。
相続問題は複雑なケースも多いため、司法書士へ相談することがおすすめです。
文責:
-

- 税理士 天池 健治
- 天池 健治 税理士のプロフィール
- 税理士 / 証券アナリスト / 宅建士 / 公認コンサルタント