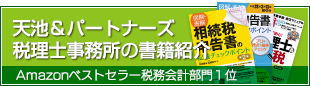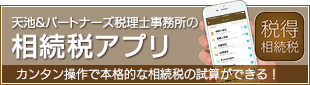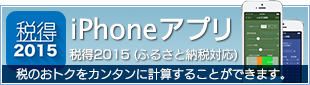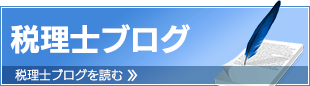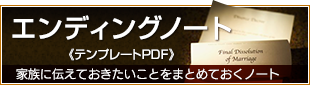税金お役立ち情報

遺留分とは?遺留分の基本的な知識と遺留分侵害額請求について解説
相続において、遺言書のある場合には、原則的に遺産はその内容の通りに分割することになります。
ただし、特定の相続人には、遺留分という権利が認められています。今回は、遺留分について、基本的な知識と遺留分侵害額請求について解説していきたいと思います。
遺留分とは?
遺留分とは、法律で定められた一定の相続人に保障される最低限の相続財産の割合のことです。
この制度は、被相続人の死後残された相続人の生活の保障を目的に設けられました。
相続において遺言書は非常に強い効力を持っていますが、それでも侵害できない権利が遺留分です。
ただし、遺留分は自動的に保障されるものではなく、遺留分を侵害された場合には、侵害した相続人に対して権利を主張して、侵害分を請求する必要があります。
たとえば「長男に全ての財産を相続させる」などの偏った遺言書があった場合について考えてみましょう。
長男が被相続人の遺産をすべて手に入れることに対して、他の相続人が納得しているのであれば、遺留分にはなりません。
遺留分が認められる相続人の範囲
遺留分が認められる相続人の範囲は、法定相続人となった被相続人の配偶者、子ども、孫、両親、祖父母です。
兄弟姉妹や甥や姪については、法定相続人であっても遺留分は認められません。
遺留分の割合について
遺留分は通常、遺産総額の半分、または3分の1の金額と定められており、具体的な割合は、相続人の組み合わせによって異なります。
配偶者のみの場合、遺留分は遺産全体の2分の1となります。
配偶者、子どもの場合、配偶者の遺留分は遺産全体の4分の1、子どもについては1人の場合遺産全体の4分の1、複数人いる場合には、4分の1×子どもの人数で遺留分を算出していくことになります。
配偶者、直系尊属の場合、配偶者の遺留分は遺産全体の3分の1、直系尊属が1人の場合6分の1となり、2人の場合には12分の1となります。
子どものみの場合、遺留分は遺産全体の2分の1となり、複数人いる場合には、2分の1×子どもの人数で遺留分を算出していくことになります。
直系尊属のみの場合、遺留分は遺産全体の3分の1となり、2人の場合には6分の1となります。
遺留分侵害額請求の時効と除斥期間
仮に遺言書に従って相続した結果、一部の相続人が自身の遺留分を下回る財産しか受け取れなかった場合など自身の遺留分が侵害されていることに気づいた場合、その相続人は遺留分に不足する金額を遺産を多く受け取った人に請求していくことになります。
この請求のことを遺留分侵害額請求といいます。
遺留分侵害額請求を請求するためには、期限が定められています。
時効については、自己の遺留分が贈与などによって侵害されたことを知った日から1年と定められています。
また、排斥期間についても定められており、遺留分が侵害されていることを知らない場合でも、相続が開始してから10年経過すると、期間の経過によって権利が消滅してしまうので注意が必要です。
遺留分侵害額請求の流れ
遺留分侵害額請求を行うとき、まずは相手との話し合いから始めます。
電話やメールなどで話を持ちかけても良いですが、内容証明郵便で請求書を送ってから話し合うことで、時効を中断することにもつながるので、相手方への請求をしてから話し合いをするのもいいかもしれません。
相続人同士で合意できたら遺留分侵害額についての合意書を作成し、内容に沿って支払いを受けることになります。
話し合いをしても合意できない場合には、家庭裁判所で遺留分侵害額の請求調停を申し立てることになります。
裁判所の管轄は、相手の住所地の家庭裁判所になります。
調停を申し立てると、家庭裁判所の調停委員が間に入って調整を進めてくれます。
遺留分侵害額の金額や支払い方法について合意することができた場合には、調停が成立して、遺留分が侵害されている金額を払ってもらえます。
調停が成立しない場合には、遺留分侵害額請求訴訟を管轄の地方裁判所で行うことになります。裁判で主張を認めてもらうには、法的に正しい主張を行い、それを根拠づける資料の提出が必要です。
まとめ
今回は、遺留分について、基本的な知識と遺留分侵害額請求について確認していきました。
明らかに不公平な遺言書が見つかったり、多額の贈与が行われている場合など、遺留分の権利を主張し、遺留分侵害額請求を行うことができる可能性があります。
ただし、自身で請求するには、手続きについてなど判断に迷うこともあるかもしれません。
遺留分が侵害されていることに気づいたら、専門的な知識をもつ弁護士に相談することを検討してみてください。
文責:
-

- 税理士 天池 健治
- 天池 健治 税理士のプロフィール
- 税理士 / 証券アナリスト / 宅建士 / 公認コンサルタント