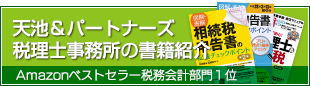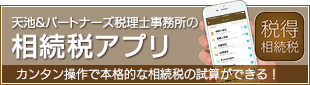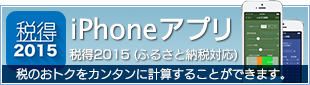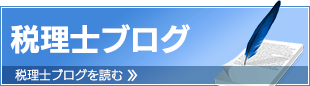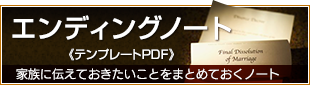税金お役立ち情報

相続税申告の手続きと必要書類|申告の期限について
相続税の申告は、相続が発生した後に避けて通れない重要な手続きです。
相続税は、期限や必要書類が細かく定められており、適切に対応しないと延滞税や加算税などのペナルティが発生するおそれがあります。
本記事では、相続税申告の基本的な流れや必要書類、申告期限について紹介します。
相続税申告が必要なケース
相続税申告は、すべての相続で必要というわけではありません。
「基礎控除額」を超える遺産がある場合は、申告と納税が必要となります。
基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
たとえば、配偶者と子1人が相続人の場合、基礎控除額は次のように計算されます。
この場合、相続財産が4,200万円以下であれば、相続税はかからず申告も不要です。
課税対象となる財産の例
課税対象となる財産には、不動産、預貯金、有価証券、自動車、などが含まれます。
一方で、住宅ローンなどの借入金や、未払の医療費・税金などの債務は、相続財産から差し引くことができます。
また、被相続人が亡くなったことにより受け取った生命保険金や退職金も対象となります。
ただし、生命保険金と死亡退職金には、それぞれ「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設けられており、この非課税枠を超えた場合に課税対象となります。
相続税申告の手続きの流れ
ここからは、相続税申告の基本的な流れについて見ていきます。
1. 被相続人の財産調査と評価
まずは、被相続人が所有していたすべての財産を洗い出します。
預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含めて確認し、全体の財産状況を正確に把握します。
さらに、調査した財産を相続税のルールに従って評価します。
不動産については、路線価や固定資産税評価額を基に評価し、株式などの有価証券は相続が発生した時点の時価などを参考にして金額を算出します。
2. 相続人の確定
次に、誰が相続人となるかを確認します。
被相続人の戸籍謄本を収集し、法定相続人を確定させます。
3. 遺言書の確認と遺産分割協議
遺言書が存在するかどうかを調べ、それに基づく対応を検討します。
遺言がない場合は、相続人全員で話し合いを行い、財産の分け方を決定します。
このとき、「遺産分割協議書」を作成しておくと、今後の手続きが円滑に進みます。
4. 相続税の計算
相続財産の合計額から基礎控除を差し引いて、課税対象となる金額を求めます。
さらに、配偶者控除や、小規模宅地等の特例など、適用可能な制度を加味して最終的な税額を計算します。
なお、相続財産が基礎控除の範囲内に収まる場合は原則として申告は不要ですが、特例の適用を受けるには申告が必要になるケースもあるため、事前に確認しておくことが大切です。
5. 相続税の申告書作成と提出
評価が完了し、分割内容が確定したら、相続税申告書を作成します。
その際には、遺産分割協議書や戸籍謄本などの必要書類を添付し、被相続人の住所地を管轄する税務署に提出します。
相続税申告の期限
相続税の申告と納税は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
この期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課される場合があります。
ただし、納税額が高額で一括での納税が困難な場合には、延納や物納といった制度を利用できます。
相続税申告に必要な書類
相続税申告に必要な書類は、被相続人の財産内容や相続の状況によって多少異なりますが、主に以下の書類を準備する必要があります。
戸籍関連書類
被相続人と相続人の身分関係を証明するための書類として、以下を用意します。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続関係説明図(ある場合)
財産関係書類
相続の対象となる財産の内容や評価額を確認するために、次のような書類が必要です。
- 預貯金の残高証明書
- 不動産の登記簿謄本および固定資産税評価証明書
- 株式や投資信託の残高証明書
- 生命保険の支払通知書
債務・葬式費用に関する書類
相続財産から控除できる債務や葬儀費用があれば、それを証明するための書類が必要です。
- 住宅ローンや借入金の残高証明書
- 未払医療費や未払税金の明細
- 葬儀にかかった費用の領収書
遺産分割関係書類
相続人の間での遺産分割の合意や手続きを示すための書類も必要です。
また、配偶者控除や小規模他宅地等の特例など、一定の特例制度を適用する際には、必ず必要となります。
- 遺言書または遺産分割協議書
- 相続人の印鑑証明書
- 申告期限後3年以内の分割見込書(分割が期限内にできない場合)
まとめ
相続税申告は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
申告の際には、戸籍謄本や財産の証明書類、評価資料、分割協議書など、多くの書類が必要になるため、スムーズに適切な書類を揃え、計画的に進めることが大切になります。
相続税の計算や手続きに不安がある場合は、税理士に相談することをおすすめします。
文責:
-

- 税理士 天池 健治
- 天池 健治 税理士のプロフィール
- 税理士 / 証券アナリスト / 宅建士 / 公認コンサルタント