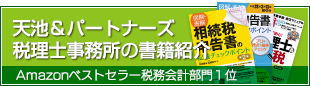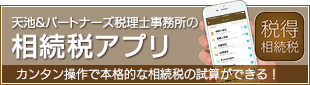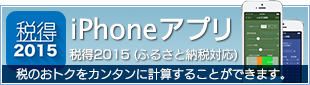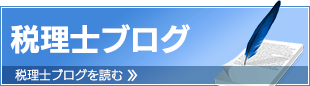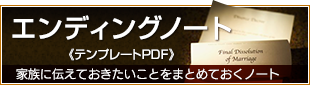税金お役立ち情報

相続税が0円でも申告は必要?
相続税の納税が生じない場合、申告を行わなくても良いと考える方も少なくないと思います。
しかし、実際には納税しなくても相続税の申告が必要なケースがあります。
本記事では、相続税の納税がなくても申告の必要があるケースなどについて解説します。
相続税が0円になるケースとは
相続税の計算結果が最終的に0円になる場合、申告が必要かどうかは、その理由によって異なります。
申告が不要となるのは、相続財産が最初から課税対象外となる非課税の範囲に収まっているケースです。
遺産総額が基礎控除額以下の場合
相続税には「基礎控除額」が設けられており、遺産総額がこの基礎控除額以下であれば、相続税は課税されません。
基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式で算出することができます。
たとえば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4800万円となります。遺産総額が4800万円を下回る場合は、相続税の申告も納税も一切不要です。
また相続税の課税対象は、遺産の総額から債務を差し引いた額になります。
遺産総額が基礎控除額を超えていたとしても、債務が差し引かれた後の金額が基礎控除額を超えなければ納税の義務は生じません。
遺産を相続しない場合
相続人が家庭裁判所に申し立てを行い、「相続放棄」が正式に受理された場合、その相続人は最初から相続人ではなかったものとみなされます。
相続放棄を行った場合、その相続人については相続税の納税義務が発生しないため、申告も原則として不要となります。
ただし、相続放棄をすると、負債だけでなく不動産などのプラスの財産などの一切の財産を承継する権利を失います。
なお、遺産分割協議の結果として不動産や現金といったプラスの財産を一切相続しないことで相続税の支払いを0円にすること自体は可能です。
ただし遺産を相続放棄せずにいると、実際は財産を取得していなくても、遺産に債務などのマイナスの財産がある場合、返済義務を負わなければならない可能性があるので注意が必要です。
特例を使うと相続税が0円でも申告が必要になる
相続税の特例は、納税額を大きく軽減できる強力な優遇措置ですが、これらを適用するためには、たとえ最終的な税額が0円になったとしても、税務署への申告手続きが義務付けられています。
申告を行うことで初めて特例の適用が認められるため、申告期限を守ることが重要です。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例は、被相続人の居住用や事業用の宅地について、一定の要件を満たす場合に、その評価額を最大で80パーセント減額できるという非常に大きな節税効果を持つ特例です。
この特例が適用されることで、宅地の評価額が大幅に下がり、結果として相続税額が0円になるケースがあります。
しかし、この特例の適用を受けるためには、必ず相続税の申告書に特例の適用を受ける旨を記載し、必要な書類を添付して申告期限内に提出しなければなりません。
申告期限を過ぎてしまうと、この特例は適用できなくなる可能性があり、本来の評価額で課税され、多額の相続税を納付しなければならなくなるため注意が必要です。
相続税の配偶者控除
相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)は、配偶者が取得した遺産のうち、「1億6千万円」または「法定相続分相当額」のいずれか多い金額まで相続税がかからないという強力な制度です。
この特例の適用により、多くのケースで配偶者が取得した財産に対して相続税が0円になりますが、納税額が0円になった場合も、例外なく税務署への申告が必要です。
申告書には、遺産分割協議書など、配偶者が実際にどの財産をどれだけ取得したかを証明する書類を添付しなければなりません。
この特例も小規模宅地等の特例と同様に、申告期限までに申告を行わなければ適用を受けることができない可能性があります。
まとめ
相続税の申告は、すべてのケースで必要というわけではありません。
遺産総額が基礎控除額や非課税枠内に収まる場合は、相続税額がゼロとなり、申告は不要です。
しかし、納税額を0円にするために「特例」を適用した場合は、たとえ最終的な納税額が0円であっても、必ず申告期限までに申告書を提出しなければなりません。
申告を怠ると特例の適用が受けられず、追徴課税の対象となることもあるので、ご自身のケースで特例を使うかどうかを確認し、申告が必要な場合は期限厳守で対応しましょう。
文責:
-

- 税理士 天池 健治
- 天池 健治 税理士のプロフィール
- 税理士 / 証券アナリスト / 宅建士 / 公認コンサルタント